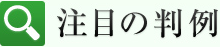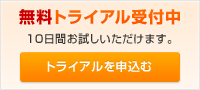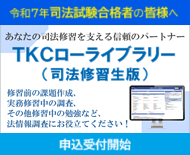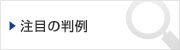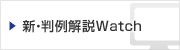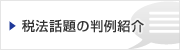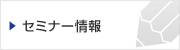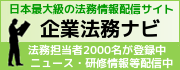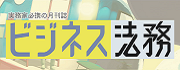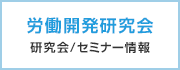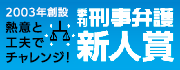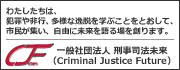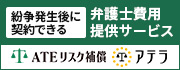2020.02.04
投稿記事削除請求事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 4月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
★「新・判例解説Watch」憲法分野 4月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25580335/東京地方裁判所 令和 1年10月11日 判決 (第一審)/平成30年(ワ)第66号 等
原告が、ツイッターに投稿された原告の過去の逮捕歴に係る本件各投稿記事により原告の前科等を公表されない利益や社会生活の平穏を害されない利益が侵害されていると主張して、同ウェブサイトを管理運営する被告に対し、前記各利益に係る人格権及び人格的利益に基づく妨害排除請求権に基づき、本件各投稿記事の削除を求めた事案において、本件各投稿記事がグーグルにおける検索結果では表示されず、ツイッターにおける検索結果においてのみ表示されるものであって、本件各投稿記事が伝達される範囲は一定程度限られたものであることを考慮したとしても、本件逮捕に関する事実を公表されない原告の法的利益は、本件各投稿記事により本件逮捕に関する事実の公表を継続する法的利益ないし必要性に優越するものと認められるとして、原告の請求を認容した事例。