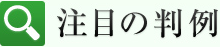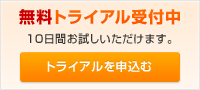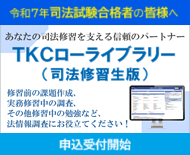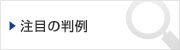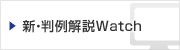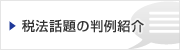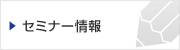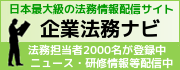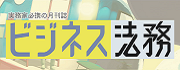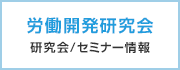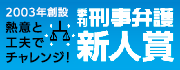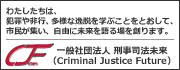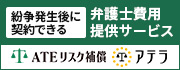2020.07.07
国民健康保険税処分取消請求事件
LEX/DB25570920/最高裁判所第二小法廷 令和 2年 6月26日 判決 (上告審)/令和1年(行ヒ)第252号
加須市長が、国民健康保険税及びその延滞金の滞納処分として、上告人の預金払戻請求権を差し押さえ(本件差押処分)、取り立てた金銭を上記国民健康保険税等に係る債権に配当する旨の処分(本件配当処分)をしたことについて、上告人が、上記債権は時効消滅していたなどと主張して、被上告人を相手に、本件配当処分の一部(上告人が延滞金として納付義務を認めている額を超える部分)等の取消しを求めるとともに、当該部分に相当する額の金員の支払を求めた上告審において、被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき、納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知は、これに係る地方税の徴収権について、地方税法18条の2第1項1号に基づく消滅時効の中断の効力を有しないとし、上告人による配当処分の取消請求を棄却し、金員の支払請求に係る訴えを却下した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中、配当処分の取消請求及び金員の支払請求に関する部分を破棄し、被上告人の控訴を棄却し、上記部分の上告人の各請求については認容し、上告人のその余の請求に関する上告を棄却した事例。