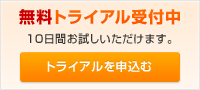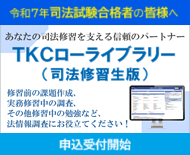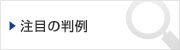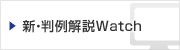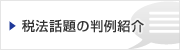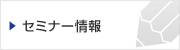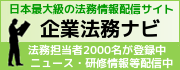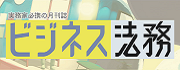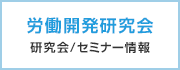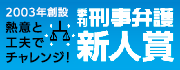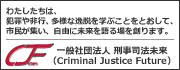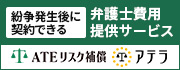2025.12.16
保険金請求事件
LEX/DB25623563/最高裁判所第一小法廷 令和 7年10月30日 判決(上告審)/令和6年(受)第120号
Aが車両を運転中に自損事故を起こして死亡したことについて、Aの相続人であるBが、当該車両に係る自動車保険契約の保険者である上告人・保険会社に対し、当該保険契約に適用される普通保険約款中の人身傷害条項に基づくAの人身傷害保険金の請求権を相続により取得したと主張して、人身傷害保険金の支払を求め、Bが第一審係属中に死亡し、被上告人らが相続により本件訴訟を承継した事件において、第一審が請求を一部認容したことから、上告人が控訴し、控訴審が控訴を棄却し、認容額を減額更正したところ、上告人が上告した事案で、死亡保険金の請求権は、被保険者の相続財産に属するものと解するのが相当であるとし、また、死亡保険金の額は、人身傷害保険金を支払うべき被保険者の精神的損害の額が本件精神的損害額の全額であることを前提として算定されるべきであって、被保険者の死亡により精神的損害を受けた被保険者の近親者が存在することは死亡保険金の額に影響を及ぼすものではないと解するのが相当であるから、所論の点に関する原審の判断は結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。
2025.11.11
損害賠償請求事件
LEX/DB25623181/福島地方裁判所いわき支部 令和 7年 3月 5日 判決(第一審)/令和4年(ワ)第131号
原告が、平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故により、原告が所有していた各土地がいずれも使用不能となり、所有権が侵害されたと主張して、本件原発を設置・運営していた被告会社に対し、原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき、本件各土地の価格相当額の損害賠償金等の支払を求めた事案で、本件事故により本件各土地の所在地は帰還困難区域に指定され、現在全く使用できず、無価値なものとなったというべきであるから、原告の損害については、本件各土地の本件事故当時の評価額を求めたうえで算定すべきであるところ、被告は、直接請求手続及びADR手続を通じて、原告に対し、本件各土地の財物賠償としての賠償金を支払っており、上記既払金を控除した後の残額である金額が原告の損害であると認められるから、原告の請求は前記の限度で理由があるとして、請求を一部認容した事例。
2025.08.19
損害賠償、求償金請求事件
LEX/DB25574415/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 7月 4日 判決(上告審)/令和5年(受)第1838号
上告人が、普通乗用自動車で走行中に進入しようとした駐車場の設置又は保存の瑕疵により傷害を負ったと主張して、被上告人に対し、不法行為(工作物責任)に基づく損害賠償を求め、上告人は、上記自動車の登録使用者が自動車保険契約を締結していた保険会社から、上記保険契約に適用される普通保険約款中の人身傷害条項に基づき、人身傷害保険金の支払を受けたことから、上記保険会社が上告人の被上告人に対する損害賠償請求権を代位取得する範囲、すなわち、裁判所が、被上告人の上告人に対する損害賠償の額を定めるにあたり民法722条2項の規定を類推適用して上記の事故前から上告人に生じていた身体の疾患をしんしゃくし、その額を減額する場合に、支払を受けた人身傷害保険金の額のうち上記損害賠償請求権の額から控除することができる額の範囲が争われた事案の上告審で、上記疾患が本件限定支払条項にいう既存の身体の障害又は疾病に当たるときは、被害者に対して人身傷害保険金を支払った訴外保険会社は、支払った人身傷害保険金の額と上記の減額をした後の損害額のうちいずれか少ない額を限度として被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すると解するのが相当であり、このことは、訴外保険会社が人身傷害保険金の支払に際し、本件限定支払条項に基づく減額をしたか否かによって左右されるものではないとしたうえで、上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができ、論旨は採用することができず、なお、その余の上告受理申立て理由は、上告受理の決定において排除されたとして、本件上告を棄却した事例(補足意見1名)。
2025.08.12
不当利得返還等請求事件
LEX/DB25574403/最高裁判所第一小法廷 令和 7年 6月30日 判決(上告審)/令和6年(受)第1067号
別荘地の管理を行っている被上告人が、同別荘地内に存在する土地を所有していた訴外E及び訴外Eから本件の土地の所有権を相続により取得した上告人Bは、被上告人による本件の土地を含む別荘地の管理により、法律上の原因なく本件の土地の管理に係る管理費相当額の利得を得た一方、原告はこれにより同額の損失を被ったと主張し、上告人らに対し、不当利得に基づき利得金相当額の支払などを求め、第一審がいずれの請求も棄却したことから、被上告人が控訴し、控訴審が被上告人の請求を認容したところ、上告人らが上告した事案で、亡Aらは、本件管理契約を締結することなく被上告人の本件管理業務という労務により法律上の原因なく利益を受け、そのために被上告人に損失を及ぼしたものと認められ、このことは、本件管理業務が本件土地の経済的価値それ自体を維持又は向上させるものではなかったとしても変わるものではなく、また、亡Aらが被上告人による本件管理業務の提供を望んでいなかったとしても、本件管理業務に対する管理費として相当と認められる額の負担を免れることはできないというべきであり、このように解することが契約自由の原則に反するものでないことは明らかであるから、亡Aらは、被上告人に対し、本件管理業務に対する管理費として相当と認められる額の不当利得返還義務を負うものであり、控訴審の判断は是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。
2025.08.12
不当利得返還等請求事件
LEX/DB25574404/最高裁判所第一小法廷 令和 7年 6月30日 判決(上告審)/令和5年(受)第2461号
上告人(被控訴人・原告)が、被上告人(控訴人・被告)に対し、本件管理業務という労務により被上告人は法律上の原因なく利益を受け、上告人は損失を被ったとして、不当利得返還請求権に基づき、平成28年7月から令和3年6月までの間における管理費と同額の支払を求め、第一審が請求を一部認容したところ、被上告人らが控訴し、控訴審が、上記事実関係の下において、本件管理業務が本件土地の経済的価値に与えた影響は不明であるから、被上告人が利益を受けたとは認められず、被上告人は上告人に対し不当利得返還義務を負わないと判断して、上告人の請求を棄却したところ、上告人が上告した事案で、上告人の本件管理業務という労務は、本件別荘地内の土地に建物を建築してその土地を利用しているか否かにかかわらず、本件別荘地所有者に利益を生じさせるものであるというべきであり、そして、本件管理業務に要する費用は、本件別荘地所有者から本件管理業務に対する管理費を収受することによって賄うことが予定されているといえるから、被上告人からその支払を受けていない上告人には損失があるというべきであるとし、また、被上告人が上告人による本件管理業務の提供を望んでいなかったとしても、本件管理業務に対する管理費として相当と認められる額の負担を免れることはできないというべきであって、このように解することが契約自由の原則に反するものでないことは明らかであるから、被上告人は、上告人に対し、本件管理業務に対する管理費として相当と認められる額の不当利得返還義務を負い、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却した事例。
2025.05.13
損害賠償請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」民法(財産法)分野 令和7年5月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574036/大阪高等裁判所 令和 7年 1月20日 判決(控訴審)/令和5年(ネ)第619号
被控訴人(被告)会社の従業員である被控訴人(被告)Eが被控訴人会社の業務の執行中に運転していた小型特殊自動車が、歩行中の被害者(先天性の聴覚障害を有していた児童)に衝突し、被害者が死亡した交通事故につき、被害者の父母である控訴人(原告)らが、被控訴人Eに対しては民法709条に基づき、被控訴人会社に対しては同法715条に基づき、損害賠償を求め、原審は請求を一部認容し、控訴人らが、逸失利益等に係る判断を不服として控訴を提起した事案において、被害者児童の労働能力は、一般に未成年者の逸失利益を認定するための基礎収入とされる労働者平均賃金を、当然に減額するべき程度の制限があったとはいえない状態であったと評価するのが相当であると判断し、原判決を変更した事例。
2025.05.13
消費者契約法による差止請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」民法(財産法)分野 令和7年7月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574030/大阪高等裁判所 令和 6年12月19日 判決(控訴審)/令和5年(ネ)第1812号
適格消費者団体である控訴人(原告)が、テーマパークを運営する被控訴人(被告)に対し、被控訴人が消費者との間でインターネットを経由してチケットの購入契約を締結する際に適用される利用規約(WEBチケットストア利用規約)中にある、一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項が、消費者の利益を一方的に害する条項に該当するなど消費者契約法10条及び同法9条1項1号の条項に当たると主張するとともに、同利用規約中にある、チケットの転売を禁止する旨の条項が、同じく同法10条の条項に当たると主張し、同法12条3項に基づく差止請求として、同各条項を内容とする意思表示の停止、同各条項が記載された上記利用規約が印刷された規約用紙等の破棄及び上記の意思表示の停止等のための被控訴人の従業員らに対する書面の配布を求め、原審が控訴人の請求を全部棄却したので、これを不服とする控訴人が控訴した事案において、控訴人の当審における訴えの変更(追加請求)は許さないこととし、控訴人のその余の請求は、いずれも理由がなく、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例。
2024.10.08
損害賠償等請求控訴事件
LEX/DB25620664/東京高等裁判所 令和 6年 4月11日 判決 (控訴審)/令和5年(ネ)第5588号
Z社(破産会社)が被控訴人らを含むファクタリング会社に対して売掛金債権を譲渡したところ、債務者らが供託したことから、破産会社の破産管財人である控訴人(原告)が、被控訴人らに対し、被控訴人(被告)らが既に還付を受けた分については、不法行為又は不当利得に基づき、その取得額及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、還付未了の供託金については、控訴人が還付金請求権を有することの確認を求め、原審が控訴人の請求をいずれも棄却したことから、控訴人が控訴した事案で、破産会社が被控訴人らに譲渡した本件債権にはいずれも基本契約において譲渡禁止特約が付されていたところ、被控訴人らは自らのファクタリング会社としての知識や経験を踏まえ、本件債権について譲渡禁止特約が付されている可能性が高いことを認識していたのであるから、破産会社に対して譲渡禁止特約の有無を確認してしかるべきであり、そうすれば、譲渡禁止特約の存在が明らかとなったにもかかわらず、被控訴人らは、こうした極めて容易な確認作業を行うことなく、漫然と破産会社から本件債権の譲渡を受けたものであり、譲渡禁止特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失があったというべきであるし、供託金の還付を受けたことについて少なくとも過失があったと認められるから、不法行為に基づき、控訴人が受けた損害について賠償義務を負うというべきであるところ、控訴人の請求を棄却した原判決は失当であるとして、原判決を取り消したうえ、控訴人の請求をいずれも認容した事例。
2024.08.13
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25620053/名古屋高等裁判所 令和 6年 4月18日 判決 (控訴審)/令和5年(ネ)第426号
出生後間もなく喉頭軟化症と診断され、気管切開術を受けて人工呼吸器管理となっていたP1の相続人である控訴人(原告)らが、〔1〕P1の入院していた被控訴人病院の医師において、P1が退院して自宅療養させるに際しての療養指導義務を怠り、また、〔2〕P1の訪問看護を担っていた原審相被告T社において、P1が気管に装着していた気管切開カニューレと人工呼吸器回路との接続方法を誤って勧めたために、P1の装着していたカニューレに事故が起こって呼吸不能又は呼吸困難な状態となり、さらに、〔3〕臨場した消防署所属の救急隊員や搬送先である被控訴人(被告)病院の医師において、直ちにカニューレを引き抜くなどして気道を確保しなかったために、P1が心肺停止状態となり、その後P1が死亡するに至ったなどと主張して、T社に対しては、不法行為又は債務不履行に基づいて、入院先及び搬送先の病院である被控訴人病院を開設し、かつ、臨場した救急隊員が所属する消防署を開設する被控訴人・一宮市に対しては、医師の各注意義務違反につき不法行為又は債務不履行に基づき、救急隊員の注意義務違反につき国家賠償法1条1項に基づいて、P1に生じた損害の相続分及び自らの固有の損害に当たる損害賠償金等の連帯支払を求め、原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したことから、控訴人らが被控訴人に対して控訴した事案で、被控訴人病院医師としては、退院後もP1に多様な原因・態様によるカニューレ事故が発生し得る蓋然性が高いことを当然に予見できたものと認められ、控訴人らに対して、想定される多様な事態に即した指導をする医師としての注意義務があったところ、P8医師が行った説明指導等は、到底本件療養指導義務を履行したといえるものではないから、前記療養指導義務を怠った過失があるものといわざるを得ないうえ、療養指導義務を果たしていれば、上記のような事態は生じなかったものと認められ、被控訴人病院医師の過失とP1の死亡との間には相当因果関係があるといえるところ、控訴人らの請求は一部について理由があり、それと異なる原判決中、被控訴人に関する部分は相当でないとして、原判決を変更した事例。
2024.06.18
損害賠償請求事件
LEX/DB25599625/函館地方裁判所 令和 6年 5月 8日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第175号
原告P1が、被告八雲町が運営する病院の産婦人科で被告P3ら医師から処方を受けていた経口避妊薬であるアンジュ28錠の服用により脳静脈洞血栓症を発症し、重度の身体障害等を負ったとして、(1)原告P1が、主位的に、被告P3に対しては不法行為に基づき、被告八雲町に対しては使用者責任に基づき、連帯して金員の支払を求めるとともに、予備的に、被告八雲町に対し、債務不履行に基づき、上記と同額の損害賠償金等の支払を求め(原告P1の主位的請求及び予備的請求1)、(2)原告P1が、更に予備的に、被告P3には、本件薬剤を投与する前に原告P1の血圧を測定しなかった過失があり、これにより、原告P1への投与は本件薬剤が適正に使用された場合に当たらないとされ、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)から副作用救済給付を受けられなかった旨主張し、被告らに対し、不法行為に基づき、連帯して、損害賠償金等の支払を求め(原告P1の予備的請求2)、(3)原告P1の夫である原告P2が、原告P1に対する被告P3の前記の不法行為によって自身も精神的苦痛を被った旨主張し、被告P3に対しては不法行為に基づき、被告八雲町に対しては使用者責任に基づき、損害賠償金等の支払を求めた(原告P2の請求)事案で、本件処方には、添付文書上要求される血圧測定等を行わずに漫然と本件薬剤を処方した注意義務違反が認められ、原告P1と被告八雲町との間の診療契約に基づいて行われたものであるから、説明義務違反の有無等について判断するまでもなく、被告八雲町には債務不履行に基づく損害賠償責任が認められるとして、原告らの請求を一部認容した事例。
2024.06.04
虐待認定違法確認等請求控訴事件
LEX/DB25599317/東京高等裁判所 令和 6年 4月18日 判決 (控訴審)/令和5年(行コ)第255号
障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)を行う事業所を運営する控訴人(原告)が、被控訴人(被告)・大田区から、同事業所に通所していた児童に対する控訴人代表者の行為が心理的虐待及びネグレクトに該当する旨の認定(本件虐待認定等)、並びに、上記控訴人代表者の行為に関する改善案等の提出による報告の求め(本件報告の求め)を受けたことにつき、本件虐待認定等は前提とする事実を誤り、その評価も不合理なものであって違法であり、また、本件虐待認定等が適法であることを前提とする本件報告の求めに従う義務もないなどとして、本件虐待認定等が違法であることの確認を求める(本件各違法確認請求)とともに、本件報告の求めに応じる義務がないことの確認を求め(本件義務不存在確認請求)、併せて、被控訴人から本件虐待認定等及び本件報告の求めを受けたことにより控訴人の事業に多大な損害が生じたなどとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金等の支払を求め、原審が本件訴えのうち、本件各確認請求に係る部分をいずれも却下し、控訴人のその余の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴した事案で、本件各違法確認請求が控訴人の有する権利又は法律的地位に存する危険又は不安を除去するために必要かつ適切であるということはできず、同請求に係る訴えには確認の利益がないとし、被控訴人の担当職員らによる本件虐待認定、及び、本件ネグレクト認定が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとして、原判決は結論において相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。
2024.05.28
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25599174/東京高等裁判所 令和 6年 1月17日 判決 (控訴審)/令和5年(ネ)第3826号
控訴人(原告)は、かつて、「金融商品取引法」に改題される前の旧証券取引法違反の罪により逮捕及び起訴され、有罪判決を受けて服役したことがある者であるが、被控訴人(被告)会社がそのウェブページに控訴人の実名と共に上記前科等の事実を摘示したことは、控訴人の名誉を毀損し、プライバシーを侵害するものであるとして、控訴人が、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償金等の支払を求め、原審が控訴人の請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案で、本件記述は、控訴人が当該報道をされるような人物であるとの印象を閲覧者に与える面があること自体は否定できず、その意味において、控訴人の社会的評価を低下させる要素を含むものといわざるを得ないが、被控訴人の行為は、被控訴人の株主等に対して投資判断の材料となる情報を迅速かつ的確に提供することを目的としていたものと認められ、閲覧者が本件記述の意味内容、性格等について誤解を生ずる余地はないから、控訴人の社会的評価を違法に低下させる行為には当たらないと解するのが相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。
2024.04.02
共通義務確認請求事件
LEX/DB25573400/最高裁判所第三小法廷 令和 6年 3月12日 判決 (上告審)/令和4年(受)第1041号
特定適格消費者団体である上告人が、被上告人らが本件対象消費者に対して虚偽又は実際とは著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明をして商品を販売するなどしたことが不法行為に該当すると主張して、被上告人らに対し、平成29年法律第45号による改正前の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律3条1項5号又は同改正後の同項4号に基づき、被上告人らが本件対象消費者に対して上記商品の売買代金相当額等の損害賠償義務を負うべきことの確認を求め、同法2条4号所定の共通義務確認の訴えをしたところ、原審は、本件訴えを却下したため、上告人が上告した事案で、過失相殺及び因果関係に関する審理判断を理由として、本件について、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断には、同項の解釈適用を誤った違法があり、他に予想される当事者の主張等を考慮し、個々の消費者の対象債権の存否及び内容に関して審理判断をすることが予想される争点の多寡及び内容等に照らしても、本件対象消費者ごとに相当程度の審理を要するとはいえないとして、原判決を破棄し、第1審判決を取消し、更に審理を尽くさせるため、本件を第1審に差し戻した事例(補足意見がある)。
2024.04.02
損害賠償請求事件
LEX/DB25597024/神戸地方裁判所 令和 5年12月14日 判決 (第一審)/令和3年(ワ)第1804号
原告は、被告・兵庫県が設置運営する病院の整形外科において、同病院のd医師により診療を受けた者であるが、原告が、上記診療のために実施されたミエログラフィー(脊髄造影検査)により、原告に脊髄損傷に伴う左下肢麻痺等の障害が残存した事故に関して、d医師には、〔1〕本件ミエログラフィーの際に、脊髄損傷の高度の危険性がある第1腰椎第2腰椎間レベル(L1/2)の穿刺を行った過失がある、〔2〕脊髄損傷の高度の危険性があることについて説明することなく、L1/2の穿刺を行ったことにつき、説明義務違反があるなどと主張して、使用者責任又は診療契約の債務不履行に基づき、損害賠償金等の支払を求めた事案で、d医師は、L1/2の穿刺にあたって、本件ミエログラフィーの必要性と、L1/2の穿刺による危険性との衡量や代替手段の有無等について、熟慮することなく、その必要性についての判断を誤ったものであり、その判断に過失があったといえるうえ、当初予定していなかったL1/2に穿刺する前に、その方法による脊髄損傷のリスクなどに関する具体的な説明を何らしていないのであるから、説明義務を尽くしたということはできないところ、原告の請求は、本件事故と相当因果関係のある損害賠償を求める限度で理由があるとして、請求を一部認容した事例。
2023.12.26
取立金請求事件
LEX/DB25573172/最高裁判所第二小法廷 令和 5年11月27日 判決 (上告審)/令和3年(受)第1620号
建物の根抵当権者であり、物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえた上告人が、賃借人である被上告人に対し、当該賃料債権のうち2790万円の支払を求める取立訴訟で、原審は、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案において、被上告人は、物上代位権を行使して本件将来賃料債権を差し押さえた根抵当権者である上告人に対し、本件相殺合意の効力を対抗することはできないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決を破棄し、本件将来賃料債権(2790万円)の支払を求める上告人の請求は理由があるから、これを棄却した第1審判決を取消し、請求を認容した事例(補足意見及び意見がある)。
2023.11.21
損害賠償請求事件
LEX/DB25573116/最高裁判所第一小法廷 令和 5年10月23日 判決 (上告審)/令和3年(受)第2001号
M社からマンションの建築工事を請け負った被上告人が、上告人会社においてM社から上記マンションの敷地を譲り受けた行為が被上告人のM社に対する請負代金債権及び上記マンションの所有権を違法に侵害する行為に当たると主張して、上告人会社に対しては、不法行為に基づき、その代表取締役である上告人Y1に対しては、主位的に不法行為、予備的に会社法429条1項に基づき、被上告人の損害の一部である1億円及び遅延損害金の連帯支払を求め、原審は、被上告人の上告人らに対する不法行為に基づく損害賠償請求を認容すべきものとしたため、上告人らが上告した事案で、マンションの建築工事の注文者から上記マンションの敷地を譲り受けた行為は、自ら上記マンションを分譲販売する方法によって請負代金債権を回収するという請負人の利益を侵害するものとして本件債権を違法に侵害する行為に当たらないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、本件行為は、被上告人の権利又は法律上保護される利益を侵害するものではなく、被上告人の上告人らに対する請求は、いずれも理由がないことが明らかであるから、第1審判決中上告人らに関する部分を取り消し、被上告人の上告人らに対する請求をいずれも棄却した事例(反対意見がある)。
2023.10.31
損害賠償請求事件
LEX/DB25573103/最高裁判所第一小法廷 令和 5年10月16日 判決 (上告審)/令和4年(受)第648号
交通事故によって死亡したAの配偶者又は子である上告人らが、加害車両の運転者である被上告人らに対し、民法709条、719条等に基づき、損害賠償を求め、原審は、上告人X1の民法709条、719条に基づく請求を357万9854円及び遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容すべきものとし、上告人子らの各請求をそれぞれ105万0761円及び遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容したため、上告人らが上告した事案で、人身傷害保険の保険会社(参加人)が上告人らに対して人身傷害保険金額に相当する額を支払った場合において、上告人らの被上告人に対する損害賠償請求権の額から上記の支払額を全額控除することはできないとして、原判決を一部変更し、その余の上告人らの請求を棄却した事例。
2023.10.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25595973/那覇地方裁判所 令和 5年 8月23日 判決 (第一審)/令和4年(ワ)第899号
企業向けの衣類クリーニング業を営む原告が、被告会社から購入した本件システムの使用中に事故が発生して損害を被ったなどと主張して、被告会社に対し、製造物責任又は債務不履行責任に基づく損害賠償請求として(選択的請求)、被告会社の取締役であるその余の被告らに対し、会社法429条1項に基づく損害賠償請求として、連帯して、賠償金等の支払を求めた事案において、原告は、各被告に対して、それぞれ請求する損害額全額を請求することができ、このうち被告B、被告C及び被告Dが負う各債務は連帯債務となり(会社法430条)、もっとも、被告Bら3名の責任は、特別の法定責任と解するのが相当であって、被告会社の責任について、不法行為責任の特則と解される製造物責任法3条に基づく製造物責任を選択しても、債務不履行責任を選択しても、被告会社と被告Bら3名が不真正連帯債務を負うことにはならないとした事例。
2023.09.05
国家賠償請求控訴事件
LEX/DB25595642/札幌高等裁判所 令和 5年 6月22日 判決 (控訴審)/令和4年(ネ)第202号
被控訴人らが、札幌市内で実施された第25回参議院議員通常選挙の候補者のための街頭応援演説に対し、路上等から「P1辞めろ」、「増税反対」などと声を上げたところ、北海道警察の警察官らに肩や腕などをつかまれて移動させられ、あるいは長時間にわたって付きまとわれるなどしたと主張して、北海道警察を設置する地方公共団体である控訴人に対し、それぞれ国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金330万円等の支払を求め、原審は、警察官らが被控訴人らに対して違法な有形力の行使等を行ったものと認め、警察官らによるこれらの違法行為によって、被控訴人らの表現の自由のほか、被控訴人2の移動・行動の自由、名誉権及びプライバシー権が侵害されたとして、被控訴人らの請求のうち、被控訴人1につき33万円、被控訴人2につき55万円の各損害賠償金等の支払を求める限度で認容し、その余の請求はいずれも理由がないとして棄却したため、控訴人が控訴した事案において、被控訴人1の控訴人に対する請求は理由がなく棄却すべきであるから、被控訴人1の請求を一部認容した原判決は一部失当であり、控訴人の被控訴人1に対する控訴は理由があるから、原判決主文第1項を取消し、同部分につき被控訴人1の請求を棄却することとし、被控訴人2の控訴人に対する請求を一部認容した原判決は相当であり、控訴人の被控訴人2に対する控訴を棄却した事例。
2023.08.15
損害賠償請求事件(那須雪崩事故遺族側勝訴判決)
LEX/DB25595542/宇都宮地方裁判所 令和 5年 6月28日 判決 (第一審)/令和4年(ワ)第83号
被告高体連主催の平成28年度春山安全登山講習会において、平成29年3月27日雪崩が発生し、県立高等学校の部活動の一環として参加していた生徒及び教師が死亡した雪崩事故について、被告県の公務員であり、かつ、本件講習会の講師であった被告P1、被告P2及び被告P3並びに被告高体連が、雪崩の発生を予見し、本件講習会を中止すべき義務があったのにこれを怠ったことによって生じたものであるとして、本件被災者らの遺族である原告らが、被告三講師及び被告高体連に対しては民法709条に基づき、被告県に対しては国家賠償法1条1項に基づき、各損害賠償金等の連帯支払を求めた事案で、被告県及び被告高体連に対する請求について、本件事故により各原告らに対し、別紙認容額一覧表の記載額の範囲内で賠償責任を負うとして認容し、原告らの被告県及び被告高体連に対するその余の請求並びに被告三講師に対する請求については、いずれも棄却した事例。