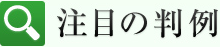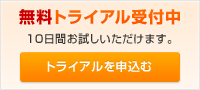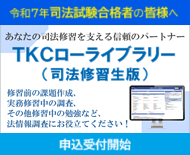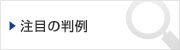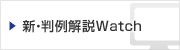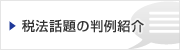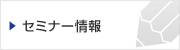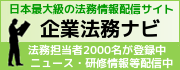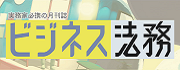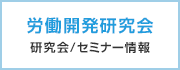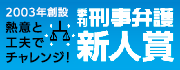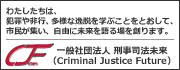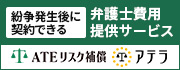2026.02.10
建物明渡等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 

LEX/DB25574725/最高裁判所第二小法廷 令和 8年 1月 9日 判決(上告審)/令和6年(受)第1046号
本件本訴は、国が所有する国家公務員宿舎の居室について、国から使用許可を受けた被上告人・福島県が、各居室をそれぞれ占有し、または占有していた上告人らに対し、上告人P3に対しては、国の上告人らに対する所有権に基づく明渡請求権を代位行使すると主張して居室の明渡しを求め、上告人らに対し、上告人らの各占有により被上告人の使用収益権が侵害されたとして、不法行為に基づき賃料相当損害金の各支払を求め、本件反訴は、上告人らが、被上告人知事の政策判断や被上告人職員らの嫌がらせ等により精神的苦痛を受けたと主張して、国家賠償請求権に基づき慰謝料の一部等の支払を求めたところ、第一審が、上告人らは本件各建物につき占有権原を有せず、また、被上告人が国の明渡請求権を代位行使することが違法であるとはいえないとして、被上告人の本訴請求をいずれも認容する一方、上告人らの反訴請求をいずれも理由がないとして棄却したため、上告人らが控訴し、反訴請求における遅延損害金の請求をそれぞれ本訴請求の提起日から年3分の割合として、請求の拡張をし、控訴審が、原判決は相当であるなどとして、本件控訴をいずれも棄却し、当審における拡張請求をいずれも棄却したことから、上告人らが上告した事案で、被上告人が上記建物明渡請求権の代位行使をすることができるとした原審の判断は、結論において是認することができ、原判決に所論の違法はなく、また、所論は、本件判断は裁量権の範囲を逸脱する違法なものであって、上告人は本件建物について占有権原を有するにもかかわらず、これを否定した原審の判断には、法令の解釈適用の誤りがあるというものであるが、しかし、本件判断が違法なものであるか否かは、上告人の占有権原の有無に影響を及ぼすものではなく、前記事実関係の下において、上告人が本件建物について占有権原を有するとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(共同意見、意見、反対意見あり)。