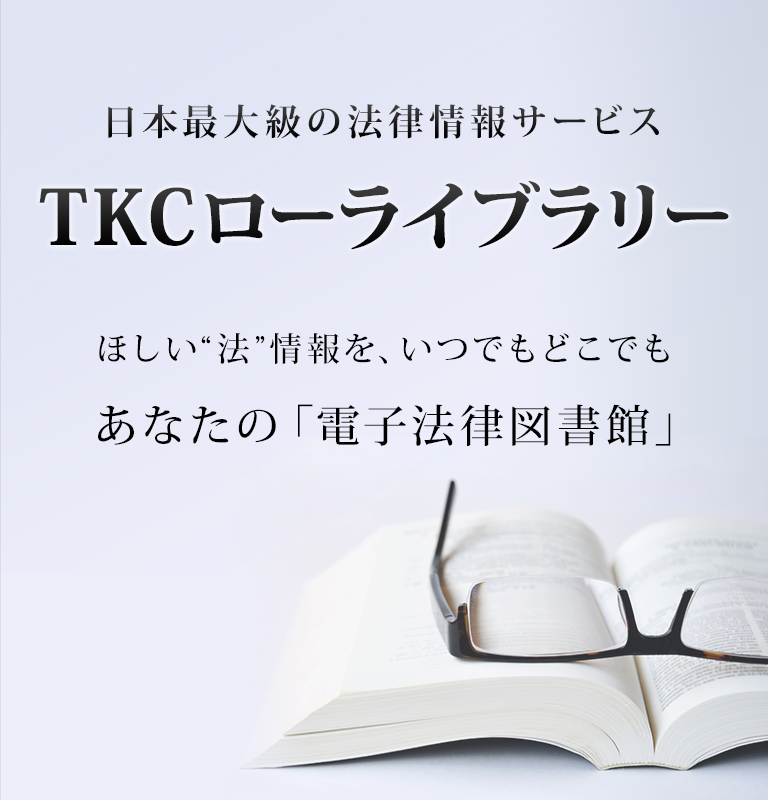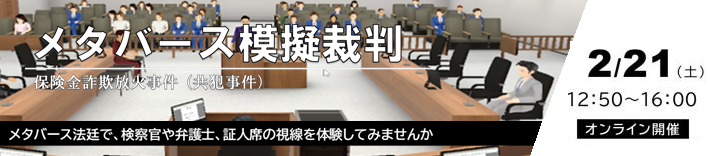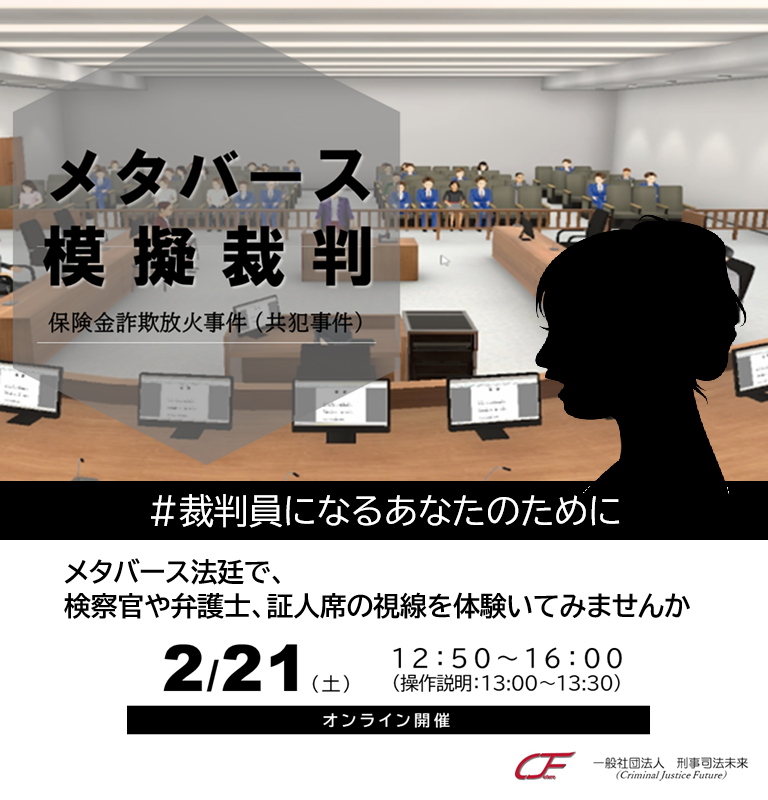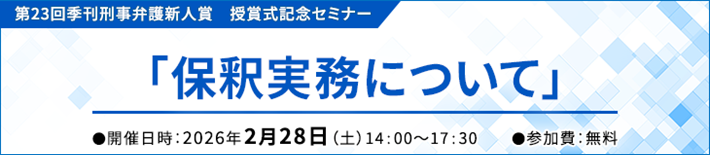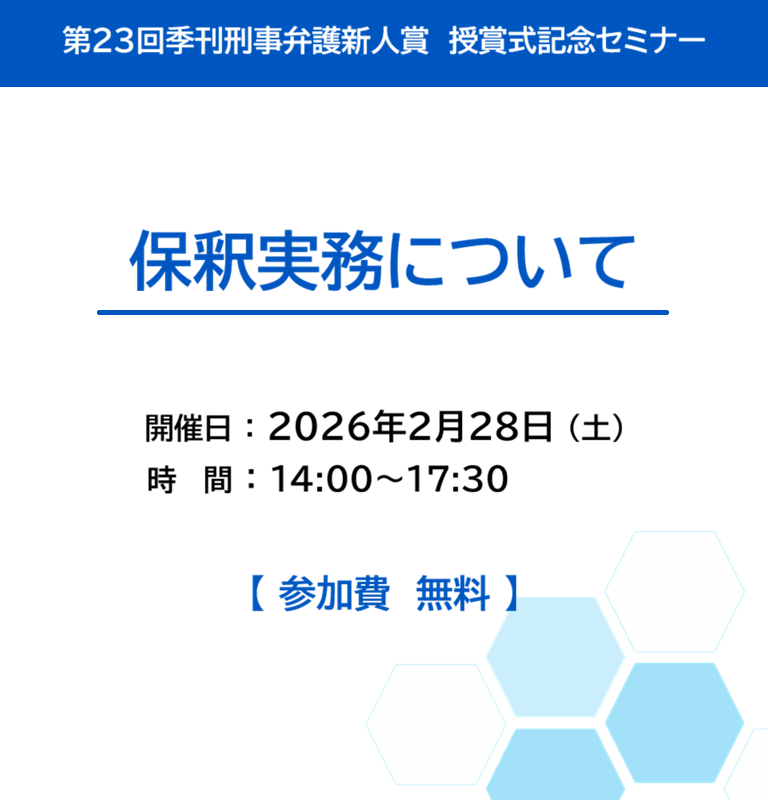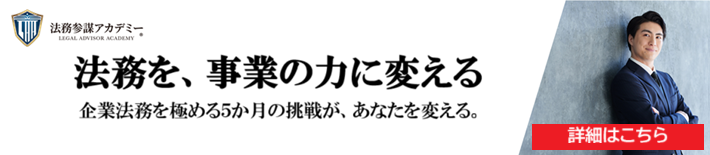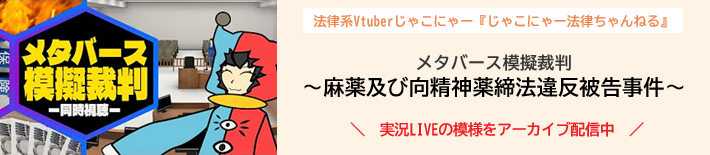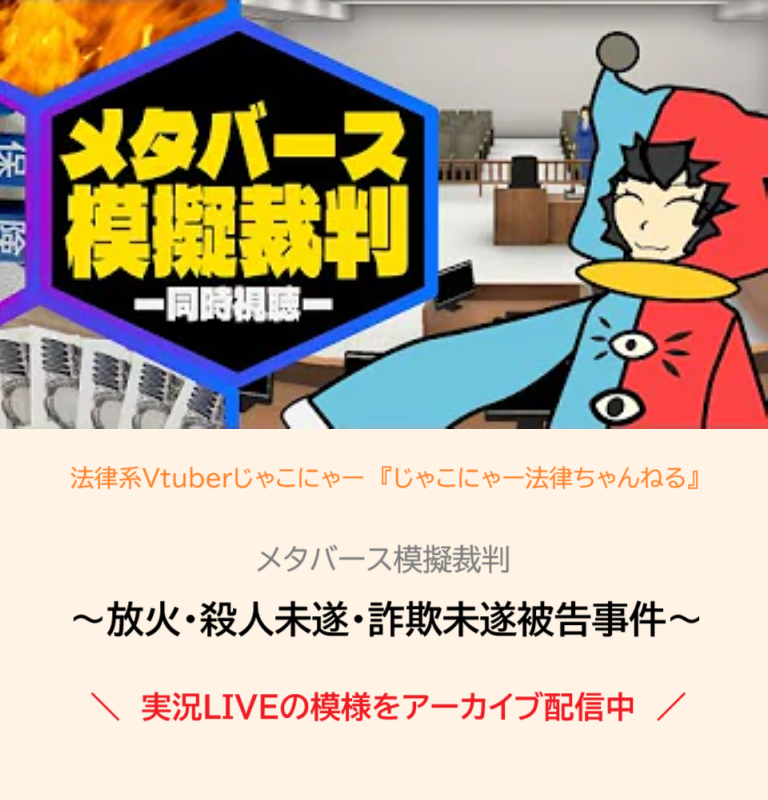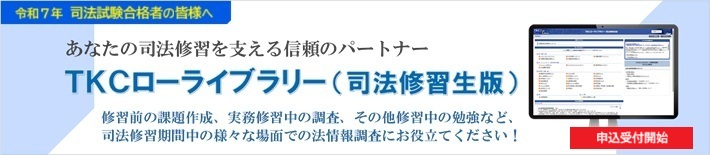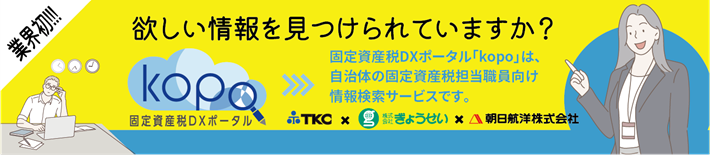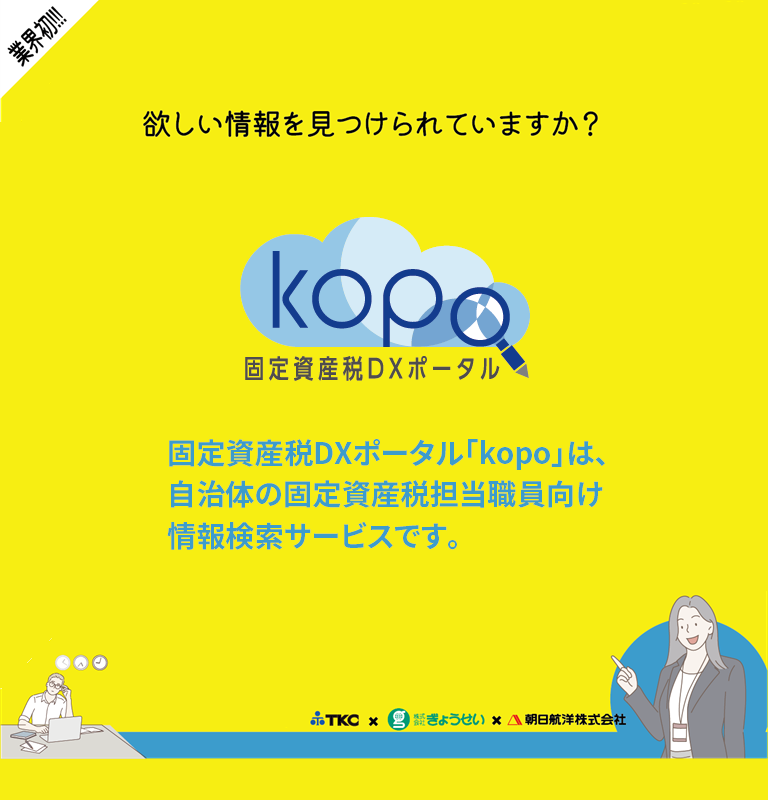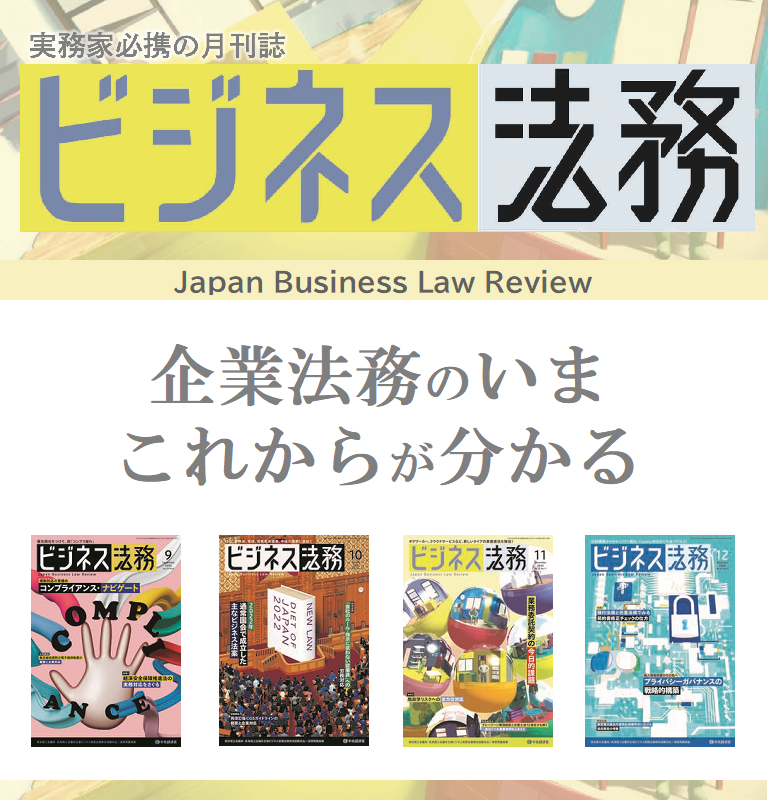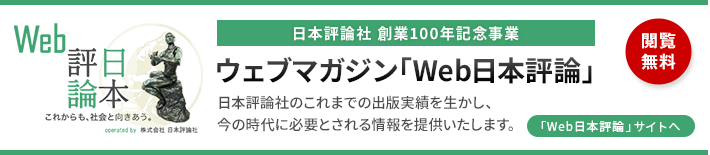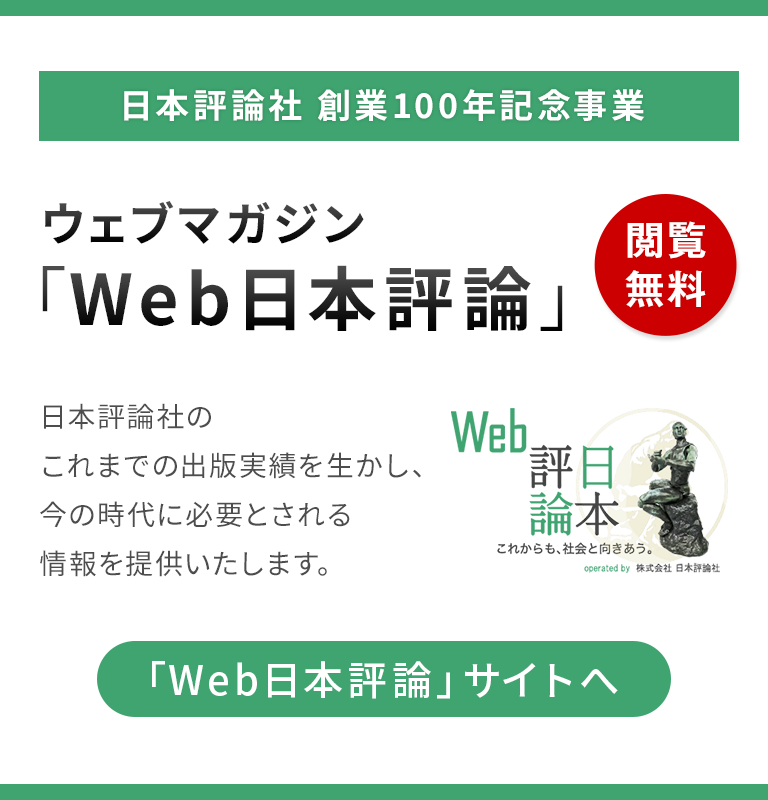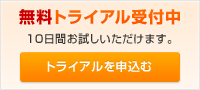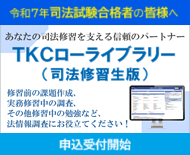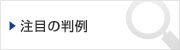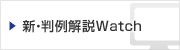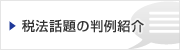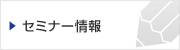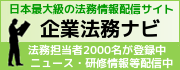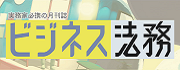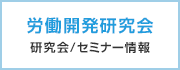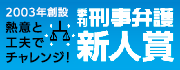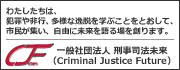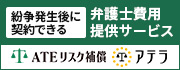2026.02.17
第三者異議事件

LEX/DB25574744/最高裁判所第三小法廷 令和 8年 1月20日 判決(上告審)/令和5年(受)第2245号
被上告人は弁護士であり、その職務に関して預かり保管する金員を管理するため、みずほ銀行において普通預金口座を開設していたが、上告人は、被上告人に対して婚姻費用の分担金の支払を命ずる審判を債務名義とする強制執行として、被上告人がみずほ銀行に対して有する預金債権の差押えを2回にわたって申し立て、上記各申立てに基づき債権差押命令が発せられ、本件預り金口座に係る預金債権のうち、「被差押金額」の部分が差し押さえられたところ、被上告人が、依頼者からの預り金は、当然に信託財産に属する財産となるから、被上告人を受託者とし、本件預り金を信託財産に属すべきものと定めた信託契約が成立し、本件預り金を原資とする本件預金債権も信託財産に属する財産となるとして、上告人に対し、信託法23条5項の規定による異議に係る訴えを提起し、本件各差押部分に対する前記各強制執行の不許を求め、控訴審が被上告人の請求をいずれも認容すべきものとしたことから、上告人が上告した事案で、当審において、預り金について信託と明示されていたか否か、被上告人が本件預り金を預かり保管した目的、成立するとされる本件信託契約における受益権及び信託事務処理の内容のいずれもが明確にされておらず、そればかりか、依頼者が預り金であると認識して被上告人に金員を預託したのかすら明らかではなく、現在の主張の内容にとどまる限り、信託の目的についての合意はもとより、実効確保の仕組みについての合意があったともいえず、信託契約が成立したとはいえないとして、原判決を破棄し、本件を高等裁判所に差し戻した事例(補足意見、意見あり)。
2026.02.17
地位確認等請求控訴・同附帯控訴事件
 ★
★「新・判例解説Watch」労働法分野 令和8年4月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
★LEX/DB25625083/大阪高等裁判所 令和 7年10月14日 判決(控訴審)/令和7年(ネ)第606号 他
被控訴人(原告)は、平成22年4月1日から令和4年3月31日まで控訴人(被告)・学校法人が運営するC高等学校(本件高校)の常勤講師(教育職員)として控訴人に雇用されていたが、同年4月1日付けで常勤嘱託(事務職員)への配置転換命令を受けたところ、被控訴人が、控訴人に対し、〔1〕被控訴人と控訴人との間には被控訴人の職種及び業務内容を教育職員に限定する合意(本件職種限定合意)が成立しており、被控訴人を事務職員に配置転換することはできないなどと主張して、常勤講師としての労働契約上の権利を有する地位の確認を求め(主位的請求)、〔2〕仮に本件職種限定合意が成立していないとしても、被控訴人を常勤嘱託に配置転換したことは配転命令権の濫用であるなどと主張して、常勤嘱託として勤務する義務がないことの確認を求める(予備的請求)とともに、〔3〕期間の定めのない労働契約を締結している労働者(無期労働者)である専任教員と有期労働契約を締結している労働者(有期労働者)である常勤講師との間の賃金の差は、合理的な根拠のない差別であり、違法であるなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償請求として、損害賠償金並びに遅延損害金の支払を求め、原審が、被控訴人の請求〔1〕を却下し、請求〔2〕を棄却し、請求〔3〕を一部認容し、その余を棄却したところ、控訴人が控訴し、被控訴人が控訴及び附帯控訴した事案で、専任教員と常勤講師であった原告との賃金差は、不合理なものであるとはいえず、これが労働契約法20条や短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条にいう不合理なものに当たるとはいえないし、原告指摘のその他の法令に反するものともいえないから、原告に専任教員よりも低い賃金しか支給しなかった被告の対応が、原告に対する不法行為を構成するとはいえないとして、請求〔3〕に係る原判決を取り消したうえで、請求〔3〕を棄却し、被控訴人の控訴及び附帯控訴を棄却した事例。
2026.02.10
建物明渡等請求本訴、損害賠償請求反訴事件
LEX/DB25574725/最高裁判所第二小法廷 令和 8年 1月 9日 判決(上告審)/令和6年(受)第1046号
本件本訴は、国が所有する国家公務員宿舎の居室について、国から使用許可を受けた被上告人・福島県が、各居室をそれぞれ占有し、または占有していた上告人らに対し、上告人P3に対しては、国の上告人らに対する所有権に基づく明渡請求権を代位行使すると主張して居室の明渡しを求め、上告人らに対し、上告人らの各占有により被上告人の使用収益権が侵害されたとして、不法行為に基づき賃料相当損害金の各支払を求め、本件反訴は、上告人らが、被上告人知事の政策判断や被上告人職員らの嫌がらせ等により精神的苦痛を受けたと主張して、国家賠償請求権に基づき慰謝料の一部等の支払を求めたところ、第一審が、上告人らは本件各建物につき占有権原を有せず、また、被上告人が国の明渡請求権を代位行使することが違法であるとはいえないとして、被上告人の本訴請求をいずれも認容する一方、上告人らの反訴請求をいずれも理由がないとして棄却したため、上告人らが控訴し、反訴請求における遅延損害金の請求をそれぞれ本訴請求の提起日から年3分の割合として、請求の拡張をし、控訴審が、原判決は相当であるなどとして、本件控訴をいずれも棄却し、当審における拡張請求をいずれも棄却したことから、上告人らが上告した事案で、被上告人が上記建物明渡請求権の代位行使をすることができるとした原審の判断は、結論において是認することができ、原判決に所論の違法はなく、また、所論は、本件判断は裁量権の範囲を逸脱する違法なものであって、上告人は本件建物について占有権原を有するにもかかわらず、これを否定した原審の判断には、法令の解釈適用の誤りがあるというものであるが、しかし、本件判断が違法なものであるか否かは、上告人の占有権原の有無に影響を及ぼすものではなく、前記事実関係の下において、上告人が本件建物について占有権原を有するとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(共同意見、意見、反対意見あり)。