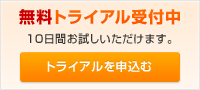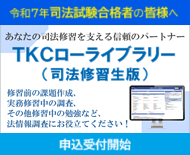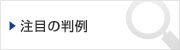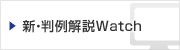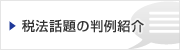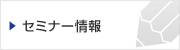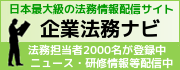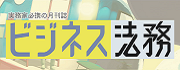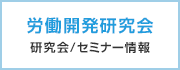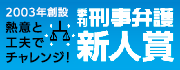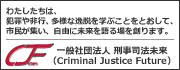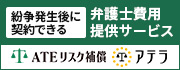2026.01.27
旅券不発給処分無効確認等請求事件
LEX/DB25574628/大阪地方裁判所 令和 7年 9月30日 判決(第一審)/令和4年(行ウ)第182号
日本国民である父の子として出生し、日本の国籍を取得し、その後カナダ市民権法5条1項に基づき、自らの申請によりカナダ市民権を取得した原告が、〔1〕主位的に、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失うとの国籍法11条1項の規定は憲法に違反して無効であると主張して、(1)原告が日本の国籍を有することの確認、(2)外務大臣が原告に対してした一般旅券の発給をしない旨の処分が無効であることの確認、(3)外務大臣が一般旅券を発給することの義務付け、並びに(4)同項の改廃をしなかった立法不作為、同項を周知しなかったこと及び原告に対する本件処分は国家賠償法上違法である旨主張して、同法1条1項に基づき、原告の被った損害のうち一部の金員及び遅延損害金の支払を求め、〔2〕予備的に、法務大臣が原告の国籍喪失届を不受理として原告に在留資格を付与しなかったことは国賠法上違法である旨主張して、同法1条1項に基づき、原告の被った損害のうち一部の金員及び遅延損害金の支払を求めた事案で、国籍法11条1項の規定は、立法目的に合理性があり、立法目的と手段との間の合理的関連性も認められるから、立法府の裁量権の範囲を逸脱するものではなく、憲法10条、98条2項、31条及び11条に違反するともいえず、また、国籍法11条1項の規定は、憲法11条、13条、22条2項の規定により保障される権利を侵害するものでもなく、これらの各規定に違反するともいえず、さらに、国籍法は、重国籍の防止又は解消方法につき、同法11条1項の適用対象となる自己の志望によって外国の国籍を取得した場合とそれ以外の場合とで一定の区別を設けているものの、そのような区別を設けることの立法目的には合理的な根拠があり、かつ、その区別の具体的内容は上記の立法目的との関連において不合理なものではなく、立法府の裁量判断の範囲を超えるものでもないから、上記の区別は、憲法14条1項に違反するともいえないなどとして、本件訴えのうち、一般旅券の発給の義務付けを求める部分を却下し、その余の請求をいずれも棄却した事例。
2025.12.23
若年成人被選挙権剥奪違憲確認等請求事件(第1事件)、若年成人被選挙権剥奪違憲確認等請求事件(第2事件)
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和8年1月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25624006/東京地方裁判所 令和 7年10月24日 判決(第一審)/令和5年(行ウ)第299号、令和5年(ワ)第17364号
原告らは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律を根拠として令和5年4月9日及び同月23日に執行された統一地方選挙に際し、それぞれ立候補の届出をしたが、各届出は、公職選挙法10条1項3号、4号又は5号の定める被選挙権の各年齢要件を満たさないことを理由に受理されなかったところ、第1事件は、原告a及び原告bが、公選法10条1項4号又は5号が違憲であるなどと主張して、公法上の法律関係に関する訴訟(行政事件訴訟法4条の実質的当事者訴訟)として、(1)主位的に、次回統一地方選挙(神奈川県知事選挙又は京都市議会議員選挙)で被選挙権を行使できる地位にあることの確認、(2)予備的に、〔1〕公選法10条1項4号又は5号を改廃しないこと、又は〔2〕年齢が満30歳又は満25歳に満たないことをもって、同各選挙で被選挙権の行使をさせないことが違法であることの確認をそれぞれ求め、第2事件は、原告らが、本件各規定を改廃しないという立法不作為により被選挙権を行使することができず、これにより精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ、10万円及び遅延損害金の支払を求めた事案で、本件地位確認の訴え及び本件違法確認の訴えは、いずれも、原告a及び原告bの有する権利又は法律的地位についての危険又は不安を除去するために必要かつ適切な内容のものとはいえず、即時確定の利益がないから、確認の利益を欠くものとして、不適法であるとし、また、町村総会における住民参加権と市町村議会の議員の被選挙権とが同列のものということはできず、これらが同列のものであることを前提とする原告らの上記主張は、採用することができないとし、さらに、本件各規定は、憲法14条1項に違反するものとはいえないし、憲法44条ただし書に違反するものともいえないなどとして、第1事件に係る訴えをいずれも却下し、第2事件原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2025.12.02
損害賠償請求事件
LEX/DB25622991/京都地方裁判所 令和 7年 6月26日 判決(第一審)/令和3年(ワ)第1146号
被告大学の教職員で構成される労働組合である原告が、被告大学及び被告京都市に対し、被告大学が設置、運営する本件大学の敷地外構部分に設置されていた立看板に関して、被告市が被告大学に行政指導をし、被告大学が原告の設置した立看板を撤去したことは、違憲、違法であるなどと主張して、共同不法行為に基づき、連帯して損害賠償金等の支払を求めるとともに、被告大学に対しては、上記立看板の撤去及び同立看板を撤去した後、原告との間で一切の調整に応じない対応が不当労働行為に当たると主張して、不法行為に基づく損害賠償金等の支払を求めた事案で、本件行政指導は、被告大学に対して行われたものであり、原告主張に係る利用者、すなわち立看板を掲出し、あるいはしようとする者に対する制約を直截の目的とするものではないこと、原告が、被告大学の管理する本部構内について、これを立看板の設置場所として当然に利用する権原を有するとも認められないことなどに照らすと、本件行政指導が違法とはいえないし、被告大学が、被告大学の敷地の管理権に基づき、本部構内の外構部分に立看板を設置することを禁じる規程を制定し、本件規程に基づき本件両撤去行為をしたことが、原告に対する不当労働行為に当たるともいえず、さらに、被告大学は、原告に対し、外構部分への立看板の設置については許容できないことを明確に伝えつつ、原告に生じる不利益を低減させるように代替措置を提案していたと認められるのであるから、団体交渉に臨む態度が不誠実であったとも認められないとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2025.11.18
性別の取扱いの変更申立事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和8年1月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25623511/札幌家庭裁判所 令和 7年 9月19日 審判(第一審)/令和6年(家)第1212号
生物学的な性別が男性である申立人が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の5号規定に係る要件(外観要件)について、〔1〕主位的には、これを合憲的に限定解釈して、申立人においても外観要件を充足すると主張し、〔2〕予備的には、外観要件自体が憲法13条に反して違憲無効である(法令違憲)、又は、申立人に外観要件を適用することが憲法13条に反して違憲無効である(適用違憲)と主張して、申立人の性別の取扱いを男から女に変更するとの審判を求めた事案で、申立人が、性同一性障害者に当たること及び同法3条1項の1号規定から3号規定までの各規定をいずれも充足することは明らかである一方、性別適合手術及びホルモン療法はいずれについても未施行であり、外観要件である5号規定については充足しないというべきであるところ、5号規定による身体への侵襲を受けない自由の制約については、現時点において、その必要性が相当に低く、その程度が重大なものとなっていることなどを総合的に較量すれば、それが必要かつ合理的なものとはいえないから、5号規定は憲法13条に違反するものというべきであり、これを充足する必要はないと認められるとして、本件申立てを認容した事例。
2025.11.18
性別の取扱いの変更申立事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和8年1月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25623512/札幌家庭裁判所 令和 7年 9月19日 審判(第一審)/令和7年(家)第1099号
生物学的な性別が女性である申立人が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の5号規定に係る要件(外観要件)について、〔1〕主位的には、これを合憲的に限定解釈して、申立人においても外観要件を充足すると主張し、〔2〕予備的には、外観要件自体が憲法13条に反して違憲無効である(法令違憲)、又は、申立人に外観要件を適用することが憲法13条に反して違憲無効である(適用違憲)と主張して、申立人の性別の取扱いを女から男に変更するとの審判を求めた事案で、申立人が、性同一性障害者に当たること及び同法3条1項の1号規定から3号規定までの各規定をいずれも充足することは明らかである一方、性別適合手術及びホルモン療法はいずれについても未施行であり、外観要件である5号規定を充足しないというべきであるが、5号規定による身体への侵襲を受けない自由の制約については、現時点において、その必要性が相当に低く、その程度が重大なものとなっていることなどを総合的に較量すれば、それが必要かつ合理的なものとはいえないから、5号規定は憲法13条に違反するものというべきであり、これを充足する必要はないと認められるとして、本件申立てを認容した事例。
2025.10.28
選挙無効請求事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年12月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25623364/最高裁判所第二小法廷 令和 7年 9月26日 判決(上告審)/令和7年(行ツ)第155号
令和6年10月27日施行の第50回衆議院議員総選挙について、東京都第5区、同第8区、同第28区及び同第30区の選挙人である原審原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の定数配分及び選挙区割りに関する公職選挙法の規定は、選挙権(投票価値)の平等の保障に反するなど憲法に違反する無効なものであるから、これらに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟で、原審が、本件選挙当時における選挙区間の投票価値の較差の拡大をもって、本件選挙区割りが本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものということはできないとして、請求をいずれも棄却したところ、原審原告らが上告した事案で、本件選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできないから、原審の判断は、是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(意見あり)。
2025.10.28
選挙無効請求事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年12月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25623365/最高裁判所第二小法廷 令和 7年 9月26日 判決(上告審)/令和7年(行ツ)第117号
令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙について、広島県第1区及び同第2区の選挙人である原審原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して、公職選挙法204条に基づき、本件選挙の無効を求め、原審が請求をいずれも棄却したところ、原審原告らが上告した事案で、本件選挙区割りの下においては、令和2年国勢調査の結果による選挙区間の人口の最大較差が1対1.999であったのに対し、本件選挙当日には、選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.059となっており、本件区割制度が、選挙区を改定してもその後に選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを前提とするものであって、このような制度に合理性が認められるところ、本件選挙当時における選挙区間の投票価値の較差が自然的な人口異動以外の要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれず、本件選挙区割りの下におけるその拡大の程度が著しいものともいえないから、上記の選挙区間の投票価値の較差の状況をもって、本件選挙区割りが本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできないというべきであるから、本件選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできないとして、本件上告を棄却した事例(意見あり)。
2025.10.28
選挙無効請求事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年12月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25623366/最高裁判所第二小法廷 令和 7年 9月26日 判決(上告審)/令和7年(行ツ)第128号 他
令和6年10月27日に行われた衆議院議員総選挙について、公職選挙法別表第1に定める各選挙区の選挙人である上告人らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する同法の規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して、選挙無効訴訟を提起し、14件の原審が、本件選挙区割りが衆議院議員選挙区画定審議会設置法又は憲法に違反するに至っていたということはできないとして、上告人らの請求をいずれも棄却したところ、上告人らがそれぞれ上告した事案で、本件選挙区割りの下においては、令和2年国勢調査の結果による選挙区間の人口の最大較差が1対1.999であったのに対し、本件選挙当日には、選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.059となっており、本件区割制度が、選挙区を改定してもその後に選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを前提とするものであるところ、本件選挙当時における選挙区間の投票価値の較差が自然的な人口異動以外の要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれず、本件選挙区割りの下におけるその拡大の程度が著しいものともいえないから、上記の選挙区間の投票価値の較差の状況をもって、本件選挙区割りが本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできないというべきであり、本件選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできないから、原審の各判断は、いずれも是認することができるとして、本件各上告を棄却した事例(意見あり)。
2025.07.29
持続化給付金等支払請求事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年9月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574371/最高裁判所第一小法廷 令和 7年 6月16日 判決(上告審)/令和6年(行ツ)第21号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条7項1号所定の無店舗型性風俗特殊営業を行う事業者である上告人が、新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けて被上告人国が策定した持続化給付金給付規程及び家賃支援給付金給付規程に定める各給付金につき、本件特殊営業を行う事業者には給付しないこととされていることが、憲法14条1項、22条1項に違反するなどと主張して、被上告人らに対し、本件各給付金の支払等を求め、第一審が、上告人の各確認の訴えをいずれも却下し、その余の請求をいずれも棄却したことから、上告人が控訴し、控訴審が控訴をいずれも棄却したところ、上告人が上告した事案で、本件各取扱いは、憲法14条1項に違反するものとはいえないなどとして、本件上告を棄却した事例(反対意見及び補足意見あり)。
2025.07.15
児童扶養手当支給停止処分取消請求事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年8月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574366/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 6月10日 判決(上告審)/令和6年(行ツ)第54号
配偶者のない母として4人の子を養育し、児童扶養手当を受給していた上告人が、平成29年4月20日、平成27年11月分に遡って障害基礎年金(障害等級1級)の給付決定を受け、同月分から平成29年3月分までの障害基礎年金として195万3158円の支払を受け、同年4月分以降も障害基礎年金の支給を受けることになったため、京都府知事から、児童扶養手当法(令和2年法律第40号による改正前)13条の2第2項の規定を受けた同法施行令(令和2年政令第318号による改正前)6条の4に基づき、同年2月分以降の児童扶養手当の支給を停止する旨の処分を受けたことから、児童扶養手当法施行令(同改正前)6条の4のうち、障害基礎年金の子加算部分だけでなく本体部分についても併給調整の対象として児童扶養手当の支給を停止する旨を定めた部分は、〔1〕児童扶養手当法(同改正前)13条の2第2項に基づく法律の委任の範囲を逸脱した違法、無効なものである、〔2〕憲法14条、25条及び国際人権規約等の条約に反した無効なものであると主張して、本件併給調整規定に基づいてされた本件各処分のうち、それぞれ障害基礎年金の子加算部分に相当する部分を除く部分の取消しを求め、第一審が請求をいずれも棄却したことから、上告人が控訴し、控訴審が、本件控訴を棄却したところ、上告人が上告した事案で、児童扶養手当法13条の2第2項1号の規定及び児童扶養手当法施行令6条の4の規定のうち同号所定の公的年金給付中の受給権者に子があることによって加算された部分以外の部分を対象として児童扶養手当の支給を制限する旨を定める部分が、障害基礎年金との併給調整において憲法25条、14条1項に違反するものとはいえないなどとして、本件上告を棄却した事例(反対意見あり)。
2025.06.17
生物学上の親調査義務確認等請求事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年7月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
★「新・判例解説Watch」国際公法分野 令和7年7月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25622506/東京地方裁判所 令和 7年 4月21日 判決(第一審)/令和3年(ワ)第28700号
昭和33年○月に本件産院にて出生し、本件産院内において他の新生児と取り違えられたために生物学上の親とは異なる夫婦の下で育てられた原告が、本件産院を設置・管理していた被告・東京都に対し、〔1〕主位的には、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)及び児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)の各規定に基づき(主位的調査請求)、予備的に分娩助産契約(予備的請求1)、更に予備的に医療事故に準ずる重大な問題事案におけるてん末報告義務(予備的請求2)、更に予備的に上記取り違えを先行行為として条理上認められる原状回復義務(予備的請求3)に基づき、いずれも原告の生物学上の親を特定するための調査の実施等を求め、また、〔2〕主位的調査請求と選択的に、被告が自由権規約及び子どもの権利条約の各規定に基づく調査義務を負うことの確認を求めるとともに、〔3〕被告が調査義務を怠ったことを理由として、主位的には不法行為に基づき、損害賠償として慰謝料等及び遅延損害金の支払を求め、予備的には分娩助産契約の債務不履行に基づき、損害賠償として慰謝料及び遅延損害金の支払を求めた事案で、本件訴えのうち本件調査請求に係る部分が不適法であるとはいえず、また本件訴えのうち本件義務確認請求に係る部分について、直ちに不適法であるとは認められないとしたうえで、本件各条約の各規定に基づき本件調査請求ないし本件義務確認請求に係る具体的な権利が原告に付与されていると解することはできないから、本件調査請求のうち、主位的調査請求は理由がなく、また、本件義務確認請求についても理由がないが、原告の本件分娩助産契約に基づく本件調査請求(予備的請求1)は、一部理由があるとして、請求〔1〕を一部認容し、その余の請求を棄却した事例。
2025.06.03
性別の取扱いの変更申立事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年5月2日解説記事が掲載されました★
LEX/DB25622260/京都家庭裁判所 令和 7年 3月19日 審判(第一審)
性同一性障害の診断を受けた生物学的には男性である申立人が、妻との婚姻関係を維持したまま性別の取扱いを男から女に変更することを求め、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項に基づき、男から女への性別の変更を申し立て、申立人は、同項2号の「現に婚姻をしていないこと」の要件(非婚要件)は、憲法13条及び24条に違反するから無効であり、非婚要件を除いた同項の要件をすべて満たす申立人については、性別の取扱いを変更する旨の審判がされるべきであると主張した事案で、非婚要件の存在により、憲法上保障された婚姻の継続という法的利益又は人権が制約を受けるとしても、あるいは二者択一として、性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける法的利益に制約を受けるとしても、国会において定められるべき婚姻関係を含めた法律関係の整合性の担保として非婚要件が定められている趣旨に照らせば、非婚要件が、直ちに憲法13条、24条に反して無効となると解することはできず、本件申立ては、非婚要件を欠くものであって、理由がないことに帰するといわざるを得ないとして、本件申立てを却下した事例。
2025.04.30
久米至聖廟撤去を怠る事実の違法確認等請求事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年5月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574147/最高裁判所第一小法廷 令和 7年 3月17日 判決(上告審)/令和5年(行ツ)第261号
那覇市の住民である上告人が、市長が市の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀る久米至聖廟を設置することを参加人に許可し、これに基づき市が本件土地を本件施設の敷地としての利用に供していることは、憲法上の政教分離原則及びそれに基づく憲法の諸規定(20条1項後段、3項、89条)に違反し、参加人に対し本件施設の収去及び本件土地の明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるなどとして、被上告人市長を相手に、地方自治法242条の2第1項3号に基づき、上記の怠る事実の違法確認を求めるとともに、被上告人市を相手に、同項2号に基づき、市長が参加人に対してした本件施設の一部に係る固定資産税の減免処分の無効確認を求め、第一審が請求をいずれも棄却したところ、上告人が控訴し、控訴審が控訴をいずれも棄却したことから、上告人が上告した事案で、社会通念に照らして総合的に判断すると、市長が本件設置許可をし、これに基づき市が本件土地を本件施設の敷地としての利用に供していることは、市と宗教との関わり合いの程度が、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法上の政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反するものではないと解するのが相当であるとし、本件上告について提出された上告状及び上告理由書には上告人の被上告人市に対する上告理由の記載がないから、被上告人市に対する上告は不適法として却下すべきであるとして、上告人の被上告人那覇市長に対する上告を棄却し、上告人の被上告人那覇市に対する上告を却下した事例。
2025.04.15
過料決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年5月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574121/最高裁判所第一小法廷 令和 7年 3月 3日 決定(許可抗告審)/令和6年(許)第31号
宗教法人である世界平和統一家庭連合(本件法人)の所轄庁である文部科学大臣は、東京地方裁判所に対し、本件法人が、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、報告をしなかったことは、宗教法人の代表役員等を過料に処する場合について定める宗教法人法88条10号に該当するとして、本件法人の代表役員である抗告人を過料に処すべきとする通知をし、東京地方裁判所は、抗告人を過料10万円に処する旨の決定(原々決定)をしたところ、抗告人が抗告し、抗告審が原々決定に対する抗告人の抗告を棄却した(原決定)ことから、抗告人が許可抗告をした事案で、民法709条の不法行為を構成する行為は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害するものであるから、当該行為が著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる事態を招来するものであってこれに関係した宗教団体に法律上の能力を与えたままにしておくことが不適切となることも、十分にあり得ることであるから、同条の不法行為を構成する行為が同法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たると解することは、同号の上記趣旨に沿うものというべきであり、また、解散命令は、宗教法人の法人格を失わせる効力を有するにとどまり、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないものであるところ、ある行為が同号所定の行為に当たるといえるためには、その行為が単に法令に違反するだけでなく、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為でなければならないことなどに照らせば、上記のように解したとしても、同号の規定が、宗教法人の解散命令の事由を定めるものとして、不明確であるとも過度に緩やかであるともいえず、以上によれば、民法709条の不法行為を構成する行為は、同法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たると解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができるとして、本件抗告を棄却した事例。
2025.04.01
特別地方交付税の額の決定取消請求事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和7年5月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年5月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574103/最高裁判所第一小法廷 令和 7年 2月27日 判決(上告審)/令和5年(行ヒ)第297号
上告人・泉佐野市が、総務大臣がした特別交付税の額の決定(本件各決定)について、令和元年度における市町村に係る特別交付税の額の算定方法の特例を定めた特別交付税に関する省令附則5条21項(令和2年総務省令第111号による改正前)及び同附則7条15項(令和2年総務省令第12号による改正前)は、いわゆるふるさと納税に係る収入が多額であることをもって特別交付税の額を減額するものであって、地方交付税法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるなどと主張して、被上告人・国に対し、本件各決定の取消しを求め、第一審が上告人の請求をいずれも認容したところ、被上告人が控訴し、控訴審が、本件訴えは、行政主体としての上告人が、法規の適用の適正をめぐる一般公益の保護を目的として提起したものであって、自己の財産上の権利利益の保護救済を目的として提起したものと見ることはできないから、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」には当たらないとして、原判決を取り消し、上告人の訴えをいずれも却下したことから、上告人が上告した事案で、特別交付税は、地方交付税の一種であり、交付されるべき具体的な額は、総務大臣がする決定によって定められるものである(地方交付税法4条2号、6条の2第1項、15条1項、2項、16条1項)から、特別交付税の交付の原因となる国と地方団体との間の法律関係は、上記決定によって発生する金銭の給付に係る具体的な債権債務関係であるということができ、地方団体が特別交付税の額の決定の取消しを求める訴えは、国と当該地方団体との間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に当たるというべきであり、また、特別交付税の額の決定は、地方交付税法及び特別交付税に関する省令に従ってされるべきものであるから、上記訴えは、法令の適用により終局的に解決することができるものといえ、以上によれば、地方団体が特別交付税の額の決定の取消しを求める訴えは、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たると解するのが相当であるとして、原判決を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻した事例。
2025.03.25
旅券発給拒否取消等請求控訴事件
LEX/DB25621991/東京高等裁判所 令和 7年 1月30日 判決(控訴審)/令和6年(行コ)第52号
一審原告(フリージャーナリスト)は、外務大臣に対して一般旅券の発給申請をし、外務大臣から、トルコへの入国が認められない者であるから旅券法13条1項1号に該当するとして、一般旅券の発給拒否処分を受けたため、一審原告は、一審被告(国)に対し、〔1〕本件旅券発給拒否処分の取消し、〔2〕主位的に全ての地域を渡航先として記載した一般旅券の発給の義務付け、予備的にトルコ以外の全ての地域を渡航先として記載した一般旅券の発給の義務付け、〔3〕外務大臣が本件旅券発給拒否処分をしたことが違法であるとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として慰謝料等の支払を求め、原審が〔1〕を認容し、〔2〕及び〔3〕を棄却したところ、請求全部の棄却を求めて一審被告が控訴し、請求全部の認容を求めて一審原告が控訴した事案で、本件旅券発給拒否処分の取消請求は理由があるから認容し、その余の請求は理由がないからいずれも棄却すべきであるとし、これと同旨の原判決は相当であるとして、一審被告及び一審原告の本件各控訴をいずれも棄却した事例。
2025.02.25
選挙無効請求事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年4月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574034/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 1月28日 判決(上告審)/令和5年(行ツ)第404号 等
千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)に基づいて令和5年4月9日に行われた千葉県議会議員一般選挙について、船橋市選挙区の選挙人である上告人が、本件条例のうち各選挙区において選挙すべき議員の数を定める規定が公職選挙法15条8項及び憲法14条1項に違反し無効であるから、これに基づいて行われた本件選挙の本件選挙区における選挙も無効であると主張して選挙無効を求めたところ、原審が、本件定数配分規定が定められた本件改正当時において同法15条8項ただし書にいう特別の事情があるとの評価がそれ自体として合理性を欠いていたとも、本件選挙当時において上記の特別の事情があるとの評価の合理性を基礎付ける事情が失われたともいい難いから、本件選挙当時における本件定数配分規定が公選法15条8項に違反していたものとはいえず、適法というべきであるとして、請求を棄却したことから、上告人が上告及び上告受理申立てをした事案で、本件選挙当時、本件条例による各選挙区に対する定数の配分が千葉県議会の合理的裁量の限界を超えるものとはいえず、本件定数配分規定が憲法14条1項に違反していたものとはいえないことは、当裁判所大法廷判決(最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁等)の趣旨に徴して明らかというべきであり、また、その余の上告理由は、違憲をいうが、その前提を欠くものであって、民事訴訟法312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しないとして、本件上告を棄却した事例(補足意見、反対意見あり)。
2025.02.18
第二次世界大戦戦没者合祀絶止等請求事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年4月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574001/最高裁判所第二小法廷 令和 7年 1月17日 判決(上告審)/令和6年(受)第275号
靖國神社は、被上告人(被告・被控訴人)・国から第二次世界大戦で戦没した軍人及び軍属の氏名等の情報の提供を受け、それらの者を合祀していたところ、大韓民国の国籍を有する上告人(原告・控訴人)らが、被上告人に対し、被上告人が、上告人らの了承を得ずに、靖國神社に上告人らの各父親の情報をも提供した行為は違法であるなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払等を求め、第一審が請求をいずれも棄却した事件の上告審の事案で、上告人らの請求に係る損害賠償請求権については、平成29年法律第44号による改正前の民法724条後段の除斥期間が経過していることが明らかであり、そして、原審が適法に確定した事実及び上告人らの主張を精査しても、被上告人が上記除斥期間の主張をすることが、信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断するに足りる事情があるとはうかがわれないから、本件情報提供行為に係る上告人らの損害賠償請求を棄却すべきものとした原審の結論は是認することができ、論旨は、原判決の結論に影響を及ぼさない事項についての違法をいうに帰着し、採用することができないとして、本件上告を棄却した事例(原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻す旨の反対意見あり)。
2024.11.12
大垣警察市民監視国家賠償、個人情報抹消請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和6年12月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25621036/名古屋高等裁判所 令和 6年 9月13日 判決 (控訴審)/令和4年(ネ)第287号
岐阜県警察本部警備部及び岐阜県警各警察署警備課が、一審原告らの個人情報を長年にわたって収集、保有し、大垣警察署警備課の警察官がそれらの情報の一部を民間企業に提供したことにより、一審原告らの人格権としてのプライバシー等が侵害されたとして、一審原告らが、一審被告県に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金の支払等を求め(甲事件)、また、一審原告らが、人格権としてのプライバシーに基づき、一審被告県に対しては岐阜県警等が保有する、一審被告国に対しては警察庁警備局が保有する、一審原告らの個人情報の抹消を求め(乙事件)、原審が、甲事件について、一審原告らの一審被告県に対する請求を一部認容し、その余をいずれも棄却し、乙事件につき、抹消を求める内容の特定性を欠くから不適法であるとして、一審原告らの一審被告県及び一審被告国に対する訴えをいずれも却下したところ、一審被告県及び一審原告らがそれぞれ控訴し、なお、一審原告らは、当審において、乙事件の請求につき、抹消請求の対象を変更して、訴えの変更をした事案で、甲事件について、原判決を一部変更し、一方、乙事件について、大垣警察を含めた岐阜県警による一審原告らの上記個人情報の保有は、一審原告らのプライバシーを侵害するもので違法であり、とりわけ本件においては、一審原告らの個人情報が、法令の根拠に基づかず、正当な行政目的の範囲を逸脱して、第三者であるq2に開示され提供されているのであり、岐阜県警が保有する一審原告らの個人情報が、法令等の根拠に基づかず、正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示される具体的現実的な危険が生じていると認められるから、一審原告らは、人格権に基づく妨害排除請求として、一審被告県に対し、上記各個人情報の抹消を請求できるものと認められ、一審原告らの乙事件の変更後の一審被告県に対する予備的請求3は、いずれも理由があるが、一審被告国に対する予備的請求3は、一審被告国が一審原告らの個人情報を保有しているものとは認められないから、いずれも理由がないとして、一部認容、一部却下し、その余を棄却した事例。
2024.11.05
就籍許可申立許可審判に対する即時抗告事件
★「「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年1月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
★「新・判例解説Watch」国際公法分野 令和7年7月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25620948/名古屋高等裁判所 令和 6年 9月11日 決定 (抗告審(即時抗告))/令和5年(ラ)第431号
抗告人が、2022年に、かつてアフガニスタン・イスラム共和国国籍を有していた抗告人父母の間の子として愛知県豊橋市内において出生したが、この頃までに、共和国全土はタリバーンによって国家の要件を欠くなどしたために抗告人父母はいずれも無国籍となっていたから、抗告人は、日本で生まれ、かつ、父母がともに国籍を有しない子であり、国籍法2条3号後段の要件を満たすとして、日本国民として就籍の許可を求めたところ、原審が本件申立てを却下したことから、抗告人が抗告した事案で、抗告人が出生した当時、共和国は、実質的に国家としての実体を失っていたというべきであり、また、暫定政府(タリバン政権)は、「自国民の保護等を他国の政府に求めることができない。」という要件を欠いている状態にあったと解されるし、抗告人父母は、かつて共和国が存在していた領域に戻って暫定政府の保護を受ける意思はないものと解され、そして、国籍は、当該国家が存在することを当然の前提とするものであるから、共和国の国籍をもと有していた抗告人父母は、いずれも、上記当時、少なくとも実質的に国籍法2条3号にいう「国籍を有しないとき」に該当する者であったというべきであるが、抗告人父母は、共和国及び暫定政府のいずれからも国民としての保護を受けられない状態になっていたというべきであるから、抗告人父母が共和国又は首長国の国籍を有するものとし、日本において出生した抗告人に日本国籍の取得を認めないことは、可及的に無国籍者の発生を防止して国家による本人の利益の保護を図るという同号の趣旨に反すると解されるし、児童は出生の時から国籍を取得する権利を有し、締約国はこの権利の実現を確保するとしている「児童の権利に関する条約」7条の趣旨にも反するものと解され、抗告人は、国籍法2条3号に基づき、日本国籍を取得したものというべきであるとして、原審判を取り消し、抗告人の申立てを認容した事例。