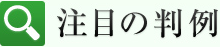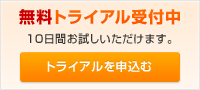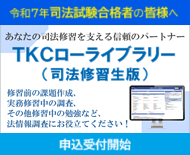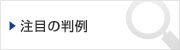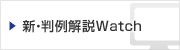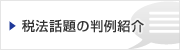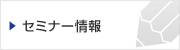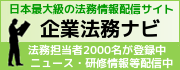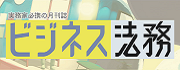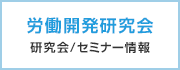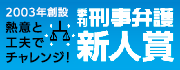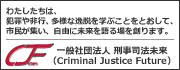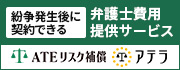2020.08.04
発信者情報開示請求事件
LEX/DB25570963/最高裁判所第三小法廷 令和 2年 7月21日 判決 (上告審)/平成30年(受)第1412号
本件写真の著作者である被上告人(控訴人・原告)が、ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれるメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)のウェブサイトにされた投稿により本件写真に係る被上告人の氏名表示権等を侵害されたとして、ツイッターを運営する上告人(被控訴人・被告。米国法人)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき、上記投稿に係る発信者情報の開示を求めたところ、原判決が、本件各アカウントのタイムラインにおいて表示される画像は、表示するに際して、HTMLプログラム等により、位置や大きさなどを指定されたために、本件各表示画像となったものと認められるから、本件リツイート者らによって改変されたもので、同一性保持権が侵害されているということができるとし、第1審判決を変更したため、上告人が上告した事案で、本件各リツイートによる本件氏名表示権の侵害について、本件各リツイート者は、プロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報の発信者」に該当し、かつ、同項1号の「侵害情報の流通によって」被上告人の権利を侵害したものというべきであるとし、原審の判断は是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(反対意見、補足意見がある)。