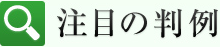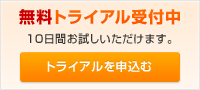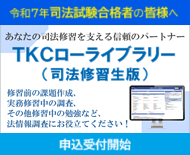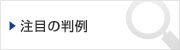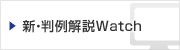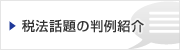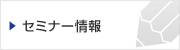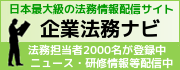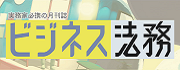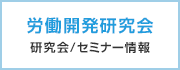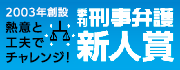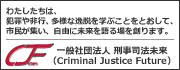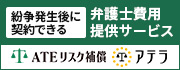2021.06.08
執行判決請求、民訴法260条2項の申立て事件
LEX/DB25571523/最高裁判所第三小法廷 令和 3年 5月25日 判決 (上告審)/令和2年(受)第170号 等
被上告人らが、上告人に対して損害賠償を命じた米国カリフォルニア州の裁判所の判決について、民事執行法24条に基づいて提起した執行判決を求め、原審は、本件外国判決のうち上告人に対して14万0635.54米国ドル及びこれに対する本件外国判決の言渡し日の翌日である平成27年3月21日から支払済みまでの利息の支払を命じた部分についての執行判決を求めた被上告人らの請求を認容したため、上告人が上告した事案で、本件弁済が本件懲罰的損害賠償部分に係る債権に充当されたものとして本件外国判決についての執行判決をすることはできず、本件外国判決のうち本件懲罰的損害賠償部分を除く部分は民事訴訟法118条3号に掲げる要件を具備すると認められ、本件外国判決については、本件弁済により本件外国判決のうち本件懲罰的損害賠償部分を除く部分に係る債権が本件弁済の額の限度で消滅したものとし、その残額である5万0635.54米国ドル及びこれに対する利息の支払を命じた部分に限り執行判決をすべきであるとして、原判決中、主文第1項及び第2項を破棄し、被上告人らの請求を認容した第1審判決は正当であり、被上告人らの控訴を棄却した事例。