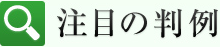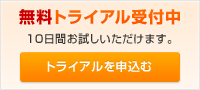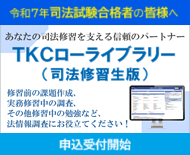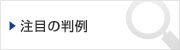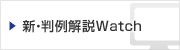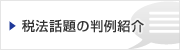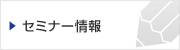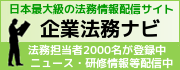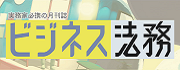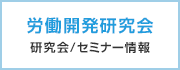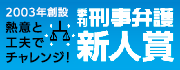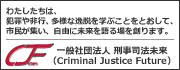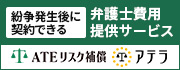2022.01.25
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25591382/札幌高等裁判所 令和 3年12月14日 判決 (控訴審)/令和3年(ネ)第18号
北海道内の漁業者である控訴人らが、〔1〕被控訴人(国・北海道)らは、遅くとも平成29年7月1日までに法的拘束力のある漁獲制限をする義務があったにもかかわらず、これを怠り、漁業者の自主管理に委ねた結果、第3管理期間において上限を大幅に超過する漁獲を招き、控訴人らは第4管理期間以降のくろまぐろ漁が事実上できなくなった、〔2〕被控訴人国の第4管理期間における超過差引きは裁量権を逸脱・濫用するものであり違法であるなどと主張して、被控訴人らに対し、国家賠償法1条1項に基づき、第4管理期間以降6年間の逸失利益及び慰謝料等の支払をそれぞれ求めたところ、原審は、控訴人らの請求をいずれも棄却したため、控訴人らは、原判決を不服として控訴した事案で、被控訴人国の資源管理法、漁業法及び水産資源保護法に基づく規制権限の不行使について、国家賠償法1条1項の適用上、違法とはいえないとし、また、被控訴人北海道の規制権限不行使についても違法とはいえないなどとして、原判決は相当であるとし、本件各控訴を棄却した事例。