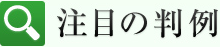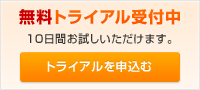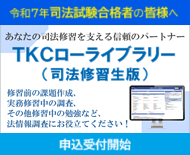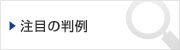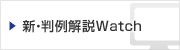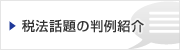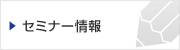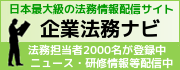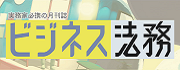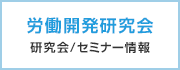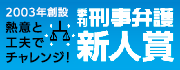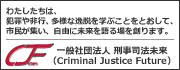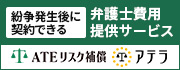2021.02.16
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25568416/名古屋高等裁判所 令和 3年 1月13日 判決 (控訴審)/令和1年(ネ)第664号
控訴人が、被控訴人(国)に対し、入国管理局の職員が、難民不認定処分に対する取消訴訟等の意向を示していた控訴人を集団送還の対象者に選定した上、本件異議棄却決定の後、上記訴訟等の提起を妨害するために、上記決定の告知をその40日後まであえて遅らせ、同告知後に弁護士との連絡ができないようにしたほか、帰国後に訴訟ができるとの虚偽の説明をするなどして、本件送還をしたことにより、控訴人の裁判を受ける権利を侵害したなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金の支払を求め、原審は、入管法上、在留資格未取得外国人について難民不認定処分に対する異議申立てについての決定があるまで送還を停止する旨の規定以外に送還を停止すべき旨の規定がなく、被退去強制者については裁判所による執行停止決定がない限り送還が法令上停止されるものでなく、これらに当たる場合でなければ入管職員に送還を停止すべき義務が生ずるものではないから、本件異議棄却決定がされ執行停止決定を得ていない控訴人を送還対象者に選定し、強制送還を中止しなかったことにつき、国賠法1条1項の適用上違法があるとはいえないとしつつ、本件異議棄却決定の告知に際して、控訴人が送還された後も難民不認定処分に対する取消訴訟が可能であるかのような誤った教示をしたことは、同項の適用上違法であるとして、控訴人の請求につき合計8万8000円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余を棄却したところ、控訴人がその敗訴部分を不服として控訴した事案で、控訴人の請求は、44万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余を棄却すべきところ、これと異なる原判決は一部不当であるとし、原判決を変更した事例。