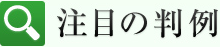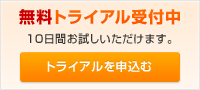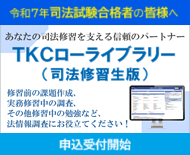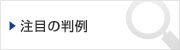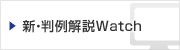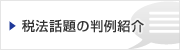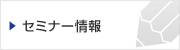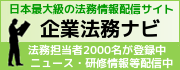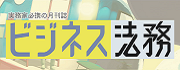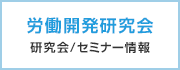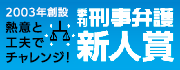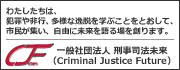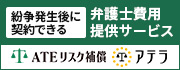2020.03.17
債務確認請求本訴、求償金請求反訴事件
★「新・判例解説Watch」財産法分野 6月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
★「新・判例解説Watch」労働法分野 8月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
★「新・判例解説Watch」財産法分野 6月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
★「新・判例解説Watch」労働法分野 8月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25564902/最高裁判所第二小法廷 令和 2年 2月28日 判決 (上告審)/平成30年(受)第1429号
本件本訴請求は、被上告人の被用者であった上告人が、被上告人の事業の執行としてトラックを運転中に起こした交通事故に関し、第三者に加えた損害を賠償したことにより被上告人に対する求償権を取得したなどと主張して、被上告人に対し、求償金等の支払を求め、原審は、上告人の本訴請求を棄却したため、上告人が上告した事案において、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができるものと解すべきであるとしたうえで、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決中、上告人の本訴請求に関する部分を破棄し、上告人が被上告人に対して求償することができる額について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻した事例(補足意見がある)。