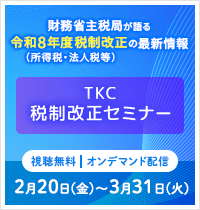更新日 2025.01.09

株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹
令和6年9月27日に、法人税法132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)の適用の可否が争われていたPGMプロパティーズ事件で、東京地裁の判決が下され、納税者側が完全勝訴となりました。この事件は、現在、国側が控訴しており、まだ判決が確定しているわけではありませんが、この事件の判決がどのような内容で確定するのかによって子会社等の組織再編成に影響が出てくるというケースもあると考えられます。
今回は、この事件の判決を取り上げてみます。
当コラムのポイント
- TPR事件の判決を杓子定規に用いるのは適切ではない
- 国税当局は、本件が敗訴で確定したとしても、TPR事件の合併と同じようなことをしたもの、本件のような事情がないまま休眠状態となっている法人を吸収合併したものなどに対しては、租税回避として課税することになる可能性が高いため、十分に注意をする必要がある
- 目次
-
4.本件地裁判決の確認と筆者の意見
(3) 本件地裁判決の第3の2と4で述べられている節税と租税回避の区別に関する判示について
本件地裁判決の第3の3の部分ではなく、同2の部分となりますが、本件地裁判決においては、東京地裁が租税回避となるのか否かという判断の基準を非常に具体的に示していることにも注目する必要があります。
本件地裁判決の第3の2(2)においては、次のように判示されています。
「 そして、①適格合併が行われた結果、未処理欠損金額が引き継がれ、租税負担が減少する場合があるというのは、組織再編成税制が予定しているものであること(むしろ、適格合併の場合に譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させることは、組織再編税制の趣旨そのものである。後記3参照)、②利益を生み出し、これを株主に対して還元することを究極の目的とする株式会社において、一定規模以上の取引をするに当たり、税務上の影響を全く考慮しないことは考え難く(甲64参照)、むしろ、かかる考慮をしないで取引を行えば、取締役の責任を追及される事態も生じかねないのであって、株式会社が事業の目的に沿って種々の経済活動を遂行するに当たり、業務の管理・遂行上、財務上又は税務上等の様々な観点から、利益を最大化し得る方法を法令の許容する範囲内で自由に選択することができると解されることからすると、行為・計算の不自然性が全く認められない場合や、そのような行為・計算を行うことの合理的な理由となる事業目的等が十分に存在すると認められる場合には、他の事情を考慮するまでもなく、組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用したものということはできず、不当性要件に該当すると判断することは困難である(甲60参照)。
したがって、株式会社が合理的な事業目的のある組織再編成を行うに当たり、通常は想定されない手順や方法ではなく、実態と乖離した形式を作出するものでもない、不自然性の全く認められない複数の手順や方法の中から最も税負担の少ないものを採ったとしても、そのことから直ちに組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用したものということはできない(例えば、引き継がれる末処理欠損金額は、合併の時期によって差異が生ずるが(57条2項、3項、57条の2等参照)、いつ合併するかは基本的に当事者の自由であり、合併につき合理的な事業目的がある場合には、税務上の効果が最大となる時期を見定めて合併を実行したとしても、そのことから直ちに不当性要件に該当すると判断することはできないと解される。)。」(53・54頁)
特に、この最後の括弧書きは、租税回避となるのか否かという判断をする場合の基準については、一般的なことを語って済ますのではなく、可能な限り具体的に語る必要があるということを示すものであって、重要であると考えます。
そして、東京地裁は、このような基準を示した上で、本件地裁判決の第3の4(2)クにおいて、次のような判断を示しています。
「(ア) なお、PGPAH6及びPGMP4らの吸収合併が本件ビジネスモデルに基づくもので、合理的な理由となる事業目的が十分に存在するものであり(前記ア)、また、本件各合併に当たり、本件合併1と本件合併2との二段階で行ったことが通常は想定されない、又はう遠な手順や方法をあえて採るものではなく(前記イ、ウ)、一般に採られている合理的な手順・方法の一つであるとしても(前記エ)、PGMグループが本件各合併のスキームを採用するに当たり、本件未処理欠損金額の原告への引継ぎを重視したことは否定し難い(認定事実(4)ア参照。原告も、かかる考慮をしたことを認めている。)。
(イ) しかしながら、本件各合併は、PGMグループで繰り返されていた組織再編成の一環として本件ビジネスモデルに基づき事務管理費の削減と経営効率の向上を図ることを目的として実行されたものであり、しかも、前記ウ、カ、キのような事情があったから、本件各合併に係るスキームを採用したことについても、合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在していたということができる。
(ウ) また、そもそも、株式会社が一定規模以上の取引をするに当たり、税務上の影響を全く考慮しないことは考え難く、そのような考慮をすることはむしろ当然であって、株式会社が合理的な事業目的のある組織再編成を行うに当たり、通常は想定されない手順や方法ではなく、実態と乖離した形式を作出するものでもない、不自然性の全く認められない複数の手順や方法の中から最も税負担の少ないものを採ったとしても、そのことから直ちに組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用したものということはできない。
そして、前記イからキまでにおいて認定、説示したとおり、本件各合併に係るスキームは、通常は想定されない手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなどといった、不自然なものでは全くないのであるから、そのスキームの採用に当たり、本件未処理欠損金額の原告への引継ぎを重視したとしても、このことをもって、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるものということはできない(前記2(2)参照)。」(74・75頁)
上記(ア)においては、東京地裁は、「本件合併1と本件合併2との二段階で行ったことが通常は想定されない、又はう遠な手順や方法をあえて採るものではな(い)」と判示しています。
これは、国税庁自身が「三社合併における適格判定について(照会)」という照会回答事例を公表し、その中で三社合併において個々の合併に順序を付して適格判定を行うこととして差し支えないという見解を示していることからすると、当然のことであって、「本件合併1と本件合併2との二段階で行ったこと」が支配関係法人間の適格合併の要件となっている従業者引継要件や事業継続要件の規定の本来の趣旨及び目的を逸脱する態様で当該規定の適用を免れるものとはならないということは、明らかです。
また、上記(ア)において、東京地裁は、「PGMグループが本件各合併のスキームを採用するに当たり、本件未処理欠損金額の原告への引継ぎを重視したことは否定し難い(認定事実(4)ア参照。原告も、かかる考慮をしたことを認めている。)」と述べています。
これは、原告が税負担を確認する資料を作成してできるだけ税負担が少なくなるスキームを採用しようと検討した事実があることをいうものです。
しかし、東京地裁は、上記(イ)と(ウ)で、原告がそのようなスキームを採用しようとしていたとしても、それは「当然」のことであって、「そのことから直ちに組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用したものということはできない」と説示しています。
納税者は、節税の金額が大きいスキームを採ることが可能である場合には、できるだけそのようなスキームを採ろうとするわけであり、節税の金額が大きければ大きいほど、納税者にとって、節税が重要な目的となることは、当然のことです。このため、法人税法132条の2は、税負担の減少額が大きい場合には同条の適用があって税負担の減少額が小さい場合には同条の適用がないなどという考え方は、採っておらず、同条がそのような考え方を採っていないということは、ヤフー事件最高裁判決の不当性要件の判断の枠組みからそのような考え方を導き出し得ないことからも、明らかです。
そして、この説示に続く上記(ウ)の「そして」以下の部分には、「前記イからキまで」とありますが、この部分では、本件の事実関係が非常に詳しく書かれています。
このように、東京地裁は本件が租税回避とはならないということを本件の事実関係から非常に詳細に説明しているというところも、非常に重要であって、他の案件において租税回避であるのか否かということを判断するに当たって、大変、参考となると考えられます。
過去に法人税法132条を適用して租税回避として課税を行った事案の裁判例を見ると、国側は、納税者が税法上の取扱いを深く検討していたことを理由に挙げて、それが恰も租税回避の証拠であるかの如く主張することが少なくありませんが、納税者が税法上の取扱いを深く検討することは、当然のことであり、また、同法132条の2が適用されるのか否かということは、組織再編成税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様で当該各規定の適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するべきことであって、納税者が税法上の取扱いを深く検討していた事実を並べ立てて、それを根拠に同条が適用されると主張するなどということになると、それは、明らかな同条の解釈誤りであるという指摘を受けることとならざるを得ません。
換言すれば、納税者が当然の権利である「節税」を行っていることを恰も「租税回避」を行っているかの如く主張するのは、不適切であり、納税者が税法を深く学んだり税法上の取扱いを深く検討したりすればするほど、それを理由にして租税回避を行っているとされるなどというようなことは、決してあってはならない、ということです。
なお、上記の判示は、ヤフー事件最高裁判決における不当性の判断の枠組みとして確認した上記2の「ⅳ 判断に当たってどのような事情を考慮すべきか」の中の「等」として、考慮すべき事情に関する判示となっているということを念のために確認しておきます。
この連載の記事
-
2025.01.09
第1回 はじめに、本件の概要と過去判決の確認
-
2025.01.09
第2回 本件地裁判決の確認と筆者の意見(その1)
-
2025.01.09
第3回 本件地裁判決の確認と筆者の意見(その2)
-
2025.01.09
第4回 本件地裁判決の確認と筆者の意見(その3)
-
2025.01.09
第5回(最終回) 最後に
テーマ
プロフィール

免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。