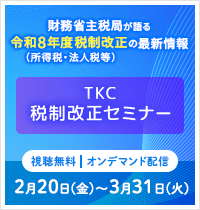更新日 2025.01.09

株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹
令和6年9月27日に、法人税法132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)の適用の可否が争われていたPGMプロパティーズ事件で、東京地裁の判決が下され、納税者側が完全勝訴となりました。この事件は、現在、国側が控訴しており、まだ判決が確定しているわけではありませんが、この事件の判決がどのような内容で確定するのかによって子会社等の組織再編成に影響が出てくるというケースもあると考えられます。
今回は、この事件の判決を取り上げてみます。
当コラムのポイント
- TPR事件の判決を杓子定規に用いるのは適切ではない
- 国税当局は、本件が敗訴で確定したとしても、TPR事件の合併と同じようなことをしたもの、本件のような事情がないまま休眠状態となっている法人を吸収合併したものなどに対しては、租税回避として課税することになる可能性が高いため、十分に注意をする必要がある
- 目次
-
最後に
筆者は、平成18年に退官してから現在まで、多くの組織再編成の事例の相談や依頼を受けてきており、特に、租税回避に該当するのか否かということに関しては、非常に多くの相談や質問を受けてきました。そして、その租税回避に該当するのか否かということに関して受けた相談や質問に対しては、租税回避に該当すると回答したものが少なくありません。
そのような経験から、本件に関する筆者の印象を述べると、「どう観ても、租税回避にはならないだろう!」というのが正直なところです。
筆者としては、裁判の結果がどうなるのかということもさることながら、そもそも、何故、本件のようなものに法人税法132条の2を適用するということになってしまったのかということが気になっているところです。
TPR事件判決以来、国税当局は、組織再編成の事案において、税務調査で、①税金を減少させようとする旨の記述がある資料が把握され、②組織再編成で事業が引き継がれていないという事実認定が行い得る、ということであれば、法人税法132条の2の適用の要件を満たすとして、同条を適用して課税するという運用を行うようになっているように見受けられます。
このような運用が定着してしまうと、上記の①と②に該当すれば、有無を言わさず租税回避として課税されるということになってしまいます。
筆者は、このような運用の結果が最初に争いとなったのが本件となっていると推測しているところです。
そうであるとすれば、本件は、国税当局がTPR事件判決を用いた形式的かつ硬直的な運用を行っていることに対し、再考を求める非常に重要な事案ということともなります。
最終的に、本件がどのような内容で確定するのかということは、今の時点では、まだ見通せないわけですが(注3)、筆者としては、本件が税に携わる方々の常識に反することのない内容で確定することを願っています。
(注3)上記4(2)②ⅵ(ⅲ)bにおいても述べましたが、国税当局は、本件が敗訴で確定したとしても、TPR事件の合併と同じようなことをしたもの、本件のような事情(法人を買収して合併を繰り返すビジネスモデルに沿って合併をしていたり、買収した法人に簿外債務が存在していたりするなどの事情)がないまま休眠状態となっている法人を吸収合併したものなどに対しては、法人税法132条の2によって未処理欠損金額の引継ぎを否認したり、移転資産の含み損益を計上させたりする可能性が高いと思われます。
このため、納税者としては、本件が納税者の勝訴で確定したとしても、完全支配関係にある法人間の組織再編成が全て租税回避とされなくなったと勘違いしないように、十分、注意する必要があります。
この連載の記事
-
2025.01.09
第1回 はじめに、本件の概要と過去判決の確認
-
2025.01.09
第2回 本件地裁判決の確認と筆者の意見(その1)
-
2025.01.09
第3回 本件地裁判決の確認と筆者の意見(その2)
-
2025.01.09
第4回 本件地裁判決の確認と筆者の意見(その3)
-
2025.01.09
第5回(最終回) 最後に
テーマ
プロフィール

免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。