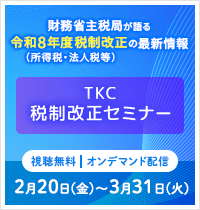更新日 2025.01.09

株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹
令和6年9月27日に、法人税法132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)の適用の可否が争われていたPGMプロパティーズ事件で、東京地裁の判決が下され、納税者側が完全勝訴となりました。この事件は、現在、国側が控訴しており、まだ判決が確定しているわけではありませんが、この事件の判決がどのような内容で確定するのかによって子会社等の組織再編成に影響が出てくるというケースもあると考えられます。
今回は、この事件の判決を取り上げてみます。
当コラムのポイント
- TPR事件の判決を杓子定規に用いるのは適切ではない
- 国税当局は、本件が敗訴で確定したとしても、TPR事件の合併と同じようなことをしたもの、本件のような事情がないまま休眠状態となっている法人を吸収合併したものなどに対しては、租税回避として課税することになる可能性が高いため、十分に注意をする必要がある
- 目次
-
4.本件地裁判決の確認と筆者の意見
(2) 本件地裁判決の第3の3における被合併法人の「事業」と「事業の移転及び継続」に関する判断について
(2)においては、本件地裁判決の第3の3において述べられている被合併法人の「事業」と「事業の移転及び継続」に関する東京地裁の判断がどのような内容となっているのかということについて、まず初めに、①において、概要を確認し、その後に、②において、①で概要を確認した東京地裁の判断について筆者の意見を述べることとします。
① 被合併法人の「事業」と「事業の移転及び継続」に関する東京地裁の判断の概要の確認
本件地裁判決の第3の3においては、次のような判示がなされています。
ⅰ 法人税法57条2項等の規定の本来の趣旨及び目的の確認の必要性((1)、54頁)
本件地裁判決の第3の3(1)においては、本件が不当性要件に該当するか否かは、法人税法57条2項等の規定の本来の趣旨及び目的を踏まえた上で判断する必要があるということを確認しています。
ⅱ 未処理欠損金額の取扱いが基本的に移転資産等の譲渡損益の取扱いに合わせることとされているということの確認((2)、54・55頁)
本件地裁判決の第3の3(2)においては、組織再編税制においては、移転資産に対する支配が組織再編成の後も継続していると認められるものについて、経済実態に実質的な変更がないとして、従前の課税関係を継続させることとするという考え方が採られていることを確認した上で、合併に伴う未処理欠損金額の取扱いについても、基本的に、移転資産等の譲渡損益に係る取扱いに合わせて従前の課税関係を継続させることとするか否かを決めることとされているということを確認しています。
ⅲ 法人課税小委員会報告から、「資産の移転が独立した事業単位で行われること」と「組織再編成後も移転した事業が継続すること」が必要とされたのは、「個別の資産の売買取引と区別する観点」からである、ということの確認((3)、55~57頁)
本件地裁判決の第3の3(3)においては、平成12年10月に政府税制調査会の法人課税小委員会から出された「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」という報告書の記述を引用しながら、次のように、「資産の移転が独立した事業単位で行われること」と「組織再編成後も移転した事業が継続すること」が必要とされたのは、「個別の資産の売買取引と区別する観点」からであると述べています。
「 この点に関し、税制調査会法人課税小委員会(小委員会)が平成12年に組織再編税制について議論した際、組織再編成の前後で経済実態に実質的な変更がない場合には、その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるという組織再編税制の基本的な考え方を基に、経済実態に実質的な変更がないか否かは、移転資産等に対する支配の継続の有無によって判断することとされた上で、資産の移転等を「個別の資産の売買取引と区別する観点」から、「資産の移転が独立した事業単位で行われること」と「組織再編成後も移転した事業が継続すること」を要件とすることが必要とされつつ、「ただし、完全に一体と考えられる持分割合の極めて高い法人間で行う組織再編成については、これらの要件を緩和することも考えられる。」との見解が示されていた(甲5)。このように、小委員会において示された組織再編税制の基本的な考え方は、飽くまで、組織再編成の前後で経済実態に実質的な変更がない場合には、その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるというものであり、この観点から、移転資産等に対する支配が組再編成後も継続しているものについて、譲渡損益の計上を繰り延べるというものであって、「資産の移転が独立した事業単位で行われること」と「組織再編成後も移転した事業が継続すること」が必要とされたのは、「個別の資産の売買取引と区別する観点」からに過ぎない。」(56・57頁)
ⅳ 本件地裁判決の第3の3の(1)から(3)までのまとめとして、組織再編税制の本質(本来の趣旨及び目的)は、組織再編成により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更がない場合に、その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるというものである、ということの確認((4)、57頁)
本件地裁判決の第3の3(4)においては、同3の(1)から(3)までのまとめとして、「組織再編税制の本質(本来の趣旨及び目的)」は、組織再編成により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更がない場合に、その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるというものである、ということを述べており、それが正しいということを示唆するものとして、国税庁が平成21年3月19日付けで回答した「投資法人が共同で事業を営むための合併を行う場合の適格判定について」という文書回答事例を挙げています。
この本件地裁判決の第3の3(4)は、次のとおりとなっています。
「 以上によれば、組織再編税制に係る法人税法57条2項等の趣旨及び目的は、組織再編成により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更がない場合には、その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるというものであり、経済実態に実質的な変更がないか否かを判断するなどのために、法人税法2条12号の8及びこれを受けた法人税法施行令4条の3等において、適格合併と判定するための具体的な要件が定められているものと認められる。
なお、「投資法人が共同で事業を営むための合併を行う場合の適格判定について(照会)」に係る国税庁の見解(甲47、弁論の全趣旨)は、従業員(「員」は原文ママ)引継要件や事業継続要件等が法令上明文で必要とされている共同事業適格合併の該当性の判断につき、形式的にはこれらの要件を満たさない場合であっても、合併の前後で経済実態に実質的な変更が生ずるか否かなどといった観点を踏まえてその該当性を判断するのが相当な事案があることを示唆するものといえる。このことからも、組織再編税制の本質(本来の趣旨及び目的)は、組織再編成により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更がない場合において、その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるという点にあることがうかがわれるというべきである。」(57頁)
ⅴ 国側の主張に対する東京地裁の判断((5)、57~63頁)
本件地裁判決の第3の3(5)においては、国側の主張に対する東京地裁の判断が示されていますが、長文となっていますので、次のように分けて確認をすることとします。
(ⅰ)法人税法57条2項等は被合併法人の事業の移転及び合併後のその事業の継続を前提として未処理欠損金額の引継ぎを認めたものと解するべきであるなどという国側の主張の確認((5)ア、57・58頁)
国側の主張は、法人税法57条2項等は被合併法人の事業の移転及び合併後のその事業の継続を前提として未処理欠損金額の引継ぎを認めたものと解するべきであるなどというものであり、具体的には、次のようなものであるとされています。
「被告は、「移転資産等に対する支配が継続している場合」としては、当該移転資産等の果たす機能の面に着目するならば、被合併法人において当該移転資産等を用いて営んでいた事業が合併法人に移転し、その事業が合併後に合併法人において引き続き営まれることが想定されているなどとして、法人税法57条2項等は、完全支配関係適格合併の場合も含めて、合併による事業の移転及び合併後の事業の継続を前提として被合併法人の有する未処理欠損金額の合併法人への引継ぎを認めたものと解すべきであり、また、被合併法人が「事業」を営んでいたか否かは、特段の事情がない限り、法人税法施行規則3条1項1号の判定基準によるべきであるとして、このような観点から不当性要件の該当性を判断すべきである旨主張する。」(57・58頁)
(ⅱ)上記(ⅰ)で確認した国側の主張に対する東京地裁の判断((5)イ、58~61頁)
本件地裁判決の第3の3(5)イにおいては、上記(ⅰ)において確認した国側の主張に対する東京地裁の判断が示されています。
この東京地裁の判断は、上記(ⅰ)において確認した国側の主張を否定するものであり、要約すると、次のとおりとなっています。
- a 完全支配関係適格合併については事業継続要件等が必要とされていないなど((5)イ(ア)、58頁)
- b 完全支配関係適格合併の場合にも「事業の継続」が一律に適用の前提となっていたということを認めるに足りる的確な証拠はないなど((5)イ(イ)、58・59頁)
- c 「経済実態に実質的な変更があるか否か」という観点からみて、完全子会社の吸収合併の場合には、基本的に、合併の前後で経済実態に実質的な変更がなく、個別の資産の売買取引との区別も問題とならないということができるなど((5)イ(ウ)、59頁)
- d 100%グループ内の合併による事業の移転及び合併後の事業の継続は厳格に考えることはしないとされた旨の筆者(朝長)の意見書等が提出されている((5)イ(エ)、59・60頁)
- e 課税実務上、資産の移転が独立した事業単位で行われておらず合併後に事業が継続していないという理由により法人税法132条の2を適用するという取扱いがされているとはうかがわれない((5)イ(オ)、60頁)
- f 法令上、完全支配関係があり対価要件を満たす法人間の合併の場合に組織再編税制の適用を一律に否定するとの趣旨を読み取ることはできない((5)イ(カ)、60・61頁)
(ⅲ)国側の個々の主張に対する東京地裁の判断((5)ウ、61・62頁)
本件地裁判決の第3の3(5)ウの(ア)から(ウ)までにおいては、国側の主張を個々に取り上げてそれぞれに対する東京地裁の判断が示されています。
この東京地裁の判断も、国側の主張を否定するものであり、要約すると、次のようになります。
- a 完全支配関係がある法人間の合併の場合には合併による事業の移転及び合併後の事業の継続が当然の前提とされているとまでは認め難いなど((5)ウ(ア)、61頁)
- b 組織再編税制の立案担当者(朝長)が完全支配関係適格合併についても一律に「事業の継続」を前提とする説明をしたとは認められないなど((5)ウ(イ)、61頁)
- c 国側が挙げる最高裁昭和43年判決は、「事業の継続」を基準としたものではない((5)ウ(ウ)、61・62頁)
(ⅳ)東京地裁の判断内容のまとめ((5)エ、62頁)
本件地裁判決の第3の3(5)エにおいては、「法令上に明記されていない一律の「前提」(事実上の要件)を明確な根拠もなく想定すべきではない」というように、国側の「事業の継続」が前提となるという主張に対する東京地裁の判断のまとめと言ってよいことが述べられています。
(ⅴ)上記(ⅰ)で確認した国側の主張には理由がないということ((5)オ、62・63頁)
本件地裁判決の第3の3(5)オにおいては、完全支配関係適格合併の場合において、「合併による事業の移転及び合併後の事業の継続」が法人税法57条2項等の適用の「前提」となっているとか、「合併による事業の移転及び合併後の事業の継続」がない完全支配関係適格合併に上記規定を適用することはその本来の趣旨及び目的に反するとか等と解することはできず、上記(ⅰ)の国側の主張には理由がない、という判断が示されています。
② 上記①で概要を確認した本件地裁判決の判断に関する筆者の意見
②においては、上記①で概要を確認した本件地裁判決の判断に関する筆者の意見を述べることとします。
ⅰ 上記①のⅰからⅲまでで確認した本件地裁判決の判示について
上記①のⅰからⅲまでにおいて確認した本件地裁判決の第3の3の(1)から(3)までにおいて述べられていることは、いずれも正確であって、これらの判示に関して筆者が追加して意見を述べるようなことをする必要はないように思われます。
もし、敢えて何か意見を言うとすれば、それは、大きな税制改正を行った場合には、その立法に携わった者は、本件地裁判決で繰り返し引用されている『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』などのように、その改正の背景、経緯、趣旨・目的などを詳しく確認することができるものを残すようにしてもらいたい、ということくらいです。
ヤフー事件・IDCF事件、TPR事件においては、『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』の記述が重要な証拠として提出され、裁判所の判断に大きな影響を与えました。この書籍は、翌年に連結納税制度の創設を控えた中で、相当に無理をして執筆と編集を行ったものであり、今にして思うと、もう少し詳しく書いておけばよかったと思うところも所々にありますが、当時は、これが精一杯というのが実情でした。このように、この書籍は、時間と労力に非常に厳しい制約があったために、十分と言い得るまでのものとすることはできませんでしたが、仮に、この書籍を残していなかったとしたら、これらの事件において、組織再編成税制の条文について、創設時に予定していた解釈とは全く異なる解釈がなされてしまい、裁判所の判断も大きく異なるものとなっていたのではないかと思われます。
勿論、この書籍に書かれていることで組織再編成に関する税制の取扱いの判断をしたという声やこの書籍を読んで組織再編成税制を学んだという声は、多くの方々から何度も聞いてきました。
このような事情にありますので、この書籍は、一応、執筆時に考えていた最低限の役割は果たすことができていると考えています。
ⅱ 上記①ⅳで確認した本件地裁判決の判示について
上記①ⅳにおいて確認した本件地裁判決の第3の3(4)は、同3の(1)から(3)までのまとめとなっていますので、このまとめの部分に関しては、筆者の意見を述べる必要はないと考えています。
ただし、上記①ⅳにおいて確認したとおり、本件地裁判決の第3の3(4)においては、同3の(1)から(3)までのまとめの部分の後に、なお書きで、「投資法人が共同で事業を営むための合併を行う場合の適格判定について(照会)」における国税庁の回答を根拠とした判示がなされています。
このため、以下、ⅱにおいては、この照会と回答について説明を行っておくこととします。
国税庁は、平成21年3月19日に、金融庁からの「投資法人が共同で事業を営むための合併を行う場合の適格判定について」という照会に対し、「貴見のとおりで差し支えありません」という回答を行い、ホームページで公開しています。
この照会は、適格合併となる合併の三つの形態(100%グループ内の合併、50%超100%未満のグループ内の合併及び共同事業を営むための合併)のうち、最も厳格に要件を定めている共同事業を営むための合併に関して尋ねるものであって、法人税法2条12号の8ハ及びその委任政令である法人税法施行令4条の3(照会当時は同令4条の2)4項各号(適格合併の事業関連性要件等)の趣旨目的を確認するものともなっているため、組織再編成税制が適格合併に関して「事業」をどのように捉えているのかということを詳しく知ることができるものとなっています。
この照会においては、次のように述べられています。
「投資法人は、投信法において、一般事務を一般事務受託者に、その資産の運用に係る業務を資産運用会社に、その資産の保管に係る業務を資産保管会社に、それぞれ委託しなければならないこととされています・・・このように実質的に投資法人は導管体であり、このような導管体には『事業』の実態がないものとみとめられるため、投資法人間の合併において事業関連性要件を満たすことはできないのではないかとも考えられます。」(「3 照会者の求める見解となることの理由」の「(1)照会事項(1)について(事業関連性要件)」参照)
そして、投資法人は、確かに、このように「「事業」の実態がないものとみとめられる」という状態にあるとしても、次に引用するとおり、「委託先との委託契約を通じて投資法人が自らの「事業」を行っているものと認められ」、「不動産を合併後において有機一体的に活用して引き続き不動産投資事業を行うことが見込まれている」ということから、照会者は、投資法人の合併は事業関連性要件を満たすものと解されるとしています。
「これらの委託先との委託契約を通じて投資法人が自らの「事業」を行っているものと認められます。
したがって、本件合併においては、X社とY社の投資対象がいずれも不動産であることから両社の営む事業は同一の事業と認められ、また照会事項のとおり、X社とY社のそれぞれが有していた不動産を合併後において有機一体的に活用して引き続き不動産投資事業を行うことが見込まれていることからすれば、本件合併は事業関連性要件を満たす」(同前)
投資法人は、全ての業務を他の者に委託している状態にあり、「導管体」であるため、投資法人は「事業」を行っていると言い得るのか否かということが問題となるわけです。
この照会回答においては、投資法人が「事業」と言い得るものを行っているのか否かということに関しては、やや曖昧さを残しつつも、合併の前後で経済実態に実質的な変更がないということを理由として、事業関連性要件を満たしていると判断してよいかという照会を行っているものに対し、国税庁が貴見のとおりで差し支えないと回答しています。
また、この照会においては、次のような記述もなされています。
「投資法人には業務に従事する者が存在しないことから、従業者引継要件を満たすことができず、共同事業要件を満たすことはできないのではないかとの疑義が生じるかもしれません。」(「3 照会者の求める見解となることの理由」の「(3)照会事項(3)について(従業者引継要件)」参照)
そして、照会者は、このような「疑義」に対しては、「合併前の状態は合併後においても継続している」とした上で、「従業者引継要件を充足しないものとして共同事業要件を満たさないものとすることは、上記の従業者引継要件が設けられた趣旨に沿わないものともなりかねません」と述べて、投資法人間の合併は従業者引継要件を充足しているとしています。
この「上記の従業者引継要件が設けられた趣旨」については、次のように、適格合併は「合併の前後で経済実態に実質的な変更が生じない合併」でなければならないという旨の説明が行われています。
「そもそも従業者引継要件は、被合併法人の従業者が引き継がれない合併は合併前の状態が継続しているとは言えず、適格合併の対象となる合併の前後で経済実態に実質的な変更が生じない合併に該当しないと考えられるため、このような合併であるか否かを判定するための要件として設けられているものと考えられます。」(同前)
このような内容の照会に対して、国税庁が「貴見のとおりで差し支えありません」という回答をしているということは、組織再編成税制における「事業」に関し、事業を行っていると言い得るのか否かということに争いがあるというような限界事例について、適格組織再編成の規定の趣旨目的に反することになるのか否かということを判断するという場合には、組織再編成の前後で経済実態に実質的な変更がないと言い得るのか否かということに戻って判断をするべきであるとしていると解してよいはずです。
つまり、組織再編成税制における「事業」について、非常に柔軟に捉えているということです。
なお、この照会回答については、筆者が平成20年5月26日に外資系大手税理士法人の代表者から質問を受けたものについて、筆者がこの照会の中にある記述と同様の回答を行うとともに、監督官庁から国税庁に対して文書照会を行って回答をもらうようにすることを提案し、金融庁から国税庁に対して文書照会がなされ、国税庁から「貴見のとおりで差し支えありません」という回答があったものである、ということを申し添えておきます。
ⅲ 上記①ⅴ(ⅱ)で確認した本件地裁判決の判断について
上記①ⅴ(ⅰ)においては、法人税法57条2項等は被合併法人の事業の移転及び合併後のその事業の継続を前提として未処理欠損金額の引継ぎを認めたものと解するべきであるなどという国側の主張の確認を行っています。
本コラムは、本件地裁判決を確認し、本件地裁判決に対して筆者の意見を述べるものですから、上記①ⅴ(ⅰ)において確認した本件地裁判決の第3の3(5)アの国側の主張に対しては、ここで筆者の意見を述べることはしないこととします。
次の(ⅰ)から(ⅵ)までにおいては、上記①のⅴ(ⅱ)のaからfまでにおいて概要を確認した本件地裁判決の第3の3(5)イの(ア)から(カ)までの判断を具体的に確認した上で、そのそれぞれについて筆者の意見を述べることとします。
(ⅰ)上記①ⅴ(ⅱ)のaの判断について
本件地裁判決の第3の3(5)イ(ア)においては、次のような判断が示されています。
「法人税法及びこれを受けた法人税法施行令の規定上、支配関係適格合併及び共同事業適格合併においては、従業者引継要件及び事業継続要件等が必要とされているのに対し、完全支配関係適格合併については、これら従業者引継要件及び事業継続要件等のいずれについても必要とされていない。また、法57条2項等の規定をみても、完全支配関係のある法人間の合併について、事業の継続がない場合には一律に適用がない旨をうかがわせる文言はない。」(58頁)
この判断は、事実に基づく正確なものとなっており、誰も異論はないはずです。
もっとも、上記2のⅲで確認したとおり、ヤフー事件最高裁判決においては、「組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的」を用いて判断をするものとされていますので、本件においても、法人税法2条12号の8イ等の「本来の趣旨及び目的」がどのようなものであるのかということを確認し、その確認したものを用いて判断をするということが必要となります。
法令の条文の趣旨や目的をどのようにして確認するのかということについて、内閣法制局長官を長く勤められていた林修三氏は、次のように述べておられます(次の引用部分には続きがあり、その続きを後掲ⅵ(ⅲ)で引用していますので、その引用も参照してください。)。
「立法の目的、趣旨が何かということを解明するにあたっては、立法当時の立法者の考え方をつかむことが主になるべきことはいうまでもない」(林修三『法令解釈の常識』、日本評論社、105頁、2004年12月)
改めて言うまでもないことですが、法令の条文の趣旨や目的は、条文の文言として示されているものではありませんので、条文の文言をいくら読んでも正確なことは分からず、このように、条文の創設等の時の文献などによって確認するしかありません。
このため、上記の判断についても、法人税法2条12号の8イ等の「本来の趣旨及び目的」について、「立法当時の立法者の考え方をつかむこと」によって確認をすることを想定したものと考えられることに留意する必要があります。
現に、本件地裁判決においても、さまざまなところで、繰り返し、組織再編成税制の立法当時(平成13年当時)の文献を引用して判断を示しています。
(ⅱ)上記①ⅴ(ⅱ)のbの判断について
本件地裁判決の第3の3(5)イ(イ)においては、次のような判断が示されています。
「支配関係適格合併や共同事業適格合併の要件よりも緩和された完全支配関係適格合併の要件が定められたと解するのが自然である。また、組織再編税制の立法の過程において、完全支配関係適格合併の場合にも「事業の継続」が一律に適用の前提となっていたことを認めるに足りる的確な証拠はない。」(59頁)
この判断の前半の部分は、上記①ⅲにおける引用から分かるとおり、平成12年10月に政府税制調査会の法人課税小委員会から出された「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」という報告書の記述にある「ただし、完全に一体と考えられる持分割合の極めて高い法人間で行う組織再編成については、これらの要件を緩和することも考えられる。」という記述を根拠としたものです。
この報告書の「これらの要件を緩和することも考えられる」という部分については、「緩和」という用語は、「緩くする」や「和らげる」ということを意味するものであって、「無い」ということを意味するものではないということに留意する必要があります。
この報告書の「ただし」以下の文章は、それを書くのか否かということを含めて慎重に検討を行った上で、「・・・緩和することも考えられる」という表現となったものです。
つまり、「完全に一体と考えられる持分割合の極めて高い法人間で行う組織再編成」においても、規定という形で設けるということまではされなかったものの、緩くしたり和らげたりした「これらの要件」は「有る」ということです(その後、この緩くしたり和らげたりしたものが平成22年度税制改正によって「有る」とは言い難い状態となっていることについては、後掲ⅵ(ⅲ)を参照のこと)。
また、上記の判断の後半の部分は、国側が完全支配関係がある法人間の合併の場合は合併による事業の移転及び合併後の事業の継続が当然の前提とされていると主張していることに対する東京地裁の判断を示した部分ということになりますが、ここで用いられている「前提」という用語についても、その意味内容を正しく理解しておく必要があります。
もっとも、この意見に関しては、本来は、先に意見書等で国側に対して言うべきことであったようにも感じています。
この「前提」という用語について、インターネットで確認してみると、Weblio辞書に「実用日本語表現辞典」からの引用として、次のような記述がなされています。
「前提(ぜんてい)とは、何かを考える、行動する、判断する際に、基礎となる考え方や条件を指す言葉である。前提は、一般的には明示されず、暗黙のうちに受け入れられていることが多い。また、前提は、議論や論理の基盤となり、それに基づいて結論が導かれる。例えば、「全ての人は平等である」という前提のもと、法律が制定されることがある。しかし、前提は必ずしも真実であるとは限らず、時と場合によって変わることもある。」
この「実用日本語表現辞典」というものは、書籍として存在するものではないようですので、厳密にいえば、その信頼性に疑問なしとはしませんが、上記の記述自体は、正しいと評価してよい内容となっていると考えられます。
ところで、国側が合併による事業の移転及び合併後の事業の継続が「前提」であると主張する理由は、法人税法2条12号の8イ等の規定の立法時にそれらの条文が合併による事業の移転及び合併後の事業の継続を「前提」として設けられたためであるという理解に基づくものとなっていますので、税法の条文がどのようにして設けられるのかということを簡単に確認してから、「前提」の話に戻ることとします。
税法の条文を設ける場合にも、その条文がどのようなものに適用されるのかということを想定しながら設けることとなり、その想定するものとは、通常、「典型例」と言われるものとなります。改めて言うまでもないことですが、立法を行う者も、森羅万象を知悉していて万能であるなどということはありませんので、全ての事例にそのまま適用して何の問題も生じない完璧な条文を設けるなどということはできません。
このため、「典型例」に適用することを想定して設けられた条文を「限界事例」などと言われるものに適用するというようなことになった場合には、その条文をその文言どおりにそのまま用いて文理解釈をしたり、その考え方や趣旨目的などを解説等の記述どおりにそのまま用いて趣旨解釈をしたりするということになると、その解釈に基づく取扱いが実態に合わないものとなってしまうというようなことが起こってきます。
本件地裁判決の第3の3(3)に、資産の移転等を「個別の資産の売買取引と区別する観点」から「資産の移転が独立した事業単位で行われること」と「組織再編成後も移転した事業が継続すること」が必要とされたという旨の記述(上記①ⅲ参照)があることからも分かるとおり、法人税法2条12号の8イの完全支配関係法人間の適格合併に関する定めは、適格合併においては、「資産の移転が独立した事業単位で行われる」ということになり、また、「組織再編成後も移転した事業が継続する」ということになるものと想定して設けられました。
このため、「典型例」である合併について、「資産の移転が独立した事業単位で行われること」と「組織再編成後も移転した事業が継続すること」が必要とされると主張することには、何ら問題がなく、その主張は正しい主張ということになります。
しかし、「限界事例」である合併については、事情が異なります。
「限界事例」である合併の場合には、その「限界」の内容次第で、「資産の移転が独立した事業単位で行われること」と「組織再編成後も移転した事業が継続すること」が必要とされると主張してよいということもあり、その二つの内容を修正したものが必要とされると主張しなければならないということもあり、その二つの内の一つだけが必要とされると主張しなければならないということもあり、また、その二つのいずれも必要と主張してはならないということもある、ということになります。
後にⅳ(ⅱ)で述べる非常に分かり易いパン屋さんと肉屋さんの例で言えば、オーブンが一個しかないことから、パン屋さんがオーブンをもって分割して出て行った後の肉屋さんについては、事業に必須の資産がないという状態となりますので、そのオーブンがない状態の肉屋さんの合併について、上記の二つの内の「資産の移転が独立した事業単位で行われること」が要求されるという主張を行って非適格であるとするのは適当ではない、ということになります。
上記の「前提」の説明の中の最後には、「時と場合によって変わることもある」とされていますが、この説明に倣って言えば、上記の「資産の移転が独立した事業単位で行われること」と「組織再編成後も移転した事業が継続すること」も、「時」と「場合」などによって、変えなければならないことがある、ということになります。
つまり、「資産の移転が独立した事業単位で行われること」と「組織再編成後も移転した事業が継続すること」という「前提」は、完全支配関係法人間の適格合併の全てに対して常に一律に必要とされると考えてはならない、ということです。
上記の判示の後半の「「事業の継続」が一律に適用の前提となっていたこと」を否定する部分も、「前提」が「時」と「場合」などによって変えなければならないものであるということを正しく認識して読むと、「事業の継続」が前提であることを否定しているものではなく、「事業の継続」を求めることが一律であることを否定しているものであることが分かります。
また、本件地裁判決の第3の3(5)イ(イ)には、次のような判断も示されています。
「 そして、企業グループにおいて、完全子会社の事業継続が困難となった場合に、当該完全子会社を解散し清算するという方法は手続が煩雑であることなどから、親会社が当該完全子会社を吸収合併した上で、継続困難となった当該事業を廃止するということは一般的にみられ、中には完全子会社である休眠会社を吸収合併するような合併の事例もあることからすると(弁論の全趣旨)、組織再編税制の議論に当たり、これらの事例が容易に想定し難いものであったとはいえない。」(59頁)
この判断は、平成13年度税制改正で組織再編成税制が創設された際の「組織再編税制の議論」に関するものとなっています。
確かに、組織再編成税制の創設に際しては、この判断に書かれているような検討も行いました。
しかし、組織再編成税制の創設に際して、そのような検討を行ったということ、そのような検討の内容や結論がどのようなものであったのかということなどを確認してもらうことができるものは、残念ながら、残していません。
このため、この判断に関して筆者の意見を述べることは、控えたいと思います。
(ⅲ)上記①ⅴ(ⅱ)のcの判断について
本件地裁判決の第3の3(5)イ(ウ)においては、次のような判断が示されています。
「小委員会で示された組織再編税制の基本的な考え方(前記(2))である「経済実態に実質的な変更があるか否か」という観点からみると、前記(イ)のような完全子会社の吸収合併の場合において、合併対価要件を満たすときは、基本的に、従業員(「員」は原文ママ)引継要件及び事業継続要件を問うまでもなく、合併の前後で経済実態に実質的な変更がなく、個別の資産の売買取引との区別も問題とならないということができる。」(59頁)
この判断に関しては、「基本的に」という文言が用いられていることに留意する必要があります。
つまり、この判断は、「基本的に」という文言が用いられているため、「完全子会社の吸収合併の場合において、合併対価要件を満たすとき」の全てについて、「従業者引継要件及び事業継続要件を問うまでもなく、合併の前後で経済実態に実質的な変更がなく、個別の資産の売買取引との区別も問題とならない」と述べているものではないということです。
(ⅳ)上記①ⅴ(ⅱ)のdの判断について
本件地裁判決の第3の3(5)イ(エ)においては、次のような判断が示されています。
「 現に、平成13年度税制改正により組織再編税制が導入された際に大蔵省(財務省)主税局課長補佐として立法作業に関与した朝長税理士は、本件訴訟において、組織再編制(「制」は原文ママ)の前後で経済実態に実質的な変更がない場合には課税関係を継続させるというのが組織再編税制の最も基本的な考え方であり、我が国の企業グループが組織再編成を柔軟に行えるようにすることや完全支配関係にある法人間の関係の実態は完全に一体の関係という状況にあると考えられることもできることなどを考慮して、完全支配関係にある法人間の合併については、あえて従業者引継要件及び事業継続要件を設ける必要はないという判断により、これらの要件が設けられなかったものであって、100%グループ内の合併において、合併による事業の移転及び合併後の事業の継続は厳格に考えることはしないとされた旨の意見書等を提出している(甲45、61、62、66)。朝長税理士の上記見解は、組織再編税制の基本的な考え方(前記(2))と整合し、合理的なものということができる。」(59・60頁)
この判断に関しては、「合併による事業の移転及び合併後の事業の継続は厳格に考えることはしないとされた」というところが非常に重要な部分ということになります。
筆者は、本件において提出した意見書において「合併による事業の移転及び合併後の事業の継続は厳格に考えることはしないとされた」ということを裏付ける証拠として、『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』の23頁の写しを提出しており、そこに書かれていることは、次のとおりとなっています(下線は、意見書において同23頁を引用する際に筆者が付したものです。)。
「 例えば,ヨーロッパの例などをみると,個別の資産の売買との区分をどうするかという観点を中心にして税制を創っているように思われます。このような方向からアプローチすると,独立事業要件(独立事業単位要件と言ったほうが正確かもしれませんが)が非常に重要となってくるわけです。独立事業要件を中心に据えて,個別資産の移転ではなく,事業を丸ごと移すというケースについて,課税特例を適用するということになるわけです。わが国の商法においても,会社分割は,営業単位の移転でなければならないことになっていますので,こういった観点は,わが国における税制を考えるうえでも重要なものであることは間違いありません。今回のわが国の税制改正においても,当然,こういった観点は考慮しています。
他方,こういった観点だけで課税関係を判定するということになると,資産を個別に売買する場合には課税は繰り延べないが,資産をまとめて売買すれば課税を繰り延べるということになってしまうおそれがあります。これもまた,おかしな話です。また,前回もお話しましたが,例えば,パン屋さんと肉屋さんの両方の事業をやっている会社があって,一個のオーブンでパンを焼くのにも,肉を焼くのにも使っているとすれば,オーブンをそれぞれの事業に分けることができないことから,そもそも,課税特例の適用を受ける会社分割ができないということにもなるわけです。この譬喩は,ドイツの課税当局者が述べたものをお話しさせていただいているものです。ドイツの詳しい事情は良くわかりませんが,独立事業要件を厳格に考えるということになると,柔軟な組織再編成に対応できない非常に窮屈な制度になるおそれがあるように思われます。こういった点から,独立事業要件を中心にして制度を考える考え方には,非常に参考になる部分があるものの,他方で,反面教師となる部分もあるように思います。」(『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』23頁)
この引用部分において、「独立事業要件を厳格に考えるということになると,柔軟な組織再編成に対応できない非常に窮屈な制度になるおそれがある」と記述していることからも分かるとおり、資産の移転が独立した事業単位で行われて組織再編成後も移転した事業が継続することについては、「厳格に考える」ということはしないこととされたわけです。
この引用部分にある「厳格に考える」ということをもう少し具体的に上記の引用部分の例を用いて説明すると、パン屋さんと肉屋さんの両方の事業を行っている会社があって,一個のオーブンでパンを焼くのにも肉を焼くのにも使っている場合には、二つに分けると、一方は、必ず、事業を行い得ない状態で分かれるということになるため、課税の特例の対象とはならない、ということです。この引用部分では、そのようなことになるのは適当ではなく、オーブンが一個しかなかったとしても、パン屋さんと肉屋さんを分ける場合には、課税の特例の対象とするのが適当である、と言いたいわけです。つまり、オーブンが無くて事業を分けることになった場合には、分けた先にオーブンが有るか又は分けた先がオーブンを購入するはずであるから、オーブンが無くて一方が事業を行い得ない状態で二つに分けたとしても、「事業」や「事業の移転及び継続」を「厳格に考える」ということとはせずに、課税の特例の対象とすることにするべきである、ということです。この引用部分のパン屋さんと肉屋さんの例は、我が国の組織再編成税制が「事業」や「事業の移転及び継続」について「厳格に考える」ということとはしていないことを確認することができるものとなっています。
このように、資産の移転が独立した事業単位で行われて組織再編成後も移転した事業が継続することについて、「厳格に考える」ということはしないこととされた(言い換えると、「柔軟に考えることとされた」)ということは、組織再編成税制の創設当時の文献から、明確かつ具体的に確認することができるわけです。
(ⅴ)上記①ⅴ(ⅱ)のeの判断について
本件地裁判決の第3の3(5)イ(オ)においては、次のような判断が示されています。
「 しかも、完全子会社の事業継続が困難となり、親会社が当該完全子会社を吸収合併した上で、継続困難となった当該事業を取り止めるというような事案において、課税実務上、資産の移転が独立した事業単位で行われておらず、合併後に事業が継続していないという理由により、法人税法132条の2に基づき親会社の行為又は計算を否認するとの取扱いがされていることはうかがわれない(弁論の全趣旨)。」(60頁)
この判断の「・・・を否認するとの取扱いがされていることはうかがわれない」という記述は、課税実務の状況を正しく示していると言ってよいはずです。
もっとも、国側は、この判断の中に書かれている「事案」に問題があるということが分かったのはTPR事件があったためであり、その後は、この判断の中に書かれている「事案」のようなものについて、厳しく見るようにしている、という旨の反論をすることになるものと思われます。
(ⅵ)上記①ⅴ(ⅱ)のfの判断について
本件地裁判決の第3の3(5)イ(カ)においては、次のような判断が示されています。
「 これらの事情によれば、組織再編税制の立法に当たっては、小委員会の前記(イ)の見解も踏まえた上で、前記(イ)のような完全子会社の吸収合併の場合も含め、完全支配関係があり対価要件を満たす法人間の合併の場合には、基本的に、合併の前後で経済実態に実質的な変更がなく、個別の資産の売買取引との区別も問題とならないことから、支配関係適格合併及び共同事業適格合併とは異なる、より緩和された適格合併の要件があえて定められ、従業員(「員」は原文ママ)引継要件及び事業継続要件が必要とされなかったと解するのが相当であって、法令上、上記のような合併の場合に組織再編税制の適用を一律に否定するとの趣旨を読み取ることはできない。」(60・61頁)
この判断は、本件地裁判決の第3の3(5)イの(ア)から(オ)までの判断をまとめたものとなっています。
本件地裁判決の第3の3(5)イの(ア)から(オ)までの判断に関する筆者の意見は、既に上記(ⅰ)から(ⅴ)までにおいて述べてきましたので、改めて意見を述べる必要はないと考えています。
ⅳ 上記①ⅴ(ⅲ)で確認した本件地裁判決の判断について
ⅳにおいては、上記①のⅴ(ⅲ)において確認した本件地裁判決の第3の3(5)ウの(ア)から(ウ)までの判断(国側の個々の主張に対する東京地裁の判断)について、それぞれ筆者の意見を述べることとします。
(ⅰ)上記①ⅴ(ⅲ)のaの判断について
本件地裁判決の第3の3(5)ウ(ア)は、次のとおりとなっています。
「 以上の点につき、被告は、完全支配関係がある法人間の合併の場合は合併による事業の移転及び合併後の事業の継続が当然の前提とされていることから、これを担保する事業継続要件等の要件をあえて設ける必要はないものと考えられるなどと主張するが、前記イ(イ)で述べた完全子会社に係る合併の実情からすると、完全支配関係がある法人間の合併の場合には合併による事業の移転及び合併後の事業の継続が当然の前提とされているとまでは認め難い。加えて、前記イで説示したところに照らすと、被告の上記主張は、にわかに採用することができない。」(61頁)
上記の判断の中の「前記イ(イ)で述べた完全子会社に係る合併の実情」とは、上記ⅲ(ⅱ)の最後で引用した本件地裁判決の第3の3(5)イ(イ)の「そして」以下の事例が現実にあるということをいうものです。
つまり、上記の判断は、本件地裁判決の第3の3(5)イ(イ)の「そして」以下の事例が現実に存在することを根拠として、「完全支配関係がある法人間の合併の場合には合併による事業の移転及び合併後の事業の継続が当然の前提とされているとまでは認め難い」としているわけです。
上記の判断の中のこの記述については、上記ⅲ(ⅴ)においても述べましたが、国側は、この判断の中に書かれている「事案」や「事例」に問題があるということが分かったのはTPR事件があったためであり、その後は、この判断の中に書かれている「事案」や「事例」のようなものについて、厳しく見るようにしている、という旨の反論をすることになるものと思われます。
なお、上記の判断の「加えて」の後にある「前記イで説示したところ」とは、上記ⅲの(ⅰ)から(ⅵ)までにおいて引用した本件地裁判決の第3の3(5)イの(ア)から(カ)までに示された東京地裁の判断のことです。
(ⅱ)上記①ⅴ(ⅲ)のbの判断について
本件地裁判決の第3の3(5)ウ(イ)においては、次のような判断が示されています。
「被告は、組織再編税制の立案担当者(朝長税理士)は、適格合併等の判定に係るいわゆる従業者引継要件について説明をする際、従前の課税関係を継続させる適格組織再編成は、組織再編成前に行われていた事業が組織再編成後も継続されることを前提とする説明をしている(乙68)旨主張するが、上記説明は、従業員(「員」は原文ママ)引継要件が「要件の一つ」となっている場合、すなわち、支配関係適格合併及び共同事業適格合併を念頭にされたものであることがその文脈上明らかであるし、適格組織再編成として従前の課税関係を継続されるものにつき、「基本的には」独立した事業単位が移転をするものと考えられている旨説明していることからすると(乙68)、上記説明をもって、組織再編税制の立案担当者(朝長税理士)が完全支配関係適格合併についても一律に「事業の継続」を前提とする説明をしたとは認められない。」(61頁)
上記の判断の中の筆者の「説明」とは、『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』の中の「従業者の引継ぎ要件」に関する質問に対する回答にある「適格組織再編成として従前の課税関係を継続させるものは、基本的には、独立した事業単位が移転をするものと考えられています。」(89頁)という部分です。
この部分に関しては、上記の判断に書かれているように、「完全支配関係適格合併についても一律に「事業の継続」を前提とする説明をした」というものではありません(この質問文に「旧会社の従業員が出向の形態で新会社における業務に従事する場合であっても・・・」とあることから分かるとおり、この質問と回答は、分割と現物出資及び事後設立の中の従業者引継要件があるものを対象としたものですが、上記の引用部分自体は、基本的には、合併にも当てはまると考えてよいものです。)。
仮に、合併は「基本的には、独立した事業単位が移転するもの」となっているか否かと質問したとすれば、誰もが「そうなっている」と答えるはずですし、適格合併に関する規定を設けるに当たっても、「独立した事業単位が移転するもの」を合併と想定して設けることとなるのは、当然のことです。
そして、仮に、上記ⅲ(ⅳ)で例に挙げたパン屋さんと肉屋さんのケースで、パン屋さんにオーブンを持たせて分割し、残った肉屋さんがオーブンを持った他の法人に吸収合併されたとすれば、この肉屋さんは、オーブンがないことから事業を行うということ自体ができないため、「独立した事業単位」ということにはなり得ず、「独立した事業単位が移転するもの」ともなり得ませんが、我が国の組織再編成税制においては、そのような肉屋さんの合併について非適格合併とするという考え方を採っていないということは、上記ⅲ(ⅳ)でも述べたとおりです。
要するに、適格合併は、「基本的には」、独立した事業単位が移転するものとされているが、「一律に」、独立した事業単位が移転するものでなければならないとされているわけではない、ということです。
そして、完全支配関係法人間の適格合併と支配関係法人間の適格合併及び共同事業を行うための適格合併とで、事業継続要件の用い方に関して、何が違うのかというと、前者においては、要件として規定が設けられていないわけですから、租税回避が疑われるもの(ヤフー事件最高裁判決の文言を用いると「組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したもの」ということになります。以下、同じです。)についてのみ、適格合併の定義規定である法人税法2条12号の8イの規定の本来の趣旨及び目的として合併前の事業が継続しているのか否かということを問うことで済み、一方、後者においては、要件として規定が設けられているわけですから、合併前の事業が継続しているのか否かということを全てについて常に問わなければならない、というところが違うということになります。
また、上記ⅲ(ⅱ)で述べたとおり、完全支配関係法人間の適格合併と支配関係法人間の適格合併及び共同事業を行うための適格合併とでは、事業継続要件の内容に関して、前者は、後者よりも、緩くしたり和らげたりしたものとなっているという違いがあることにも留意する必要があります(その後、この緩くしたり和らげたりしたものが平成22年度税制改正によって「有る」とは言い難い状態となっていることについては、後掲ⅵの(ⅲ)aを参照のこと)。
この「緩くしたり和らげたりしたもの」がどのようなものかということは、個別の事案ごとに判断をすることとなります。具体例を挙げて説明すると、上記のオーブンを持たない肉屋さんの合併の例は事業継続要件の規定があるものの例と考えてよいものであり、上記ⅱで述べた投資法人の合併の例も実際に事業継続要件の規定があるものの事業継続の例となっていることから、この「緩くしたり和らげたりしたもの」は、これらの例よりも緩くしたり和らげたりして事業継続の有無を捉えることとなる、ということです。
このような事情にあることを踏まえて、TPR事件の合併がどのようなものとなっているのかということを確認してみると、TPR事件の合併は、事業継続要件の規定がない完全支配関係法人間の合併ですから、事業が継続しているのか否かということについて、緩くしたり和らげたりして判断することとはなりますが、それであっても、合併前に行っていた被合併法人の事業が合併法人に引き継がれていないことは明白です。このため、そのようなものは、適格合併の本来の趣旨及び目的から逸脱するものということにならざるを得ません。
要するに、完全支配関係法人間の合併において事業が継続していないことを理由として適格合併の本来の趣旨及び目的から逸脱すると判断されるものについて、具体例でイメージをするということになると、上記のオーブンを持たない肉屋さんの合併の例及び上記ⅱで述べた投資法人の合併の例とTPR事件の合併の例との間の線を基準として、TPR事件の合併の例に近い側のものとイメージをしてよい、ということです。
以上のような事業継続要件の用い方と事業継続要件の内容の違いは、規定という明確な形にして事業継続要件を定めたものとそうでないものとの当然の違い、ということでもあります。
このような説明でもまだよくイメージが湧かないという場合には、税に携わる方々の常識で判断していただくということでもよいと考えています。
組織再編成税制も、税に携わる方々の常識を念頭に置きながら創った制度ですから、「そんなことは、普通はやらないだろう!」というものを優遇の対象に含める仕組みを設けるなどということは、あり得ません。
つまり、上記のオーブンを持たない肉屋さんの合併と上記ⅱで述べた投資法人の合併は、いずれも「同じ立場になれば、誰でも同じことをするだろう!」というものであるのに対し、TPR事件における合併は、「そんなことは、普通はやらないだろう!」というものである、ということです。
現に、TPR事件に関しては、税理士や弁護士の方々から、そのような話を何度か聞いたことがあります。
これに対し、本件に関しては、「ビジネスモデルがそうなっており、簿外債務があったのであれば、そうするのは、当然でしょう!」という話や「三社合併について、順番を付ければそのとおりにやってよいと国税庁自身が言っているのだから、租税回避になるということは、あり得ない」という話などを税理士や弁護士の方々から何度かされたことがあります。
要するに、本件は、「同じ立場になれば、誰でも同じことをするだろう!」というものであるということです。
(ⅲ)上記①ⅴ(ⅲ)のcの判断について
本件地裁判決の第3の3(5)ウ(ウ)は、次のようなものとなっています。
「 さらに、被告は、最高裁昭和43年判決を引用しつつ、法人税法57条1項による欠損金額の繰越控除は、事業の継続に着目して認められたものであり、同条2項が同条1項の考え方を前提に新たに規定されたものであるとも主張するが、最高裁昭和43年判決は、欠損金額の繰越控除は、「経理方法に一貫した同一性が継続維持されること」を前提として認められるものであり、合併会社に被合併会社の経理関係全体がそのまま継続するものとは考えられないものについては認められない旨を判示したものであり、「事業の継続」を基準としたものではない。被告の上記主張は、最高裁昭和43年判決あるいは法人税法57条1項の趣旨を正解しないものであり、採用できない。」(61・62頁)
上記の判断は、的確であり、筆者が意見を述べる必要はないと考えています。
ⅴ 上記①ⅴ(ⅳ)で確認した本件地裁判決の判断について
本件地裁判決の第3の3(5)エは、次のようなものとなっています。
「 確かに、休眠会社を利用した組織再編成によって不当な租税回避行為が行われるおそれは否定できないが、不当性要件の該当性の判断、すなわち、法人の行為又は計算が組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであるか否かの判断は、飽くまで、組織再編成に係る個別的な事情を踏まえ、①当該法人の行為又は計算が、通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で、当該行為又は計算が、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から行うのが相当であり(前記2(1))、かつ、それで足りるというべきであって、法令上に明記されていない一律の「前提」(事実上の要件)を明確な根拠もなく想定すべきではない。」(62頁)
上記の判断は、冒頭で、「確かに、休眠会社を利用した組織再編成によって不当な租税回避行為が行われるおそれは否定できないが、」としていますが、この部分がなかったとしても、文章としては、何の問題もないものとなっています。東京地裁が上記の判断の中にこの部分を入れた理由が何かということを考えてみると、仮に、東京地裁が「休眠会社を利用した組織再編成によって不当な租税回避行為が行われる」ということが無いと考えているということであったとすれば、この部分を入れる理由がないということになりますので、東京地裁が上記の判断の中にこの部分を入れた理由は、東京地裁が「休眠会社を利用した組織再編成によって不当な租税回避行為が行われる」ということが有ると認識しているためということになります。
ただし、東京地裁が本件の合併について「休眠会社を利用した組織再編成によって不当な租税回避行為が行われる」というものではないと判断していることは、上記の判断の全体の趣旨からも、明確です。
そして、東京地裁は、そのように判断する理由については、上記の判断のところではなく、本件地裁判決の第3の3の後の同4の「本件における不当性要件該当性の検討」のところで具体的に示すと整理しているものと考えられます。
上記の判断においては、上記の冒頭の文言に続けて、ヤフー事件最高裁判決で示された判断の枠組みを確認した上で、特に、上記2のⅲで確認した「観点」から不当性要件の該当性を判断するべきであるということを強調しています。
ここで述べられていることは、至極、妥当であると考えます。
また、上記の判断は、最後の部分で、「法令上に明記されていない一律の「前提」(事実上の要件)を明確な根拠もなく想定すべきではない」としていますが、この部分についても、正確に理解しておく必要があります。
この部分の「前提」には、「一律の」という、その後に続く「前提」を制限する形容詞が付されており、この部分は、「前提」を想定すること自体が正しくないと述べているわけではありません。
上記ⅲ(ⅱ)で引用した「前提」という用語の定義の中に「例えば、「全ての人は平等である」という前提のもと、法律が制定されることがある」とあったことからも分かるとおり、法令の規定を設けるに当たって、「前提」を置いて企画立案をするということは、普通に行われていることであって、何ら問題となることではありません。
このため、法令の規定を解釈するに当たっても、「前提」があると解釈すること自体には、何ら問題はありません。
しかし、法令の規定を解釈するに当たって、「一律」に、ある「前提」があると解釈するということになると、その「前提」となっているはずの典型的なものに該当しないものにまで、その解釈を杓子定規に適用するということになってしまい、その取扱いに問題が生ずることがあります。
また、この部分からは、国側が「前提」を「事実上」の「要件」とする主張を行っていることは誤りであるという文意も読み取ることができるわけですが、これも当然のことです。
上記ⅳ(ⅱ)において述べたとおり、要件として規定が設けられていないものと要件として規定が設けられているものには、当然、違いがあります。
ⅵ 上記①ⅴ(ⅴ)で確認した本件地裁判決の判断について
(ⅰ)本件地裁判決の第3の3(5)オの確認
本件地裁判決の第3の3(5)オは、次のようなものとなっています。
「 したがって、完全支配関係適格合併の場合において、「合併による事業の移転及び合併後の事業の継続」が法人税法57条2項等の適用の「前提」となっているとか、「合併による事業の移転及び合併後の事業の継続」がない完全支配関係適格合併に上記規定を適用することはその本来の趣旨及び目的に反するなどと解することはできない。
被告の前記アの主張は、理由がない。」(62・63頁)
上記の判断は、上記ⅴで引用した本件地裁判決の第3の3(5)エで述べられていることを踏まえて、国側の主張に理由がないということをまとめて述べたものとなっています。
筆者も、この判断は、基本的には適切なものとなっていると考えています。
(ⅱ)東京地裁は、組織再編成税制の創設時から「事業の継続」ということは法人税法2条12号の8イ等の規定の本来の趣旨及び目的とはなっていなかったと判断している
東京地裁の審理の過程において、納税者側は、平成22年度税制改正の内容を具体的に挙げて、同改正により、法人税法2条12号の8イ等の規定の本来の趣旨及び目的に関しては、「事業の継続」について、同改正前よりも、なお一層、柔軟に考えるべきこととなっているということ、そして、そのようになっていることを踏まえて本件について判断をすれば、本件においては、被合併法人は簿外債務の返済の督促をひたすら待ち続けるという受動的な業務(「待ちの業務」と言ってもよいでしょう。)を行っていたものであり、合併後も「事業の継続」があるということとなって、同法132条の2の適用を受けることはないと主張していました。
一方、本件地裁判決は、平成22年度税制改正の改正内容に言及することなく、組織再編成税制の創設以来、「事業の継続」ということは、法人税法2条12号の8イ等の規定の本来の趣旨及び目的とはなっていなかったという判断を示しています。
確かに、平成22年度税制改正は、過去の改正であって、本件は同改正後の事案であり、今後とも同改正前の事案が問題となることはありませんので、同改正以後の条文解釈が同改正からのものであるのか平成13年度税制改正による組織再編成税制の創設時からのものであるのかという時期の問題は、条文解釈の正否に影響するものではなく、あまり重要ではありません。
ただし、厳密に時期の問題も加味して見ていくということになると、上記の判断とは少し異なるところもあるように思われます。
「厳格に考える」ということをしないということは、「考えない」ということではありませんし、「緩和する」ということも、「無いこととする」ということではありません。
また、投資法人の合併のケースも、被合併法人の事業が合併法人に引き継がれないということであれば、合併法人と被合併法人が完全支配関係にあったとしても、TPR事件と同様に、被合併法人の未処理欠損金額の合併法人への引継ぎは、認められなかったものと考えられます。
それは何故かというと、平成22年度税制改正前は、合併に関し、それが100%の資本関係にある法人間のものであったとしても、被合併法人の事業を合併法人に引き継がずに被合併法人の未処理欠損金額だけを合併法人に引き継ぐこととしてよいという考え方は、採っていなかったからです。
(ⅲ)平成22年度税制改正以後は、「事業の継続」が法人税法2条12号8イ等の規定の本来の趣旨及び目的とはなっていないという趣旨解釈もあり得る
平成22年度税制改正においては、いわゆる「グループ法人税制」が創設され、完全支配関係にある全ての法人について、法人間の資産の譲渡取引の損益の計上を繰り延べる等の措置を講じたことに伴い、組織再編成税制においても、特に、完全支配関係にある法人間の組織再編成について、「グループ法人の実質的な一体性」が従来以上に重視されるようになり、それと裏腹の関係で、グループ法人の「事業」が重視されないようになっています。
このような平成22年度税制改正以後の組織再編成税制については、「現行の組織再編税制は、グループ経営の場合には、グループ最上位の法人がグループ法人及びその資産の実質的な支配者であるとの観点に立って判断しているという側面もあり」(財務省『平成29年度 税制改正の解説』317頁)というような説明もされています。
つまり、完全支配関係にある法人については、一つの法人の本店と支店との関係や支店相互の関係と同じように一体であって、例えて言えば、組織再編成による資産の移転も、本支店間や支店相互間の譲渡による資産の移転と同じように、一人の人が右のポケットから左のポケットに物を移すだけのことであるというように考える傾向が非常に強まっているということです。
この平成22年度税制改正においては、解散後の残余財産の分配又は引渡しという、「事業」を行っていない法人の「現物分配」について、新たに組織再編成に含めた上で、完全支配関係にある法人間で行うものを「適格現物分配」と呼んで適格組織再編成に加えたり、一つの項(法人税法57条2項)の中に、「適格合併」の取扱いと並べて、完全支配関係にある法人の「残余財産の確定」という、「事業」を終えていなければ有り得ないものの取扱いを追加して、「残余財産が確定した法人の欠損金については・・・合併に係る欠損金の引継ぎと同様の取扱いとすることとされました」(財務省『平成22年度 税制改正の解説』284頁)と解説したり、「事業を移転しない」分割等についても適格分割等となるということを前提として、同条4項で未処理欠損金額の使用制限を緩和したりしています。
これらは、組織再編成全般について、「事業」を移転するものでなくても、適格組織再編成とすることとして未処理欠損金額について使用制限を課さないこととするという新たな考え方が採られるようになったということを意味しています。
つまり、平成22年度税制改正によって合併に関する取扱い自体は変更されてはいないものの、同改正によって、組織再編成税制全般の考え方が変わっているため、適格合併について定める法人税法2条12号の8イ等の規定の本来の趣旨及び目的も、その変化と無縁であると解することはできず、「事業の継続」がこれらの規定の本来の趣旨及び目的とはなっていないという趣旨解釈もあり得るようになっている、ということです。
参考のため、上記ⅲ(ⅰ)で引用した『法令解釈の常識』の引用部分の後に記載されていることを紹介しておくと、次のとおりです。
「立法当時にくらべて、その法令の背景となる社会状態(政治、経済、社会、文化各方面の諸条件)がすっかり変ったような場合には、立法の目的、趣旨というものも、やはり、その新しい社会状態に合致するような形でつかむようにしなければいけないのである。こういう場合にも、あくまで法令制定当時の立法の目的、趣旨に固執し、これだけが解釈の基準であるといってがんばることは、決して正しい解釈態度とはいえないのである。」(林修三『法令解釈の常識』105頁)
この記述は、法令が変わらない状態で「社会状態」が変わった場合に、「立法の目的、趣旨」を変えなければならないと述べたものですが、平成22年度税制改正においては、組織再編成税制自体の状態が変わっているわけですから、当然、「立法の目的、趣旨」も、その変化に合わせて変えなければならないということになります。
次のaとbにおいて、平成22年度税制改正が組織再編成税制の「立法の目的、趣旨」を変えることとなって、同改正以後、「事業の継続」が法人税法2条12号8イ等の規定の本来の趣旨及び目的とはなっていないという趣旨解釈があり得るようになったのは、何故なのかということ、そして、同改正においては、完全支配関係法人間の組織再編成によって租税回避が行われることについてどのように考えていたのかということを確認することとします。
a 平成22年度税制改正以後、「事業の継続」が法人税法2条12号8イ等の規定の本来の趣旨及び目的とはなっていないという趣旨解釈があり得るようになったのは、同改正において、改正内容に疑問がある改正が行われているためである
上記(ⅲ)で述べたとおり、平成22年度税制改正以後は、完全支配関係にある法人間の適格合併に「事業の継続」は必要ないという趣旨解釈もあり得るようになっていると考えられるわけですが、そのようになったのは何故なのかということを掘り下げて考えてみると、それは、同改正において、改正内容に疑問がある改正が行われているためであると考えられます。
平成22年度税制改正における組織再編成税制の改正のうち、本件に関連するものとして取り上げたものについて、筆者の意見を要約して述べると、次のとおりです。
「現物分配」や「適格現物分配」と呼ぶこととされたものは、いわゆる現物配当ですが、法人税法においては、「配当」は、課税済みの剰余を株主に分配するものとされています。
つまり、「配当」について、「適格現物分配」と呼んで、課税をしないまま金銭以外の資産を株主に分配をすることができる制度を法人税法の中に作るということは、法人税法の基本理論に明らかに反するものであるということです。
また、残余財産が確定した場合に未処理欠損金額を株主に引き継ぐというものは、清算の時点で未処理欠損金額を株主に引き継ぐというものの時期を早めただけのものであるわけですが、法人が「清算」をするにもかかわらず、課税関係(未処理欠損金額に関する部分)は清算させないという制度を作ることは、法人税法の基本的な考え方に明らかに反するものです。
また、事業を移転しない分割等について適格分割等として課税を繰り延べるという仕組みは、個別の資産の取引について「分割」等とすれば課税を繰り延べるという仕組みを作ったものに他ならず、組織再編成税制における適格組織再編成の基本的な考え方に穴を開けたものであることが明らかです。
このように、平成22年度税制改正において、法人税法の基本的な理論や考え方に明らかに反する改正を行ったり、組織再編成税制の基本的な考え方を崩す改正を行ったりしたことで、条文に書かれていない「本来の趣旨及び目的」が何かという、元々、分かりにくさが伴わざるを得ない解釈が非常に難しくなっています(注2)。
(注2)法人税法の基本的な考え方や理論に明らかに反する改正を行ったり、同法の中の各制度の基本的な考え方を崩す改正を行ったりするということは、役員給与の取扱いの原則を損金不算入とするという、法人税法における「損金」の考え方と理論のいずれからしても、本来、あり得ない改正を初めとして、いくつかの疑問のある改正を含む改正を行った平成18年度税制改正から見受けられるようになってきたものであり、平成22年度税制改正における組織再編成税制の改正だけに特有のものではありません。平成18年度税制改正以後、そのような改正が行われたものの関係条文の中には、その解釈の難易度が非常に高くなってしまったものがあるという状態となっています。
もう少し具体的に言うと、平成22年度税制改正によって「現物分配」などを始めとして「事業の継続」が明らかに不要とされているものが適格組織再編成の中に含められることとなっていますので、同改正以後、平成12年10月の政府税制調査会の法人課税小委員会の報告書にあった「ただし、完全に一体と考えられる持分割合の極めて高い法人間で行う組織再編成については、これらの要件を緩和することも考えられる」という、「組織再編成」の全般に関して「緩和」をされた「これらの要件」が有るという認識に基づいて書かれた文言が同改正以後もそのまま生きているとするのは難しいと考えられますし、平成13年8月の『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』の中の「従業者の引継ぎ要件」に関する質問に対する回答にある「適格組織再編成として従前の課税関係を継続させるものは、基本的には、独立した事業単位が移転するものと考えられています」という、「適格組織再編成」の全般に関して「基本的には、独立した事業単位が移転するもの」という旨の文言についても、同様で、同改正以後、そのままその文言どおりに生きているとしてよいのかということには、疑問が残らざるを得ないと考えられます。
平成22年度税制改正が上記のようなものとなっていることからすると、同改正以後の事案において、完全支配関係にある法人間の適格合併に「事業の継続」は必要ないという裁判所の判断が示された場合、その判断が誤っていると主張するのは難しいと考えられます。
そうすると、完全支配関係法人間の組織再編成について、「事業の継続」がないということを理由として、租税回避であるとして課税をするということは難しいということにならざるを得ません。
平成22年度税制改正以後、このような状況となっているということは、同改正を「租税回避」という側面からみても確認することができますので、次のbで説明することとします。
b 平成22年度税制改正における組織再編成税制の改正においては、完全支配関係法人間の組織再編成によって租税回避が行われるということは考慮されなかったと考えざるを得ない
税制の仕組みは、租税回避が行われないようにするということを念頭に置きながら作る必要がありますので、平成13年に組織再編成税制を創設した際にも、当然、租税回避が行われないようにするということを念頭に置きながら、制度の企画立案を行いました。
平成13年8月に発刊した『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』は、平成12年7月3日、同年10月11日、平成13年3月23日及び同年5月16日の4回の講演を短く編集して収録したものですが、同書を確認していただくと分かるとおり、その4回の講演の記録は、短いもので5頁、長いものでも18頁しかないものの、その4回の全てにおいて、相当な行数を用いて「租税回避」の説明を行っています。講演の記録が一番短いものは、平成13年5月16日のもので、5頁となっていますが、そのように短いものでも、「租税回避」について15行にわたって説明を行っています。勿論、『平成13年 改正税法のすべて』(国税庁)における組織再編成税制に関する解説においても、同様で、「租税回避」について、「二 制度の概要」と「三 制度の内容」の2か所で合計65行を用いて説明を行っています。
一方、平成22年度税制改正における組織再編成税制の改正に関する財務省の解説である『平成22年度 税制改正の解説』がどうなっているのかというと、組織再編成税制の改正について非常に多くの紙面(287頁から337頁まで50頁分もの紙面)を割いて解説を行いながら、その解説の中には、「租税回避」に言及しているところが全くなく、「租税回避」という用語さえ全く出てきません。
平成22年度税制改正による組織再編成税制に関する改正においては、完全支配関係法人間の組織再編成に関する多くの改正を行っていますが、TPR事件における助言(上記3参照)でも述べたとおり、100%グループ内では特に租税回避が行われ易いわけですから、このような改正を行う場合には、本来は、租税回避を防止するということも常に考えながら、改正の内容を慎重に吟味することが必要となります。
しかし、平成22年度税制改正における組織再編成に関する改正に関しては、その改正の財務省の解説を読んでも、TPR事件のようなことを行ったものが租税回避として否認されると解する根拠となり得るものや完全支配関係にある休眠会社を利用した組織再編成などが租税回避として否認されると解する根拠となり得るものは、全く確認することができません。
つまり、同族会社間の組織再編成の典型例である完全支配関係法人間の組織再編成に関して新たに課税を繰り延べるという制度を作りながら、租税回避に何の制度対応もせず何の解説もしないなどということは、法人税法の立法の常識からすると、本来は、あり得ないことですが、平成22年度税制改正における組織再編成税制の改正に関しては、現実には、租税回避を防止するための制度対応は全くされておらず、租税回避に関する解説も全くされていないということです。
このような事情にあることからすると、平成22年度税制改正によって行われた完全支配関係法人間の組織再編成に関する改正においては、完全支配関係法人間の組織再編成によって租税回避が行われるということは考慮されなかったと考えざるを得ません。
何故、そのように考えざるを得ないのかというと、上記(ⅲ)において述べたとおり、平成22年度税制改正によって、組織再編成税制全般の考え方に変化が生じ、完全支配関係にある法人は本店と支店との関係や支店相互の関係と同じように一体であって、例えて言えば、組織再編成による資産の移転も、本支店間や支店相互間の譲渡による資産の移転と同じように、一人の人が右のポケットから左のポケットに物を移すだけであるというように考える傾向が非常に強まり、その結果、必然的に、租税回避ということに関しても、完全支配関係法人間における組織再編成による資産の移転については、それを租税回避とはみない傾向が非常に強まっているためです。
このように、上記aで取り上げた「適格現物分配」を設ける改正等が行われたことや上記の傾向が非常に強まっていることは、本件の納税者側からすれば、本件が租税回避とはならないということをより一層明確にするものですから、歓迎するべきことです。
ただし、筆者は、法人税法の本来のあるべき姿という観点からすると、上記aで取り上げた「適格現物分配」を設ける改正等が行われたことや上記の傾向が非常に強まっていることについては、いずれも疑問があり、決して歓迎できるようなことではない、と考えています。
国税当局は、本件が敗訴で確定したとしても、TPR事件の合併と同じようなことをしたもの、本件のような事情(法人を買収して合併を繰り返すビジネスモデルに沿って合併をしていたり、買収した法人に簿外債務が存在していたりするなどの事情)がないまま休眠状態となっている法人を吸収合併したものなどに対しては、法人税法132条の2によって未処理欠損金額の引継ぎを否認したり、移転資産の含み損益を計上させたりする可能性が高いと思われますので、納税者としては、十分に注意をする必要がありますが、平成22年度税制改正以後の組織再編成税制の改正により、それらの処分の正当性の説明は、かなり難しくなっていると感じます。
この連載の記事
-
2025.01.09
第1回 はじめに、本件の概要と過去判決の確認
-
2025.01.09
第2回 本件地裁判決の確認と筆者の意見(その1)
-
2025.01.09
第3回 本件地裁判決の確認と筆者の意見(その2)
-
2025.01.09
第4回 本件地裁判決の確認と筆者の意見(その3)
-
2025.01.09
第5回(最終回) 最後に
テーマ
プロフィール

免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。