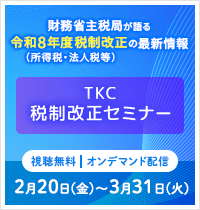更新日 2025.01.09

株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹
令和6年9月27日に、法人税法132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)の適用の可否が争われていたPGMプロパティーズ事件で、東京地裁の判決が下され、納税者側が完全勝訴となりました。この事件は、現在、国側が控訴しており、まだ判決が確定しているわけではありませんが、この事件の判決がどのような内容で確定するのかによって子会社等の組織再編成に影響が出てくるというケースもあると考えられます。
今回は、この事件の判決を取り上げてみます。
当コラムのポイント
- TPR事件の判決を杓子定規に用いるのは適切ではない
- 国税当局は、本件が敗訴で確定したとしても、TPR事件の合併と同じようなことをしたもの、本件のような事情がないまま休眠状態となっている法人を吸収合併したものなどに対しては、租税回避として課税することになる可能性が高いため、十分に注意をする必要がある
- 目次
-
はじめに
法人税法132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)が適用されて争いとなった事件としては、既に、ヤフー事件、IDCF事件、TPR事件の3件があり、この3件については、いずれも地裁から最高裁まで全て国側が勝訴しています。
このため、法人税法132条の2が適用されて争いとなった事件の中では、PGMプロパティーズ事件(以下、「本件」といいます。)が初めて納税者側が勝訴したものということになります。
筆者は、本件の前の3件においては、国側の依頼により、意見書を書いたり助言を行ったりしたところですが、本件においては、納税者側の依頼により、意見書、陳述書、補充意見書2通の合計4通を書くとともに、助言を行いました。
1.本件の概要
本件の概要を図示すると、次のようになります。

PGMグループは、従来から、ゴルフ場事業を行う法人を買収し、その後、買収した法人を合併によって減らしてコストを削減するということをビジネスモデルとして行ってきており、本件の買収と合併も、そのビジネスモデルに沿って行ったものであって、PGPAH6に未処理欠損金額がなかったとしても、同社は、いずれかの時期にいずれかの方法によっていずれかの法人に吸収合併されることとなることが当初から想定される状況にありました。
上記①の大手商社からのPGPAH6の株式の取得に際しては、PGPは、ゴルフ場事業のみを買い取りたいと二度にわたって申し出たものの、大手商社からその申し出が受け入れられなかったため、やむなくPGPAH6の株式を取得して会社ごと買い取ることとなったものです。
また、上記③にあるとおり、PGP千葉の株式をPGMP1に譲渡することで、税法上、57億円の損失が発生し、それがPGPAH6の未処理欠損金額となったわけですが、PGPAH6の経理担当者が税法上で損失が発生するということに気づいたのは、PGP千葉の株式を譲渡した後、四半期決算において、顧問税理士に税金計算を行ってもらった時であり、このPGP千葉の株式の譲渡は、税法上で損失が発生するということを全く考慮せずに簿外債務からゴルフ場事業を完全に切り離すという目的のみで行われたものです。
2.本件地裁判決で不当性の判断枠組みとなっているヤフー事件最高裁判決の確認
本件の東京地裁判決(以下、「本件地裁判決」といいます。)は、ヤフー事件の平成28年2月29日最高裁判決(以下、「ヤフー事件最高裁判決」といいます。)において示された法人税法132条の2の解釈に基づいて判断を下しています。
ヤフー事件最高裁判決において示された法人税法132条の2の解釈を確認しておくと、次のⅰからⅳまでのとおりとなります。
下線は、筆者が付したものであり、以下、同じです。
ⅰ 法人税法132条の2の意義
「 組織再編成は,その形態や方法が複雑かつ多様であるため,これを利用する巧妙な租税回避行為が行われやすく,租税回避の手段として濫用されるおそれがあることから,法132条の2は,税負担の公平を維持するため,組織再編成において法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる行為又は計算が行われた場合に,それを正常な行為又は計算に引き直して法人税の更正又は決定を行う権限を税務署長に認めたものと解され,組織再編成に係る租税回避を包括的に防止する規定として設けられたものである。」
ⅱ 租税回避とは何か
「このような同条の趣旨及び目的からすれば,同条にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,法人の行為又は計算が組織再編成に関する税制(以下「組織再編税制」という。)に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり,」
ⅲ どのような観点から判断するべきか
「 当該行為又は計算が,組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって,組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。」
ⅳ 判断に当たってどのような事情を考慮すべきか
「 その濫用の有無の判断に当たっては,①当該法人の行為又は計算が,通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり,実態とは乖離した形式を作出したりするなど,不自然なものであるかどうか,②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で,」
上記ⅲの「観点」については、「組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したもの」には、節税を意図したものと租税回避を意図したものの両方が含まれることとなり、それのみで租税回避と判断されるわけではなく、「組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められる」ということでなければ租税回避と判断されることはない、ということに留意しておく必要があります。
組織再編成を利用しようが利用しまいが、納税者が「税負担を減少させることを意図」して行動するのは、正常なことであって、むしろ、納税者が「税負担を減少させることを意図」しないで行動することの方が異常であると言っても、決して過言ではありません。現に、機器等の取引を増やしたり、研究開発を促進したり、給与を増やしたり、寄付を増やしたりすることなどを目的として、非常に多くの減税措置が講じられており、それに伴い、非常に多くの納税者が「税負担を減少させることを意図」して、これらの機器等の取引を増やすなどの行動をしている事実があります。このようにして増加した行動は、税負担が減少しなければ行われることのなかったものということになります。このような事実があることは、税制は納税者が「税負担を減少させることを意図」して行動するということを前提として創られていることを示すものです。つまり、税制は、納税者は「節税」を行うという前提で創られている、ということです。
また、上記ⅲの「組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的」については、「組織再編税制の各規定」が改正されている場合には、その改正後の「組織再編税制の各規定」の「本来の趣旨及び目的」となることに留意しておく必要があります。ヤフー事件、IDCF事件、TPR事件の3件は、平成22年度税制改正による組織再編成税制の大幅な改正の前の事件となっていますが、本件は、同改正の後の事件となっています。
そして、上記ⅲにある「観点から判断する」ということと上記ⅳにある「事情を考慮」するということの違いも、正しく理解しておく必要があります。上記ⅲの二つの「観点」は、上記ⅱの「各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるもの」であるのか否かということを判断するに当たって、必ず必要となるものですが、これに対し、上記ⅳの①や②は、考慮するべき「事情」の例示に止まり、必ず①や②を考慮しなければならないということではなく、また、①や②以外の「事情」を考慮することもあるということになります。
加えて、上記ⅳに関しては、「節税」を行っていることは、「濫用」と判断する「事情」とはならず、むしろその反対に、「濫用」ではないと判断する「事情」となり得るということに留意する必要があります。
上記ⅳの②の「税負担の減少」には、その事由に限定が付されているわけではありませんので、「節税」によって「税負担の減少」が起こるものも含まれることとなり、同②の「税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在〔しない〕」とされるものに、「節税」以外の事由は存在するが「節税」が主たる事由であるというものも含まれると判断されることがないとは言えません。
しかし、「節税」を行ったという「事情」にあるものについては、上記ⅳの②に該当すると判断されることがあるとしても、同②の後に続く「等」に含まれる「事情」があるものとして「考慮」されることとなります。
つまり、上記ⅲの「組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるもの」でないことが明らかであると判断される「事情」があるものについては、上記ⅳの②に該当すると判断されることがあるとしても、同②の後に続く「等」に含まれる「事情」があるものとして「考慮」されて、上記ⅱの「組織再編税制・・・に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるもの」ではないと判断される、ということです(注1)。
(注1)ヤフー事件においても、「そうすると,本件副社長就任は,組織再編税制に係る上記各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものとして,法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たると解するのが相当である。」(ヤフー事件最高裁判決)というように、法人税の負担の減少が「組織再編税制に係る上記各規定を租税回避の手段として濫用すること」に因るものであることを理由として法人税法132条の2が適用されると判断しており、「法人税の負担を減少させるもの」ということを無限定に用いて同条が適用されると判断しているわけではありません。
改めて言うまでもないことですが、法人税法132条の2は、法人が法人税の負担を減少させようと努力することは当然であるという企業経営の常識も考慮した上で創られたものであって、法人が法人税の負担を減少させる行為又は計算を行えばそれのみを以って直ちに同条が適用されるなどという考え方で創られたものではありません。
3.課税の根拠とされたTPR事件の東京高裁判決の確認
本件においては、東京国税局は、TPR事件の令和元年12月11日東京高裁判決(以下、「TPR事件判決」といいます。)において示された適格組織再編成に関する法人税法の規定の本来の趣旨及び目的の理解に基づき、その本来の趣旨及び目的を逸脱する態様で適格合併の規定(法法2十二の八)及び被合併法人の未処理欠損金額の引継ぎの規定(法法57②)の適用を受けるものであるとして、同法132条の2を適用しています。
このTPR事件判決において示された適格組織再編成に関する法人税法の規定の本来の趣旨及び目的の理解がどのようなものであったのかということを確認しておくと、次のとおりとなります。
「同条の不当性要件の有無については,平成28年最判の判示する「租税回避の意図」の有無及び「各規定の趣旨目的からの逸脱」の有無の観点から検討すべきであり,後者の観点は,本件合併が,適格合併における未処理欠損金額の引継ぎ等について定める法人税法57条2項の趣旨目的から逸脱しているか否かの観点から検討するのが相当というべきである。」
「確かに,完全支配関係にある法人間の適格合併については(法人税法2条12号の8イ),支配関係にある法人間の適格合併におけるような従業者引継要件及び事業継続要件(同条12号の8ロ)の定めは設けられていない。しかしながら,原判決第5・3(2)が説示するように,組織再編税制は,組織再編成の前後で経済実態に実質的な変更がなく,移転資産等に対する支配が継続する場合には,その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるということを基本的な考え方としており,また,先に組織再編税制の立案担当者の説明を引用して判示したとおり,組織再編税制は、組織再編成により資産が事業単位で移転し,組織再編成後も移転した事業が継続することを想定しているものと解される。加えて,これも原判決が第5・3(2)で説示するとおり,支配関係にある法人間の適格合併については,当該基本的な考え方に基づき,前記の従業者引継要件及び事業継続要件が必要とされているものと解され,殊更に,完全支配関係にある法人間の適格合併について,当該基本的な考え方が妥当しないものと解することはできないから,当該適格合併においても,被合併法人から移転した事業が継続することを要するものと解するのが相当である。」
このように、TPR事件判決は、適格組織再編成に関する法人税法の規定の本来の趣旨及び目的は、「組織再編成により資産が事業単位で移転し,組織再編成後も移転した事業が継続する」というものについて、「適格」として従前の課税関係を継続させるということである、とした上で、「完全支配関係にある法人間の適格合併」においても、「被合併法人から移転した事業が継続することを要するものと解するのが相当」と判示しているわけです。
このTPR事件判決は、要約すると「完全支配関係にある法人間の合併を適格合併と定めた法人税法2条12号の8イには、従業者引継要件も事業継続要件も設けられてはいないが、同号イの本来の趣旨及び目的は上記のようなものであるから、ヤフー事件の平成28年2月29日最高裁判決において示された法人税法132条の2の解釈に基づいて判断をすれば、TPR事件には、同条が適用されることになる」というものであって、ヤフー事件最高裁判決で示された判断の枠組みを正しく踏まえたものとなっています。
このTPR事件判決の判示は、国側が主張したことを東京地裁がそのまま採用し、更にそれを東京高裁がそのまま採用したというものですが、東京地裁においては、国側は、平成30年3月22日に提出した準備書面(3)までは、筆者の『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』(日本租税研究協会、平成13年8月)等を証拠資料として提出して、法人税法2条12号の8イの本来の趣旨及び目的は「移転資産に対する支配の継続」があるものを適格合併とするというものであると主張していました。
しかし、TPR事件においては、「移転資産」は被合併法人から合併法人に移転してそのまま合併法人に残っていますので、この国側の主張をもって法人税法132条の2が適用されることになるというには、そもそも無理がありました。
このため、国側から筆者に対して助言の依頼があり、平成30年6月21日に、筆者から国側に助言をさせていただきました。
その助言の内容は、100%グループ内では赤字会社を黒字会社と合併させて税金を減らすなどということが簡単に行い得るので100%グループ内の適格合併については他の適格合併よりも租税回避に当たるのではないかという目でよく見る必要があるということ、平成13年の組織再編成税制の案は「事業」を移転するものが「組織再編成」であると考えて創ったということ、そして、結論として、100%グループ内の合併で、被合併法人の「事業」を合併法人に引き継いでいないというものについては、被合併法人の未処理欠損金額の合併法人への引継ぎを租税回避として否認するべきであるということでした。この助言に際し、筆者は、「事業」がどのようなものであるのかということについて全く何も言及しませんでしたが、それは、TPR事件が本件とは異なって組織再編成税制における「事業」がどのようなものであるのかということが全く問題とはならない事案であったからです。また、TPR事件は、組織再編成税制の大幅な改正が行われた平成22年度税制改正前の事件でありながら、その訴訟は同改正後に行われているという状況にありましたので、その訴訟においては、同改正を考慮せずに主張をしなければならないということに留意する必要がありましたが、本件は、TPR事件とは異なり、同改正後の事件ですから、納税者側と国側はいずれも同改正を十分に考慮した上で主張をしなければならないということに留意する必要があります。
平成13年の組織再編成税制の創設時には、組織再編成について「適格組織再編成」というものを設けて移転資産の含み損益の計上を繰り延べることとしたところですが、譲渡について「適格資産譲渡」などというものを設けて移転資産の含み損益の計上を繰り延べるということまでしたわけではありません。それは何故かというと、組織再編成は、譲渡と同様に資産を移転するものではあるものの、「事業」を移転して再編成を行うものであって、譲渡とは異なると考えていたからです。ただし、この「事業」については、平成13年当時、「事業」の移転を厳格に求めるドイツの税制の問題点の話をしたり、オフバランスの資産や負債だけを持つことになる「事業」もあるという話をしたりして、その内容や範囲などを「厳格に考える」ということはしないと説明していました。このような説明を平成13年当時に行っていたということは、『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』の記述(後掲4(2)②ⅲ(ⅳ)参照)からも明確に確認していただくことができます。
また、このように、平成13年に創設された組織再編成税制において、「事業」や「事業の移転」の内容と範囲などを「厳格に考える」ということをしていなかったということは、国税庁が公表している平成21年3月19日付けの「投資法人が共同で事業を営むための合併を行う場合の適格判定について」という照会回答事例(後掲4(2)②ⅱ参照)からも明確に確認することができます。
TPR事件においては、筆者が上記の助言をした後、国側は、主張を変更し、平成30年8月21日に提出した準備書面(4)では「事業が移転する」ものか否かということが法人税法132条の2の適用の有無の判断基準となるということを前面に据えた主張をするようになり、それが東京地裁判決で採用されることとなりました。
筆者がこの助言をした際に国側に示したのが『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』の中の「(質問2)〇 従業者の引継ぎ要件」という質疑応答です。
本件においても、国側は、この質疑応答の「適格組織再編成として従前の課税関係を継続させるものは、基本的には、独立した事業単位が移転をするものと考えられています」という記述を根拠として課税処分の正当性を主張しました(後掲4(2)②ⅳ(ⅱ)参照)。
この連載の記事
-
2025.01.09
第1回 はじめに、本件の概要と過去判決の確認
-
2025.01.09
第2回 本件地裁判決の確認と筆者の意見(その1)
-
2025.01.09
第3回 本件地裁判決の確認と筆者の意見(その2)
-
2025.01.09
第4回 本件地裁判決の確認と筆者の意見(その3)
-
2025.01.09
第5回(最終回) 最後に
テーマ
プロフィール

免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。