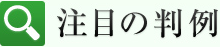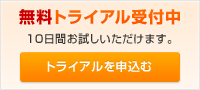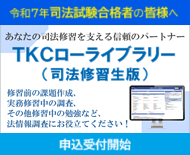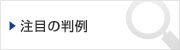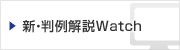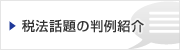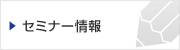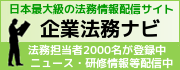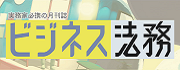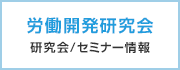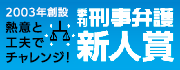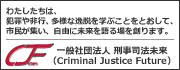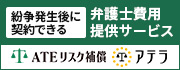2025.12.16
保険金請求事件 

LEX/DB25623563/最高裁判所第一小法廷 令和 7年10月30日 判決(上告審)/令和6年(受)第120号
Aが車両を運転中に自損事故を起こして死亡したことについて、Aの相続人であるBが、当該車両に係る自動車保険契約の保険者である上告人・保険会社に対し、当該保険契約に適用される普通保険約款中の人身傷害条項に基づくAの人身傷害保険金の請求権を相続により取得したと主張して、人身傷害保険金の支払を求め、Bが第一審係属中に死亡し、被上告人らが相続により本件訴訟を承継した事件において、第一審が請求を一部認容したことから、上告人が控訴し、控訴審が控訴を棄却し、認容額を減額更正したところ、上告人が上告した事案で、死亡保険金の請求権は、被保険者の相続財産に属するものと解するのが相当であるとし、また、死亡保険金の額は、人身傷害保険金を支払うべき被保険者の精神的損害の額が本件精神的損害額の全額であることを前提として算定されるべきであって、被保険者の死亡により精神的損害を受けた被保険者の近親者が存在することは死亡保険金の額に影響を及ぼすものではないと解するのが相当であるから、所論の点に関する原審の判断は結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。