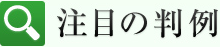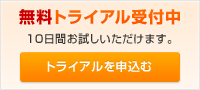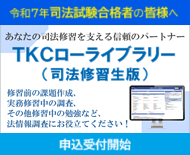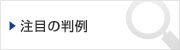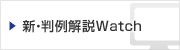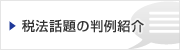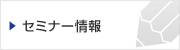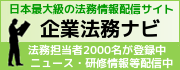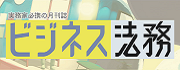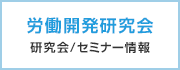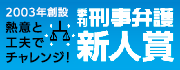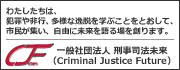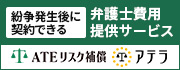2026.01.06
現住建造物等放火、殺人被告事件 

LEX/DB25574581/札幌地方裁判所 令和 7年 9月17日 判決(第一審)/令和5年(わ)第27号
被告人は、A(当時71歳)及びB(当時51歳)ら14名が現に住居に使用し、かつ、同人らが現にいる無料低額宿泊所「C」(本件施設)に放火して前記Aを殺害しようと考え、前記Bら他の入居者が死亡するかもしれないことを認識しながら、本件施設213号室の当時の被告人方居室及び2階廊下等に灯油をまいたうえ、殺意をもって、ライターで紙片に火をつけ、これを用いて同居室内のカーテンに点火して火を放ち、その火を本件施設の床面及び壁等に燃え移らせ、よって、本件施設を全焼させて焼損するとともに、本件施設201号室において前記Aを、本件施設206号室において前記Bを、それぞれ焼死させて殺害したとして、現住建造物等放火、殺人の罪で懲役30年を求刑された事案で、本件犯行当時の被告人には、善悪の識別に従って自分の行動をコントロールできる能力が失われていた疑いが残るといわざるを得ず、完全責任能力を有していたとは認められないし、心神耗弱であったとも認められず、責任能力が失われていたとの合理的な疑いが残るから、被告人による本件行為は、心神喪失者の行為として罪とならない(刑法39条1項)として、被告人に無罪を言い渡した事例(裁判員裁判)。