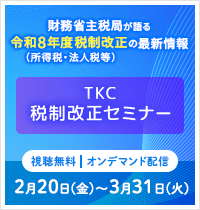更新日 2025.04.28

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ税務システム普及部会会員
税理士 杉山 直
新リース会計基準では、不動産賃貸借取引がリースとしてオンバランスの対象となり、実務上、大きな影響が生じる予定です。本コラムでは、不動産賃貸借の会計処理と税務処理の調整方法について、具体的な事例をもとに解説します。
当コラムのポイント
- 不動産賃貸借取引の会計処理と税務調整について、別表の具体的な記載方法を紹介します。
- 外形標準課税の対象となる支払賃借料について、税務上の取り扱いを解説します。
- 目次
-
前回の記事 : 第2回 税制改正をふまえた税務・会計の留意点
1.はじめに
令和6年9月13日にASBJが企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を公表し、令和9年4月1日以降の会計年度から強制適用が決定しました。税務については、令和7年度税制改正により、借手については、結論から言えば、従前の取り扱いと変わらないことになりますが、新リース会計基準の適用により会計処理と税務処理に乖離が生じ、税務調整が必要となります。本コラムでは、不動産賃貸借取引における借手(オペレーティング・リース)の取り扱いをご紹介します。
2.現行の法人税法におけるリースの取り扱い
法人税法第64条の2第3項においてリース取引が定義されており、税法上のリース取引(いわゆるファイナンス・リース)については売買処理があったものとして処理します。オペレーティング・リースについては、法人税法上のリース取引には該当せず、賃貸借処理となります。
3.令和7年度税制改正による影響
結論から言えば、税法上は従前の取り扱いについてほとんど変更はありません。オペレーティング・リース取引に係る支払額のうち、債務の確定した部分の金額を損金に算入することとされました(詳細は後述)。
また、今回の改正内容を借手側の影響と貸手側の影響に区分してご紹介します。
(1) 借手側の影響
- ①リースに係るオンバランス計上の判定について
- 新リース会計基準では、借手側は「リースの識別」によりリースを判定することとなり、契約にリースが含まれると判断された場合は、原則としてオンバランス計上となります。
一方、税法上は、従前通り「リース取引(いわゆるファイナンス・リース)」に該当した場合には、オンバランス計上となり、オペレーティング・リースに該当した場合にはオフバランス処理となります。 - ②不動産賃貸借取引について
- 新リース会計基準では、借手側の不動産賃貸借取引については、「リースの識別」により一定の要件を満たすと、原則としてオンバランス計上となります。
一方、税法上は、不動産賃貸借取引については、従前通り賃貸借処理、つまりオフバランス処理となります。 - ③所有権移転リース取引および所有権移転外リース取引について
- 新リース会計基準では、「リースの識別」により、リースと非リースを分類することとなります。
一方、税法上は、従前通りリース取引(いわゆるファイナンス・リース)について、所有権移転リース取引と所有権移転外リース取引を分類することとなります。 - ④リース期間
- 新リース会計基準では、借手のリース期間は借手が物件を使用する権利のある「解約不能期間」に、借手が行使することが合理的に確実な「延長オプション」の期間と、借手が行使しないことが合理的に確実な「解約オプション」の期間を加えて決定されます。
一方、税法上は、リース取引に該当する場合、従来通り資産の種類等に応じた法定耐用年数またはリース契約書に記載された契約期間となります。
従って、新リース会計基準が適用されると、リース期間が会計と税務で不一致になる可能性があります。 - ⑤残価保証額の取り扱い
- 従前、残価保証額の取り扱いは、税法上の所有権移転外リース取引に該当した場合、リース資産の取得価額から控除することとされていましたが、新リース会計基準の改正と同様に、法人税でも取得価額から残価保証額を控除しないこととされました。
(2) 貸手側の影響
旧リース会計基準で認められていた(第2法:毎期リース料の回収時に売上と売上原価を計上する方法)が廃止されたことに伴い、法人税法の「リース取引に係る収益計上時期の特例(旧法法63)」が廃止されました。
4.新リース会計基準における会計と税務の不一致および税務調整について
リースと識別された不動産賃貸借取引について、借手側の税務処理と会計処理の具体的な処理事例を確認します。
(1) 前提事項
- 不動産賃貸借契約の契約期間4年(合理的利用期間4年とする)
- 月額賃借料11,000円(税込)・・・以下、単位円で統一
- 利率年5.0%、消費税率10%

(2) 会計と税務の差異と具体的な処理
税務上、法人税法上のリース取引及びリース取引以外の賃貸借取引の取り扱いについて、従来の取り扱いから大きな変更はありません。オペレーティング・リース取引に関しては、改正法人税法53条において、「その契約に基づき…支払うこととされている金額のうち、当該事業年度において債務の確定した部分」を損金の額に算入することとされており、上記(1)の事例では、10,000が税務上損金算入すべき金額となります。一方、会計上は、新リース会計基準に基づき支払利息及び減価償却費を計上します。費用処理額の合計は10,855となり、税務上の損金算入限度額との差異について、税務調整が必要となります。
具体的な別表調整を以下例示します。

5.外形標準課税の付加価値割の取り扱い
改正地方税法72の17において、対象となる支払賃借料のうち、法人税法64条の2第3項に規定する取引(ファイナンス・リース取引)が除かれることが明確化されています。不動産賃貸借取引のうちオペレーティング・リースに係る支払額で、当該事業年度において法人税の所得の計算上損金の額に算入されるものは、外形標準課税の対象となる支払賃借料に含まれることになります。
この取り扱いは従前と同様ですが、新リース会計基準では支払利息および減価償却費で処理されることから、外形標準課税の対象となる支払賃借料の集計を容易に把握できるように、上記4(1)イ)の仕訳における借方の「支払賃借料」の合計額を集計する方法や、上記4(1)イ)とロ)の仕訳における「支払賃借料」の借方と貸方で勘定科目コードを別にしておくことも一つの方法かと思います。
この連載の記事
-
2025.05.15
第4回(最終回) 消費税への影響と留意点
-
2025.04.28
第3回 不動産賃貸借取引の会計処理と税務処理の調整
-
2025.03.03
第2回 税制改正を踏まえた税務・会計の留意点
-
2025.03.03
第1回 令和7年税制改正大綱の概要
プロフィール

免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。