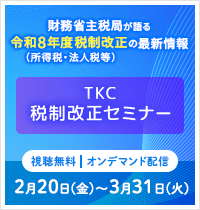更新日 2025.02.03

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
税理士・公認会計士 髙倉 裕幸
内部統制は、会社が事業活動を健全かつ効率的に運営するために必要な仕組みを指します。内部統制を整備することで、社内の不正行為やミスの防止、業務の透明性を高めるなど、重要な役割を果たします。
近年発生している経営者や従業員による粉飾決算や法令違反なども内部統制が適切に整備されていれば未然に防げていた可能性があります。
そこで、内部統制の基本や具体的な事例を紹介するとともに、全社的・決算業務の内部統制の整備、IT統制のポイントを解説します。
当コラムのポイント
- 内部統制の基本と具体的な事例を紹介
- 全社的・決算業務の内部統制の整備、IT統制のポイント
- IPO準備企業や中小企業に期待される内部統制
- 目次
-
会社法と金融商品取引法で内部統制の違いについて解説していきます。
1.会社法について
会社法は会社に関わる法律の一つであり、会社の設立・運営・解散などの基本的なルールや手続を定めている法律です。会社法で認められている会社は「株式会社」と「持分会社」の2種類に大別され、さらに持分会社は「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」の3つの種類に分類されます。
持分会社は、出資を行った社員が自ら経営を行う会社の形態であるのに対し、株式会社は、株式を通して出資した人(株主)と、実際に会社経営を行う人(取締役)が分離(※1)している点に特徴があります(所有と経営の分離)。
(※1)所有と経営が分離していなくとも問題はありません。株主でなくとも経営に参加できる点が特徴であると考えられます。
株式会社は、株主や取締役のほか、ステークホルダーとして多くの人間が関与することが想定されているため、機関設計や組織形態、運営にいたるまで細かいルールが定められています。そして、現代社会に即したかたちで株式会社のガバナンスを実現できるよう、体系的に法律が整備されています。会社法施行後も、ガバナンスの強化のために主要な改正が行われています。
株式会社は、所有と経営を分離し、様々な機関設計を可能としているため、大規模な会社運営が可能となります。大規模な会社では、従業員、取引先、債権者など多くのステークホルダーが存在し、何か問題が生じれば社会的影響が大きくなるため、各ステークホルダーの利益を適切に管理し調整することが求められます。
2.会社法で求められる内部統制について
会社法では、企業統治と事業の適正な運営を支援するための内部統制の構築が求められています。会社法362条4項6号において、
「取締役の業務執行が法令や定款に適合することを確保するための体制および当該企業やその子会社からなる企業集団の業務の適正を図るために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」
と規定し、株式会社が業務の適切性を確保するための体制を構築することを求めています。さらに、法務省令の定めである会社法施行規則100条1項には、取締役会が整備すべき体制として具体的な内容が記載されています。
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
また、大会社である取締役会設置会社は、内部統制システムの構築が義務付けられています。362条5項において、「大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。」と規定しています。
内部統制システムの構築は全ての株式会社に義務付けられているわけではなく、取締役会が設置されている大会社(資本金5億円以上または負債額200億円以上)に分類される会社のみが対象となります。大会社であっても非公開会社であれば取締役会の設置は任意となり、公開会社であれば取締役会の設置が義務付けられています。
会社法の範囲は金融商品取引法よりも広く、会社の運営に関わる内部統制までカバーしており、事業リスクの管理、法令遵守、業務効率の向上など、より全般的な統制が求められます。
3.金融商品取引法で定められている内部統制について
金融商品取引法における内部統制は、主に上場企業を対象とし、「財務報告の正確性と信頼性」を確保することを目的としています。金融商品取引法第24条の4の4第1項で内部統制について記載されており、企業は財務報告に係る内部統制を構築・評価し、その結果を内部統制報告書に記載して提出することを義務付けています。
「当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下 「内部統制報告書」という。)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない」
すなわち、主に上場企業をはじめとした有価証券報告書の提出義務のある企業を対象としています。
4.会社法と金融商品取引法の内部統制の違いについて
会社法と金融商品取引法では、内部統制の目的や対象範囲等が異なります。これは会社法が、株主をはじめとする各ステークホルダーの利益を適切に管理して調整することが目的であるのに対し、金融商品取引法は投資家保護を目的とすることに起因します。また、金融商品取引法が対象とする投資家は株式を所有している投資家(株主)のほか、これから投資をする可能性のある潜在的な投資家(非株主)も含みます。
- 会社法は「企業統治と事業運営全般にわたる内部統制」に焦点をあてているのに対し、金融商品取引法は「財務報告の信頼性を確保するための内部統制」に焦点をあてています。
- 会社法が対象とする会社は「取締役会が設置された大会社」であるのに対し、金融商品取引法が対象とする会社は「有価証券報告書を提出する会社」となります。
- 会社法の提出先は「株主総会」であるのに対し、金融商品取引法の提出先は財務局・金融庁を通じて「内閣総理大臣」に提出します。
- 取締役会設置会社は、原則として監査役(監査役会)の設置が必要となり、監査役は監査報告書を作成することとなります。一方で、金融商品取引法は公認会計士又は監査法人による会計監査を義務付けています。
これらの違いにより、会社はそれぞれの法律に基づいた適切な内部統制システムを設計し、運用する必要があります。
この連載の記事
-
2025.07.07
第4回 内部統制報告制度における全社的な内部統制と決算・財務報告に係る内部統制について
-
2025.02.03
第3回 会社法と金融商品取引法で求められる内部統制の違いについて
-
2025.01.20
第2回 内部統制の事例について
-
2025.01.14
第1回 内部統制の基本的な考え方
プロフィール

税理士・公認会計士 髙倉 裕幸(たかくら ひろゆき)
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
- 略歴
- 1998年に株式会社富士通研究所に入社しJPEGを中心とした画像圧縮技術を専門として研究開発に従事。その後、2008年に公認会計士として有限責任監査法人トーマツに入社し、テクノロジー、メディア、製造業等を中心とした上場会社の監査業務に従事、その間、前職の知識を活かしてIT監査を含むシステム統制を中心とした内部統制の改善提案等を行ってきた。現在は、税理士法人NewRの代表として税理士業務を行いながら、上場子会社のPMIを中心に決算支援や内部統制の構築支援、税務顧問など幅広く業務を行っている。
- ホームページURL
- 税理士法人NewR
免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。