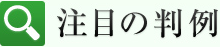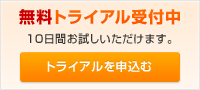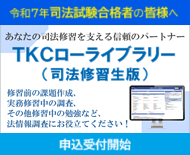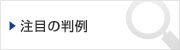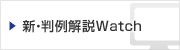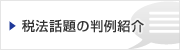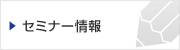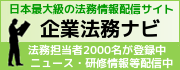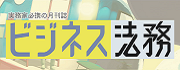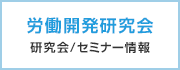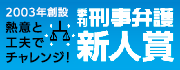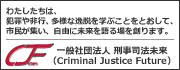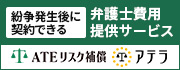2026.02.17
第三者異議事件 

LEX/DB25574744/最高裁判所第三小法廷 令和 8年 1月20日 判決(上告審)/令和5年(受)第2245号
被上告人は弁護士であり、その職務に関して預かり保管する金員を管理するため、みずほ銀行において普通預金口座を開設していたが、上告人は、被上告人に対して婚姻費用の分担金の支払を命ずる審判を債務名義とする強制執行として、被上告人がみずほ銀行に対して有する預金債権の差押えを2回にわたって申し立て、上記各申立てに基づき債権差押命令が発せられ、本件預り金口座に係る預金債権のうち、「被差押金額」の部分が差し押さえられたところ、被上告人が、依頼者からの預り金は、当然に信託財産に属する財産となるから、被上告人を受託者とし、本件預り金を信託財産に属すべきものと定めた信託契約が成立し、本件預り金を原資とする本件預金債権も信託財産に属する財産となるとして、上告人に対し、信託法23条5項の規定による異議に係る訴えを提起し、本件各差押部分に対する前記各強制執行の不許を求め、控訴審が被上告人の請求をいずれも認容すべきものとしたことから、上告人が上告した事案で、当審において、預り金について信託と明示されていたか否か、被上告人が本件預り金を預かり保管した目的、成立するとされる本件信託契約における受益権及び信託事務処理の内容のいずれもが明確にされておらず、そればかりか、依頼者が預り金であると認識して被上告人に金員を預託したのかすら明らかではなく、現在の主張の内容にとどまる限り、信託の目的についての合意はもとより、実効確保の仕組みについての合意があったともいえず、信託契約が成立したとはいえないとして、原判決を破棄し、本件を高等裁判所に差し戻した事例(補足意見、意見あり)。