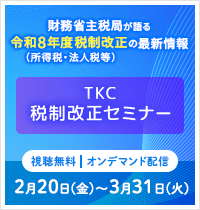更新日 2025.09.16

株式会社TKC
企業情報営業本部 税務システム営業部 税務コンサルティング支援課
2025年2月19日(水)、TKCシステム(ASP1000R、e-TAXグループ通算等)を利用する多くのユーザー企業が課題とする「人材不足」をテーマに、①最新情報を知る、②他社事例を知る、③他社と情報交換する、交流の場としてTKCユーザー会を開催しました。
- 第1部:企業税務の最新動向と人材不足の課題と対策
(講師)PwC税理士法人 - 第2部:パネルディスカッション
(パネリスト)
東レ株式会社 栗原様
鹿島建設株式会社 京極様
長瀬産業株式会社 根岸様
PwC税理士法人 橋本様 - 第3部:参加者によるテーブルディスカッション
さて、今回はユーザー企業事例として、第2部パネルディスカッションで、各社のパネリストが語った「人材不足の課題感や対応策」をご紹介します。なお、以下2点につき予めご了承ください。
- ①記事の中には第1部の講演内容を踏まえた発言、また当日の順番のまま記載しておりますので予めご了承ください。
- ②長瀬産業株式会社 根岸様の講演内容は、当日ご参加された方向けの特別講演となるため、当コラムでは割愛しております。
当コラムのポイント
- 企業税務の最新動向
- 人材不足の課題と対応策の企業事例紹介
- 税務部門の貢献とあるべき税務ガバナンスとは?
- 目次
-
【司会:白土晴久先生(PwC税理士法人)】
皆様の会社では、「人材不足」に対するどのような課題感があるのか、またどのような対応策を取られているのかお話を伺いたいと思います。
1.鹿島建設株式会社 京極剛様
(1) 税務業務に携わる組織の状況
当社の税務業務に携わる人員は、総合職が5名と一般職が2名で、全員プロパーです。2名のうち、1名は秘書なので、実質6名の体制です。総合職の年齢構成は50代が2名、40代が1名、働き盛りの30代が2名です。人数は正直足りないですが、いないことを嘆いてもしょうがないので現在の体制で対応しています。
(2) 国際課税について
さて、先ほどお話した通り連結ベースだと子会社数は313社ですが、タックスヘイブンの対象会社は700社、Pillar2の対象は1,200社となります。当社はゼネコンですので、国内は建設業ですが、海外では開発事業を展開しています。例えば、土地を買い建物を建てますが、建物が物流倉庫だったら小売業などの企業に売る、住宅だったら不動産会社に売る、商業モールだったら投資家や開発系会社に売るなど、建設事業より開発事業が多いです。その場合、プロジェクトごとに会社を作っていくことになりますので、マネジメントをする会社、ファイナンスを付ける会社、事業会社というような構成、また国をまたぐ場合にはそれぞれの国の税制優遇を受けるため、リスクを遮断するために会社が非常に多くなる傾向があります。正直6人では手が回りません。
(3) 外部専門家の活用
対象の700社と1,200社の違いは、まずタックスヘイブンは税率20%未満の軽課税国と米国ではLLCが多いですが、税率の高いフランスやオーストラリアなどの会社は数に含めていないため700社となります。一方、BEPSの方は全世界全て対象会社となるため1,200社になります。このような状況では当社の人員だけではとても対応できないので、業務を完全に外部の専門家に委託しています。例えばタックスヘイブンはA税理士法人、移転価格関係はB税理士法人というように使い分けていますが、ファームで選んでいるわけではなく、人を選んでいます。そのため、その人が違うファームに移ったらその人と契約するかもしれないくらい、あうんの呼吸を重要視しています。
そこで、外部専門家の活用については、基本的にマニュアルをある程度整備していますが、外部に委託する仕事と自社でやる仕事を分けています。仕事を2つに分けて、2つ合わせて初めて仕事が完結するような流れを作っています。外部専門家はプロなので、ある程度信用した上で、社内の人間も出来上がりを確認します。反対に、申告に伴うものなど自社で作ったものは、必要に応じて税理士や税理士法人に見てもらっています。その際、できるだけ社内にノウハウが残る形を意識しています。タックスヘイブンなど、あらかじめ課税が発生しそうな場合は事前に稟議書などを見せてもらうようルートを構築して対応できますが、それでも防げない場合は税理士法人に「こういうところで課税が起きそうですがどうですか?どうやったらいいでしょうか?」とアドバイスをもらうようにしています。外部に委託すると、社内のノウハウが溜まるだけでなくて、例えばどうやったら効率よく税制優遇を取れるかなど、社員は税務戦略等に知恵を使うことが出来ますので、そういった意味から外部専門家の活用は悪くない、我々社員のレベルアップにもつながっているという意識を持っています。
(4) 人材育成の過程や人事ローテーションについて
次に人材育成についてです。税務ではやはり税務調査を受けて国税の考え方を学び、状況に応じて反論等をするような経験値を高めることが必要だと思っています。税務というと専門知識がないとできないようなイメージをお持ちだと思いますが、私の考えは専門知識よりも経験値、専門的な経験値の方がよっぽど重要だと考えています。先ほどゼネラリストの話がありましたが、3年から5年で異動する人を育てていても、いずれいなくなるかもしれません。従って、全ての専門知識を習得できないことを前提に、分からないところや専門的なところは外部専門家に任せてしまうという割り切りでも良いと思います。私としては、税務調査の経験値こそが、人材育成にもつながっていくイメージを持っています。
人事ローテーションについては、他の会社と変わらず5年をめどに一般的な経験を積むようにしています。私は22年もいますが、他の社員は基本的に5年前後でローテーションを進めています。今の課題としては、経営戦略があるように、税務戦略もあってしかるべきだと思いますので、経営戦略に合った税務戦略を理解できる人が必要と考えています。私も税務の考え方をTKCのシステムから学びました。小さい会社を担当して、TKCのシステムに入力して、ここの数値が別表4、別表5のどこに飛ぶのかなど、税務の申告書そのものを理解しました。育成という意味では小さい会社から経験値を積んで理解していくというのは必要なプロセスだと思います。別の勉強会で教わったことですが、本来は税務ガバナンスがあって、それを理解した上で税務戦略やどう節税できるのか、タックスプランなどを考えていくべきで、税務の土台がないとダメなんだろうなと思っています。土台があってこそ最終的に申告書に反映させることが本来あるべき姿だと考えています。また、実は税務には営業的な要素があると思っています。ここでいう営業とは、コミュニケーション能力を指しています。税務、即ち申告の有無を判断するための情報を全ての部署からどのような方法で入手するかが非常に大切です。先程、税務ガバナンスの話をしましたが、税務ガバナンスを整えるためには、川上から川下まで社内の仕組みを理解した上で、どこに課税の問題があるかを把握しないと正しい申告書は書けません。そういう意味では、コミュニケーション能力さえあれば、税務的な業務は誰でも務まるのではないかというのが私の持論です。
(5) 税務マネジメントの評価
最後に、税務マネジメントの評価についてですが、局の調査課所管法人であれば、税務に関するコーポレートガバナンスにおいてA、B、C評価が一つの客観的な目安になると思います。Aを目指しているけど、残念ながらBになる年もあるでしょう。それが税務グループとしては社内的にも社外的にも言えるレベルのものとして、一つの評価基準として励みにしています。
この連載の記事
-
2025.09.16
第1回 イントロダクション
-
2025.09.16
第2回 人材不足の課題と対応策(その1)
-
2025.09.16
第3回 人材不足の課題と対応策(その2)
-
2025.09.16
第4回 参加者からの事前質問への回答(その1)
-
2025.09.16
第5回(最終回) 参加者からの事前質問への回答(その2)
テーマ
プロフィール

株式会社TKC
企業情報営業本部 税務システム営業部 税務コンサルティング支援課
免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。