更新日 2010.10.12
税理士・公認会計士 中野伸也
税理士・公認会計士 妙中茂樹
はじめに
武田昌輔教授によれば、法人の清算所得に対する課税はシャウプ勧告により廃止されたものが昭和28年に復活して以来のものだという(『法人税回顧六〇年』TKC出版年15頁)。それが平成22年度の税制改正によって廃止された。実に57年ぶりの制度改正ということになる。なお、清算所得課税が廃止されるのは平成22年10月1日以降の解散であり、平成22年9月30日以前の解散については、なお従前どおりの清算所得課税が適用される。
税制改正大綱では明確になっていなかった点も、政令により明らかになっている。以下、解説を加えながら、実務において考慮すべき点、問題となる点などを考えてみたい。
従来の清算所得課税制度と税制改正の概要
従来の清算所得課税制度の概要は、次のようなものであった。
- 法人が解散すると解散した日を境として、解散の日までは各事業年度の所得に対する課税であり、解散の日の翌日以降は清算所得課税となるため、本来の事業年度開始の日から解散の日までを事業年度(みなし事業年度)とする。
- 課税対象が異なることになるので、連結納税法人が解散すると、その時点で連結納税グループから離脱する。
- 清算所得の金額は、次の算式により求め、事業税を考慮した法人税率27.1%を乗ずる。
【残余財産の価額-(解散時の資本金等の額+解散時の利益積立金額等)】 - 清算所得がゼロ以下の場合は課税されない。そのため、多額の期限切れの繰越欠損金を有する会社が不動産の含み益を実現させても、法人税が課されない場合がある。
- 解散時の資本金等の額を超える残余財産の分配は、配当等との額とみなされる。
今回の税制改正により、清算所得課税は廃止され、法人の解散後も残余財産確定までは、各事業年度の所得に対する課税を行うこととされた(法法5)。
主要なポイントごとに、連結法人、グループ法人、非グループ法人の別に適用の有無等をまとめたものが図表1である。連結法人とグループ法人では、解散によるみなし事業年度があるかないかが大きな違いであり、その他は基本的に同一の制度となっている。これは今回の改正が、法人の解散も組織再編の一部であり、組織再編(=解散)により特段の課税関係を生じさせないようにするという趣旨によるものである。改正条文もその観点で読んでいくと、理解しやすくなっている。
| 連結法人 | グループ法人 | 非グループ法人 | |
|---|---|---|---|
| 解散によるみなし事業年度 |
なし
|
あり
|
あり
|
| 残余財産確定時のみなし事業年度 |
あり
|
あり
|
あり
|
| 期限切れ欠損金の損金算入 |
適用あり
|
適用あり
|
適用あり
|
| 残余財産の分配 |
適格現物分配
|
適格現物分配
|
非適格分配
|
| (現物分配の資産譲渡損益) |
計上しない
|
計上しない
|
計上する
|
| 欠損金の引継ぎ |
可能
|
可能
|
不可
|
みなし事業年度
(1) 連結子法人のみなし事業年度
連結納税の承認の取消し等の事由としての連結子法人の解散は「合併又は破産手続きの開始決定による解散に限る」(法法4の5②四)となり、みなし事業年度の規定(法法14条①一)において、「内国法人(連結子法人を除く。)」と改められたので、連結子法人は解散(破産による場合を除く)しても、みなし事業年度を設けずに通常の計算を続けていくことになる。ただし、解散した連結子法人が連結事業年度の中途において残余財産を確定した場合は、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までを1事業年度とみなし(法法14条①十)、連結法人として単体申告を行う。
連結会計においては、解散が必ずしも連結範囲からの離脱事由にはならない(「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の留意点についてのQ&A」Q4)ので、今回の改正により会計連結時の調整が不要になる利点があると思われる。
連結納税親法人が解散した場合に連結納税の承認取消しとみなす規定(法法4の5②三)に変更はないので、親法人が解散した場合はみなし事業年度を設けて、最後の連結納税申告後に各法人は単体申告に移行する。
(2)その他の会社(グループ法人、非グループ法人)
解散によるみなし事業年度の改正によって除かれたのは、連結子法人だけなので、それ以外の会社が解散した場合はみなし事業年度を設けて申告を行い、清算結了までは清算事務年度(会494)ごとに通常の申告納付を行っていくことになる。
なお蛇足ながら、会社が破産手続きに入った場合は会社法の適用からはずれるので、みなし事業年度は清算事務年度ではなく、法人税法の規定(法法14①一)により本来の事業年度(定款に定める事業年度)ごとに区切られる。
期限切れ欠損金の損金算入
清算所得課税の廃止に伴い、従前の財産法による所得計算では課税されなかった債務免除益等への課税を防ぐということから、残余財産がないと見込まれるときの期限切れ繰越欠損金の損金算入を所得金額(青色欠損金等の控除後で、最終事業年度の事業税の損金算入前)を限度として認めることとなった(法法59③,法令118)。
しかしながら、完全支配関係を有する法人においては後述する残余財産の適用現物分配と青色欠損金等の引継ぎにより、この制度を利用する場面は非グループ法人の場合に比べて少ないと思われる。
残余財産がないと見込まれるときとは、清算中の各事業年度終了の時に清算結了時に利益積立金がマイナスになると見込まれる状態をいう。すなわち残余財産確定時(債務免除を受ける前)に負債の額が資産の額より大きい場合である。
図表2に、改正前の清算所得課税の計算方法と改正後の損益所得計算方法による場合の計算とを比較している。最終結果は同じであるが、従前は利益積立金がマイナスなので清算所得なしというものであったのに対し、改正後は所得200に対し、青色欠損金控除100、期限切れ欠損金控除100により所得がゼロとなるものである。
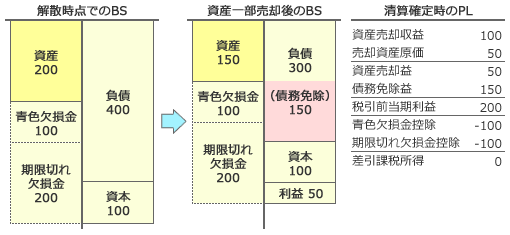
残余財産の分配等
清算所得課税がなくなったため、残余財産の分配または引渡し時には、移転する資産の残余財産確定時の価額で譲渡をしたものとして、その事業年度の所得の金額を計算することとなった(法法62の5①・②)。
ただし、完全支配関係がある内国法人の間で行われる現物分配等については組織再編税制の一環として位置づけ「適格現物分配」(法法2十二の十五)としてその移転する資産を帳簿価額により譲渡したものとして譲渡損益を計上しない(法法62の5③)し、源泉徴収も行わない(所法24①)。この規定はグループ法人間の譲渡損益資産の繰延べとは異なり、損益を認識したうえでの繰延ではなく、帳簿価額を引き継ぐものであり、適用資産が限定されているわけでもないので、少額な資産でも棚卸資産でも適用される。
また、完全支配関係がある法人では解散した会社の資産等を「適格現物分配」により親会社がそのまま引き継ぐのであれば、従来の清算会社では認められていなかった貸倒引当金の損金算入ができるし、親会社は貸倒引当金をそのまま引き継ぐ(法法52⑤・⑥・⑧)。同様に残余財産確定事業年度でも圧縮記帳が可能であり(法法42⑤等)、返品調整引当金、非適格合併等の調整勘定、長期割賦販売、工事進行基準、一括償却資産なども引き継ぐことになる。
以上の引き継ぎは「適格現物分配」に限られるので、「適格現物分配」に該当しない場合(非グループ法人)は前述したように時価による譲渡となり、残余財産確定事業年度での引当金設定等が認められないことはいうまでもない。
本文は『旬刊経理情報(6月1日号No.1249)』に掲載された記事の転載となります。
筆者紹介(中野伸也)
税理士・公認会計士 中野伸也(なかの しんや)
TKC連結納税システム推進プロジェクト会員
TKC企業グループ税務システム小委員会委員長
ホームページURL
中野会計事務所
筆者紹介(妙中茂樹)
税理士・公認会計士 妙中茂樹(たえなか しげき)
TKC連結納税システム推進プロジェクト会員
TKC企業グループ税務システム小委員会委員
著書
『会社の税金 実務必携』(共著、清文社)
ホームページURL
妙中公認会計士事務所
TKC連結納税システム推進プロジェクトとは
TKC全国会は、全国1万名を超える税理士・公認会計士による我が国最大の職業会計人集団です。株式会社TKCでは連結納税制度に対応した連結納税システム(eConsoliTax)を平成15年6月に提供開始し、平成22年6月現在で420グループ4,590社の利用実績があります。
TKC全国会では、平成15年に、システムの円滑な立上げと、その運用を支援する「連結納税システム推進プロジェクト」を発足させ、連結納税制度を適用した企業に対するコンサルティングを全国展開しています。
免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。














