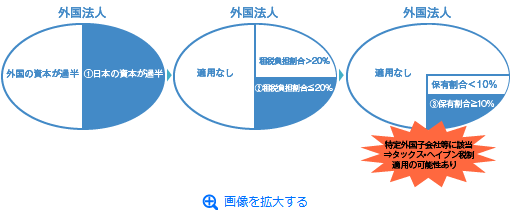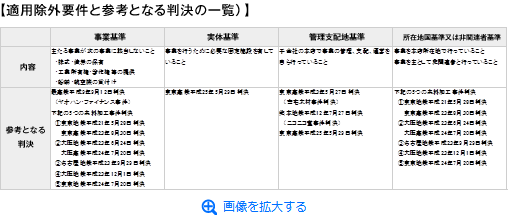更新日 2014.03.10

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
税理士・中小企業診断士 西村 道浩
グローバル展開する企業にとって、国際税務の知識は必須です。このコラムでは、海外進出から撤退の段階別に、関連する国際税務の個別論点を取り上げ解説いたします。
第4回は、②海外オペレーション時(海外事業のライフ・サイクルにおける"成長期・成熟期"に相当)における国際税務の主要論点の1つであるタックス・ヘイブン税制について検討します。
Ⅰ 最近の国内・外におけるタックス・ヘイブン税制による課税強化の方向性
前回の連載では、外国子会社配当益金不算入制度の導入以降、日本の税務当局は外国子会社から日本の親会社への配当還流時に従来のような追加課税を行うことが難しくなったことにより、外国子会社が利益を配当還流する段階ではなく、利益を計上した段階における(移転価格税制やタックス・ヘイブン税制による)課税の強化を行っている方向性を確認しました。
また、比較的最近の話題としてBEPS(税源浸食と利益移転)問題があります。BEPSとは、多国籍企業が各国の税制優遇措置や租税条約を組み合わせたタックス・プランニングにより、グローバルな租税負担の軽減を図っているという問題です。2013年には、アマゾンやスターバックスなどが徹底したタックス・プランニングにより世界中のどこでも税金を払わない"二重非課税"を図っているとして社会問題となりました。こうした多国籍企業の行動に対する社会的不公平感の高まりを受け、OECD租税委員会は2013年7月にBEPS撲滅に向けた15項目の行動計画を公表しましたが、その中には『外国子会社合算税制(我が国のタックス・ヘイブン税制に相当)の強化』も含まれています。
II タックス・ヘイブン税制とは
タックス・ヘイブン税制とは、低税率の国にある外国子会社を利用した租税回避行為を防止することを目的として、低税率国の外国子会社の所得を日本の親会社の所得と合算して課税する制度です。下図の通り、外国法人のうち、①日本資本が過半を占め、②『租税負担割合』が20%以下である、ものの株式を③10%以上保有している場合(下図の一番右の青塗部分)には、『特定外国子会社』に該当し、タックス・ヘイブン税制の適用を受ける可能性があります。
次の例で、日本の親会社(利益1,000、実効税率40%、外国税額控除を全額とれることとする)、外国子会社(利益500、現地実効税率23%、親会社に配当しない方針を採用)という前提で、タックス・ヘイブン税制の適用のあり・なしによる日本の親会社における法人税負担額と連結実効税率を比較してみましょう。
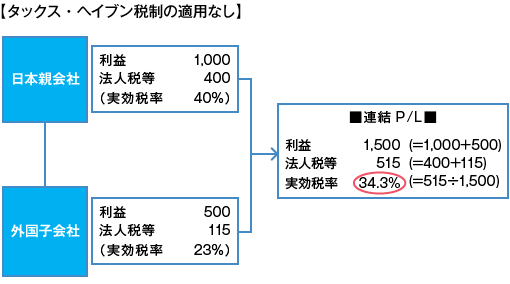
外国子会社の税率が23%と日本の実効税率より低く、日本の親会社へ配当しない方針を採用しているため留保利益に係る税効果を認識しないことから、外国子会社の税率と日本の法定実効税率との税率差5.7%(=500x(40% - 23%)÷1,500)を享受して、グループ全体の実効税率は34.3%(=515÷1,500)となっています。
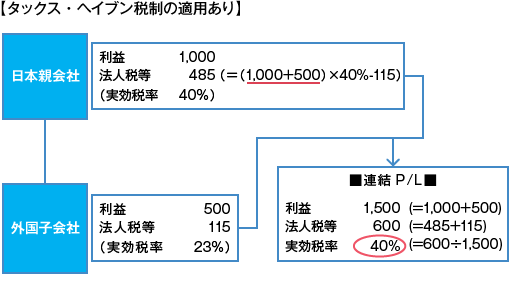
一方、タックス・ヘイブン税制の適用がある場合には、外国子会社の利益500が日本の親会社の利益1,000に合算されて課税され、法人税等が85(=500x40%-115)増加する結果、グループ全体の実効税率は40%(=600÷1,500)となっています。 つまり、先ほど見た外国子会社の税率と日本の法定実効税率との税率差5.7%がなくなり、日本の法定実効税率である40%に収斂します。
III タックス・ヘイブン税制による課税が連結実効税率に与える影響
タックス・ヘイブン税制による課税が行われると、多額の税金費用が追加計上されることになりますので、上記Ⅱで見た通り、連結実効税率は上昇(結果、ROEは低下)することになります。また、それに伴い連結実効税率の大幅な上昇があると、親会社の連結実効税率と法定実効税率との差異の原因として、連結財務諸表の注記により開示されることになります。
実際にタックス・ヘイブン税制の適用を受けた企業の事例で、移転価格課税に伴う連結財務諸表及びROEへの影響を検証してみましょう。
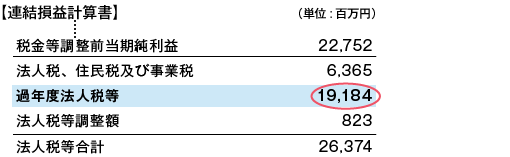
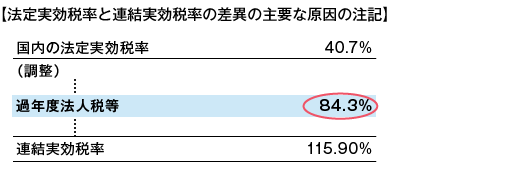
事例企業では、外国子会社がタックス・ヘイブン税制の適用除外要件を満たしていないものとして、過去3年間の外国子会社の所得を日本の親会社の所得と合算して課税されました。連結損益計算書上では、日本の親会社の追徴税額及び附帯税額の合計額(19,184百万円)が過年度法人税等として計上され、結果として、連結実効税率は115.90%(前期比89.5%増)に上昇し、ROEは△1.9%(前期比13.51%減)まで低下しました。
タックス・ヘイブン税制による申告漏れ件数は年間100件を超えますが、そのほとんどは悪質な不正脱漏ではなく、単純な計算誤りや制度(特に、適用除外要件)に対する認識不足によるものだと言われています。適用除外要件の充足の判断など事実認定に係るケースでは『見解の相違』として、事例企業の様に、過年度法人税等などの損益計算書科目で追徴税額等の引当てを行うことになりますが、単純な計算誤りなど『過去の誤謬』に該当するケースでは、訂正報告書の提出が必要になる(過年度遡及会計基準21、金融商品取引法第24条の2)など留意が必要です。
IV タックス・ヘイブン税制による課税リスクへの対応
単純な計算誤りや制度に対する認識不足による課税が多いと言われているタックス・ヘイブン税制ですが、その主要な要因である『租税負担割合』と『適用除外要件』について以下で確認しましょう。
i) 租税負担割合
下図は主要国の法人税率をグラフにしたものですが、アジアでは香港、台湾、シンガポール、ヨーロッパではアイルランド、ハンガリー、ポーランド、チェコなどが、法人税率で20%以下となっています。
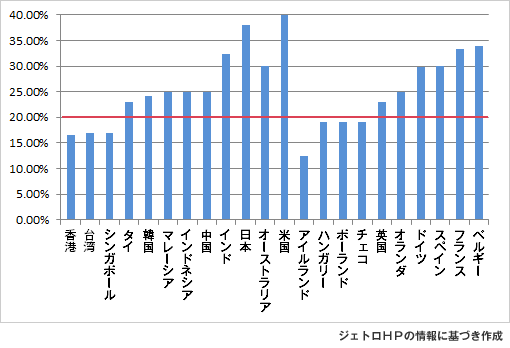
タックス・ヘイブン税制上の『租税負担割合』は、上記の法人税率ではなく、事業年度ごとに、下記の算式により計算することになります。その際、分母の外国子会社の課税所得には"非課税所得"を加味することから、その国の法人税率が20%超であっても、"非課税所得"が多額に生じた事業年度では租税負担割合が20%以下となることがあるため留意が必要です。
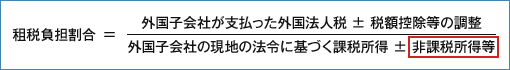
例えば、オランダの法人税率は25%ですが、資本参加免税の要件に該当するキャピタル・ゲインはオランダで非課税とされるため、分母に"非課税所得"として加算された結果、租税負担割合が20%以下となる可能性があります。
また、外国子会社がその所在地国で合併や分割などの組織再編を行った場合に、その国の組織再編税制等により資産の移転に係る譲渡益が課税されないことがありますが、これを租税負担割合の計算上"非課税所得"に含めるべきか否かという問題が生じます。そのため、法人税率が20%超の国にある外国子会社であっても、組織再編成を行う場合には留意が必要です。
ii) 適用除外要件
タックス・ヘイブン税制には『適用除外要件』があります。外国子会社が『特定外国子会社等』に該当する場合でも、適用除外要件を充足すれば、その所在地国で事業を行う経済的合理性を有するものとしてタックス・ヘイブン税制が適用されません。
適用除外要件の充足に係る判定は事実認定の問題であるため、後の税務調査で問題となることが多いことから、適用除外要件の充足が争点となった過去の判決等(下図参照)に基づいてポリシーを決定し、それぞれの基準を満たしていることを説明できる資料を準備しておくことが重要です。
IV まとめ
タックス・ヘイブン税制による課税は、多額の追徴課税が発生することから、連結実効税率及びROEへの影響が非常に大きく、課税のリスクが顕在化する前からの本社主導によるグローバル税務管理が重要だと言えるでしょう。
日本の本社では、最低限、①特定外国子会社に該当しないか、②外国子会社の租税負担割合が20%以下とならないか、③適用除外要件を充足しているか、について継続的にモニタリングしておくことが重要です。
参考文献
- 大河原健、須藤一郎 『国際取引のグループ戦略』 東洋経済新報社
- 仲谷栄一郎、井上康一、梅辻雅春、藍原滋 『外国企業との取引と税務(第4版)』 商事法務研究会
- 佐和周・菅健一郎『タックス・ヘイブン税制Q&A』中央経済社
- 手塚仙夫 『税効果会計の実務(第8版)』 清文社
- 月刊国際税務 2014年1月号 『OECDにおける最近の議論-BEPSを中心に』
- 月刊国際税務 2013年7月号 太田洋・北村導人 『実体基準・管理支配基準に関する東京高裁平成25年5月29日判決の検討』
プロフィール
税理士・中小企業診断士 西村 道浩(にしむら みちひろ)
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
ホームページURL
西村&パートナーズ総合会計事務所
免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。