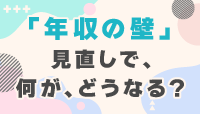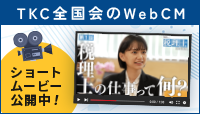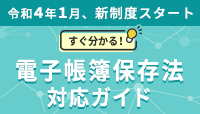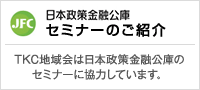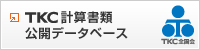- 目次
-
昨年10月末の時点で、日本で働く外国人労働者の数は前期比12.4%増の約230万人に達し、過去最高を更新した。人手不足を補う主要な働き手になりつつある外国人材の採用や戦力化のノウハウについて、最新事情や事例を取材した。
- プロフィール
- なかむら・だいすけ●1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年近畿大学経営学部卒業。フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う上場企業、外国人労働者の求人サービスを手掛けるスタートアップを経て21年にジンザイベースを創業。

まず図1(『戦略経営者』2025年5月号P7)をご覧ください。在留資格別の外国人労働者数の推移を示したものです。厚生労働省の2024年10月末時点のデータによると、外国人労働者数は過去最多となる230万2,587人に達しており、前年同月比で12.4%増加しています。
産業別では製造業が全体の27.0%(62万2,992人)を占めて最も多く、次いでサービス業(18.6%)、卸売・小売業(12.9%)と続いています。また、増加率では建設業が前年比24.0%増と最も高く、外国人労働者の受け入れが加速しています。特に製造業や建設業では、「技能実習」および19年に制度化された「特定技能」ビザでの就労が多く見られます。
ここで、在留資格について簡単に整理しておきましょう。日本で就労が可能な在留資格は29種類あり、それぞれに認められた活動範囲が厳格に定められています(『戦略経営者』2025年5月号P8図2)。これを逸脱した就労は不法就労に該当し、本人には退去強制、雇用主には不法就労助長罪(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)が適用されます。採用時は必ず在留カードを確認し、在留資格と就労内容の適合を確認することが必要です。
実務上、特に押さえておきたい在留資格は特定技能1号、技能実習、「技術・人文知識・国際業務(技・人・国)」の3種類です(『戦略経営者』2025年5月号P8図3)。建設業、外食業、宿泊業といった現場作業系は特定技能または技能実習、一方でホワイトカラー業務に従事する場合は技・人・国に該当するケースが多くなります。
特定技能1号は最長5年までの在留が可能で、家族の帯同は不可。取得方法は2通りあり、(1)日本語能力試験N4(目安は「基本的な日本語が理解できる」)以上の合格+業種別の技能評価試験合格、(2)同職種での技能実習修了者(この場合、日本語試験は不要)です。特定技能2号は無期限の在留が可能で、家族の帯同も認められています。現在は建設業など2分野でのみ取得可能ですが、今後さらに拡大される見込みです(直近ではトラック運転業務が追加)。
技・人・国は、大学・専門学校・日本語学校を卒業した方が対象で、在留更新が可能であり、家族帯同も認められています。長期間の就労や定着を見込む際に適した資格です。
技能実習は27年に廃止が予定されています。現行では1〜3号があり、最長5年間の就労が可能ですが、特定技能などに比べて定着性に欠けることが課題です。なお、技能実習から特定技能1号への移行は同一職種での3年以上の経験があれば可能です。
求職者急増で大チャンス
図4(『戦略経営者』2025年5月号P9)は外国人労働者数の国籍別人数です。ベトナムが最も多く(約57万人)、次いで中国(約41万人)、フィリピン(約24万人)と続いています。ただし、ベトナム人の比率は微減傾向にあり、背景には日本の労働条件が他国(韓国、台湾等)と比較して必ずしも魅力的でないことが挙げられます。そのため、今後注目されるのはインドネシア、ミャンマー、ネパール、スリランカ、インドなど「ネクスト・ベトナム」とされる国々ですが、出身国にとらわれず、人物本位の採用を行うことが重要です。
ちなみに今後2〜3年は求職者数が急増する見込みです。技能実習制度の廃止にともない、2号・3号修了者が一斉に特定技能へと切り替わることで、国内在住の外国人労働者が大幅に増加する見込みだからです。特定技能制度自体も拡大が進められており、政府は今後80万人規模への成長を目標に掲げています。また、24年4月からは特定技能2号において介護分野での訪問介護が解禁され、家族帯同も可能となったことで、さらなる定着促進が期待されます。
このような状況を踏まえ、外国人材の採用においては以下の6点がポイントとなります。
- まずは日本国内に居住する外国人を優先的に採用する
- 可能であれば日本語能力が高い人材を選ぶ
- それが難しい場合は海外での採用も視野に入れる
- 出身国で判断せず、人物重視の面接を行う
- ネガティブに受け取られる可能性がある情報は事前に伝える
- 明確かつ魅力的な給与条件を提示する
特に国内在住者の採用は、リードタイムの短縮、面接精度の向上、文化的適応のしやすさといったメリットがあります。海外からの招聘の場合、入国までに3〜6カ月かかることも多く、コストやミスマッチリスクも高まります。なお、技能実習制度の廃止にともなって創設予定の「育成就労」制度は、詳細が未確定であるうえ、2年目からの転職が可能、企業側のコスト負担が大きい等の課題があり、当面は特定技能の活用が現実的と考えられます。
今後、特定技能2号取得を見据えた採用では、語学力の有無がカギを握ります。移行には業種ごとの試験に合格する必要があり、日本語能力試験N3(目安は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」)レベル以上の読み書きが求められるケースがほとんどです。
最近では日本語を独学で学び、N2(目安は「日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる」)以上の力を持つ人材も増えています。SNSやユーチューブを通じた情報収集力の高まり、オンライン学習環境の普及により、語学力の高い求職者は確実に増加傾向にあります。特に都心部の中小企業では、こうした人材をいち早く採用できるチャンスが広がっています。国内採用が難しい場合は、海外で日本語を学んだ人材や、技能実習経験者の中から特定技能の要件を満たす人材に注目するのがよいでしょう。
給与は「額面」で勝負
外国人材の転職市場では、求人の比較ポイントは「時給」よりも「額面金額」です。特に残業代を含めた給与総額での比較が一般的となっており、「残業が少ない」は訴求ポイントになりにくいでしょう。
例えば、都心部の外食業では月額約30万円(残業40〜50時間含む)、介護業では夜勤や加算込みで約28万円、建設業は30万円前後以上が目安です。
地方にあり、こうした水準を提示するのが難しい企業は、資格取得支援や研修制度の充実など、「成長できる環境」を提供することで差別化が可能です。特に介護業では、入社3年後に介護福祉士取得に向けた実務者研修が始まるため、その費用やスケジュール調整などの支援を打ち出すことが効果的です。
最後に、外国人材が転職活動において最も重視するのは「採用までのスピード」です。多くの求職者が在留資格の更新期限ギリギリで動いており、内定が早い企業から決まっていく傾向があります。この点では、大企業よりも意思決定の早い中小企業に優位性があると言えるでしょう。
(構成/本誌・植松啓介)