地域の中核大学が持つ「知」の資産を中小企業が有効活用する「産学連携」。地方創生の実現が声高に叫ばれる昨今、その重要性はこれまで以上に高まっている。産学連携による新事業・商品創出の試みについて最新事情をレポートする。
- プロフィール
- いとう・まさみ 群馬大学共同研究イノベーションセンター教授。特定非営利活動法人産学連携学会前会長。「大学における研究と教育活動の領域において成り立つ産学連携の成果を出す」を基本的スタンスに年間30件程度の共同研究プロジェクトに携わっている。
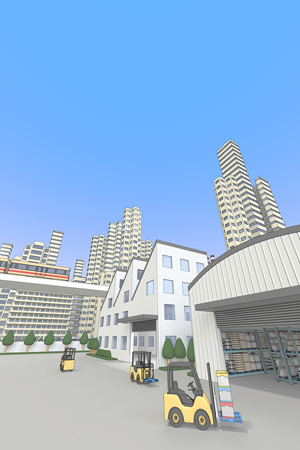
産業界側から大学に対する、産学連携への関心は今まで以上に高くなっている。しかしその割合は、製造業を担う中小企業で3%、研究開発機能を持つ中小企業でも30%程度。中小企業の産学連携は到底一般化しているとは言えない水準だ。これは大学と企業側双方にさまざまな制約条件が存在するからである。そもそもすべての企業が産学連携に適しているわけではない。産学連携が成立する企業の必要条件とはなんだろうか。
第1は、経営者に新事業創出の意欲があるということ。新製品に挑戦するということでなくても、既存の設備の改良でもっと付加価値の高いものを作りたい、原価を低減し利益を高めたいなどといった経営を改善しようとする経営者の強い気持ちがなければ産学連携は決して成功しない。
言わずもがなだが、2番目に必要なのは経営資源に余裕があるということ。決算内容が悪い会社に共同研究を持続させる体力はないからである。ここまでは必須条件だ。それから経営者の人柄や資質も重要である。大学は研究委託会社ではない。そもそも企業社会とは異質の世界に存在している組織である。そのあたりの事情をきちんと受け止められる経営者の人柄が連携の成否を左右する大きな要因になるだろう。
主体的に事業化のプランを
また大学のパフォーマンスを的確に理解・評価するということも大切だ。買い物をするときは普通品物の価値を評価してお金を払う。大学との連携も同様だ。企業は実際のところ大学に研究資金を提供して自社の研究開発に役立てるわけで、そのためには大学内の知的な資産についてその価値を正しく評価できる力が必要である。これが難しければ、信頼のおけるコーディネーター役の第三者が間に入ることで、その価値の評価を担保することができる場合もある。
最後は、企業が主体的に研究開発や事業化のプランを企画することである。大学に研究開発を丸投げするなどということは論外として、少なくとも「やってほしいこと」をきちんと説明できなければならない。そうしないとプロジェクトの照準がどうしてもずれてしまい、かなりの確率で残念な結果に終わる。
一般的に研究開発活動から事業化に至るプロセスは、基礎技術の醸成を担う「研究」、マーケティングなどを通じて仕様を絞り込んだ「開発」、実際に市場投入する「事業化」、継続的な商品投入や拡大戦略を含む「産業化」と段階を踏んで進んで行く。中小企業はこのうち「開発」から「事業化」までに関わることが多いが、大学の教員がそのすべてのプロセスに関与できるかというとそうではないケースがほとんど。したがってかなりの割合で中小企業が持ち込んだ製品について大学が評価・検証を行うというタイプの共同研究が多くなる。経営者は研究テーマを見て連携先を選ぶのではなく、あらかじめ「こんなことをやりたい」「こんな課題がある」とストレートにニーズをぶつけるべきだ。そしてそれに対し大学側が専門性に基づいて解決手段を提案するという流れが最もスムーズだが、企業側の「やりたいこと」を大学教員に「翻訳」して伝えるコーディネーターの力が必要になる場合もある。
「実現可能」の異なる意味
もちろん大学側にも産学連携についての必要条件がある。教員の専門性が連携に適しているかどうか、企業の文化や行動様式を理解しているかどうかといった事柄である。中でも学生が共同研究プロジェクトに関わった場合には注意を促しておきたい。大企業であれば産学連携で社員を派遣し大学に常駐させるようなことも行われるが中小企業ではまずありえない。必然的に学生がプロジェクトに参加するわけだが、大学教員は、企業との共同研究が学生の卒業論文や修士論文の研究対象として適切かどうかという教育的配慮をするのが一般的である。「大学の研究スピードが遅い」と経営者が嘆く声も聞かれるが、実際に手を動かしているのは学生であることを理解する必要があるだろう。
さらに産学官それぞれの目的意識が異なることも成功を阻む要因として挙げられる。企業は大学をツールとして使って自社の研究開発を促進し、事業化を通じて成長させるのが目標だ。しかし大学は産業界との連携による外部資金の獲得、研究教育活動の活性化が狙いである。さらに官は最終的には雇用の創出と税収の増大を期待する。それぞれのプレーヤーが異なる目的で行動し自分の目的ばかりを押し付けようとすると関係性にきしみが生じてしまうことを認識しておく必要があるだろう。
そこで必要となるのが、目的意識の違いをすり合わせる調整能力である。専門のコーディネーターがいればベストだが、経営者や大学の先生でその役割をこなせる人もいる。私の経験から言えば、人格的に幅広い、相手の立場をわきまえて行動できるタイプの経営者が調整能力を発揮して成果を出している成功事例が多い。
調整機能で代表的なものは、コミュニケーションギャップを埋めることである。特定のテーマで共同研究を行うにもかかわらず、同じ言葉の意味が産学で異なる場合は多く、成果や時間、コストなどを含めたプロジェクト全体の到達点についてのイメージを共有していると思い込んだままプロジェクトが進行してしまうのが一番怖い。例えば「実現可能」という言葉の意味は産学で異なる場合がある。大学教員は「原理的に可能」ということだと考えるのに対し、経営者は「商業的に可能」と捉えるのである。この違いはビジネスにとって決定的である。こうしたコミュニケーションギャップは極力小さくしなければならない。
産学連携が成り立つための条件をまとめよう。まずテーマそのものが科学的技術的見地から見てリーズナブルで大学側が研究を行えると判断できるものであること。そして企業と大学両サイドに存在するそれぞれの条件が整うこと。さらに産と学双方の関係性の調整機能があり、プロジェクトを行う上での相互理解ができているときに初めて産学連携成功へのスタートラインに立てるのである。
コーディネーター役の重要性
参考になるような成功事例を2つご紹介しよう。いずれも産学連携をきっかけに中小企業が大きく成長したケースである。一つは長野県に本社を置くタカノ。今では売上高300億円を超える東証一部上場企業だが、もともとはばねや椅子の製造販売を手がける20億円規模の中小企業だった。それが産学連携による新規事業を次々に成功させ、画像検査装置やアクチュエーター、レーザー加工機製造などの分野に参入、10年間で売上高を10倍以上に飛躍させたのである。今では食品や福祉器具などにも事業展開しており、通常これだけ手を広げれば手痛い目にも合いそうだが、産学連携を上手に活用しながら成長を続けている。
次は群馬県のアタゴ製作所。産学連携を開始したのは2000年度のことである。ガス湯沸かし器大手メーカーの協力企業として熱交換器を製造していたが、メーン商品の市場縮小に伴い新たな製品開発の必要性に迫られていた。そこで同社はコア技術であるロウ付けの技術を強化し、産学連携でその性能を徹底的に評価した。その結果、急速に市場が拡大したヒートポンプ給湯機向けで新規顧客開拓が成功、売上高を2倍に伸ばすまでになった。産学連携で実現した売り上げは全体の6割近くを占めている。
両社に共通していえることは、企業側に連携のコーディネーター役もできるキーパーソンがいたということ。タカノは当時の経営者だった堀井朝運(あさかず)氏のリーダーシップが大きな役割を果たしたし、アタゴ製作所には大手メーカー出身で研究者と渡り合えるような専門知識を持つベテランエンジニアが顧問として交渉を上手くハンドリングしていた。このような人材がいればより成果を出しやすくなると言えるだろう。
(本誌・植松啓介)













