事務所経営
「会計事務所の経営革新」検討プロジェクトメンバーが語る税理士の「近未来のあるべき姿」を目指して(前編)
- 目次
-
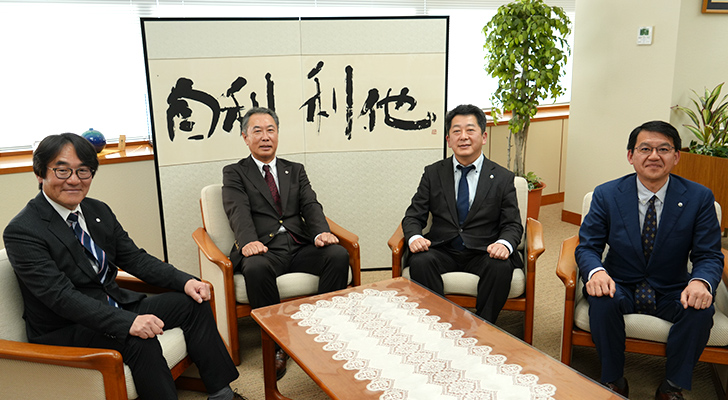
- ■出席者(左から)
- 佐藤 正行会員(サブリーダ、全国会副会長、近畿京滋会会長)
原田 伸宏会員(プロジェクトリーダ、全国会副会長、関東信越会会長)
吉野 太会員(手引き(テキスト)制作チームリーダ、全国会巡回監査・事務所経営委員長)
松﨑 太朗会員(ビジュアル化検討チームリーダ、全国会中小企業支援委員長)
TKC全国会は、6年間にわたる新たな運動方針に基づく活動を展開する。この運動の要となる〈近未来の巡回監査〉のあり方を検討してきた「会計事務所の経営革新」検討プロジェクトメンバーから4名の会員が集まり座談会を開催した。その模様を2回に分けて掲載する。前編の今回は、プロジェクトの成果物であるテキスト『TKC会計人 業務の未来設計』とコンセプトムービー「税理士の未来」の制作過程におけるエピソードを中心に語り合っていただいた。司会は、プロジェクトリーダの原田伸宏全国会副会長が務めた。
有効な一手を早急に打つ必要があるその決め手が〈近未来の巡回監査〉
原田(司会) この1月17日に開催された令和7年のTKC全国会政策発表会において、坂本孝司全国会会長が新たな運動方針を発表されました(「会計事務所の経営革新 税理士の4大業務を完遂し、中小企業を元気にしよう!──月次決算体制の構築がすべての基本」)。この方針に沿って向こう6年間(2025年~2030年)、税理士の未来を切り拓く運動をオールTKCの総力を挙げて展開していくことになります。
そこで本日は、運動の要となる〈近未来の巡回監査〉のあり方を検討してきた「会計事務所の経営革新」検討プロジェクトメンバーから、私も含めて4名が
集まり、プロジェクトの振り返りと、新たな運動方針への意気込みなどを語り合いたいと思います。それでは本題に入る前に、自己紹介を兼ねて、ご自身の事務所経営や関与先支援への思いをお一人ずつお話しください。

司会/原田伸宏会員
佐藤 TKC近畿京滋会の会長を務めています佐藤です。まず私の事務所経営についてですが、当然皆さんと一緒で、TKC理念に基づく諸施策を開業以来27年間、一つ一つ積み上げてきたつもりです。しかし自分の中では道半ばだと思っています。特に、『TKC基本講座・第5版』に示されている関与先指導をできるような所内体制を作っていくことを目指しています。具体的には、「経営者の心にベルトをかけよ」「関与先の発展のために祈りをもって全力投球せよ」「あなたは関与先経営者を断固叱れるか」などです(同書148~151頁)。また、それを支える職員を育成するために、TKCの研修制度やさまざまな仕組みをしっかりと事務所の中に取り込んで、最大のパフォーマンスを発揮できるように取り組んでいるところです。
もう一つの関与先支援への私の思いですが、このことを突き詰めていくと、黒字化支援に行き着きます。今、うちの事務所が重要視しているのが、社長との思いの共有と、目標の共有です。思いの共有に関しては継続MASを活用する。目標の共有に関しては月次決算速報サービスを活用する。これらTKCの心強いツールによる黒字化支援こそ、会計事務所に求められている関与先の親身な相談相手にもつながると思っています。

佐藤正行会員
吉野 全国会巡回監査・事務所経営委員長の吉野です。地域会はTKC神奈川会です。うちの事務所経営もそうですが地域会や支部で話していると一番の課題はやはり人材難です。ここ数年、求人を出しても人が来ない、せっかく採用してもなかなか定着しないという苦しい状況が続いています。ところが、総務省の統計などによると、2024年の日本の労働人口は過去最多に達しています。それでは、人材はどこへ行ったのかというと、今注目されているIT業界や製薬業界などに多く流れているようです。
一方、われわれの顧客である中小企業のニーズも微妙に変わってきているように感じています。うちの事務所の場合、関与先全体の黒字決算割合は、約73%~74%なのですけれども、儲かっていても跡継ぎがいないから事業を畳むとか、M&Aでほかの会計事務所に移ってしまうということがあり、とても残念な思いをしています。優良企業に育った先から離脱してしまいかねないという恐ろしい傾向にある中で、やはりこのような時代に対して何か有効な次なる一手を早急に打つ必要があるという危機感を、一事務所の経営者としても持っています。その決め手となるのがまさに〈近未来の巡回監査〉だと思います。

吉野 太会員
松﨑 昨年から、全国会中小企業支援委員長を仰せつかっている松﨑です。所属はTKC関東信越会長野支部で、プロジェクトリーダの原田先生には地域会会長として、日頃からご指導いただいています。事務所を人口約3万人の駒ヶ根市で開業しており、最寄り駅は無人駅です。そのような土地柄ですから、今日ご参集の先生方と私の置かれている状況は、少し違うのかもしれません。まず、人口が少ないので、お客さんを選べない。ですから、特定の業種に特化するといった経営は困難です。また、人材難の問題についてもより深刻ではないかと思います。地元税理士会においても退会したり、事務所を縮小したりするケースが最近よく見られます。
しかしそのような環境下にあっても、TKC全国会の運動方針に取り組めば事務所を成長させられるというのを立証したいのです。したがって、税理士の4大業務(税務・会計・保証・経営助言)を標準業務とすれば間違いないとの思いで取り組んでいるところです。
業務品質の確保については、翌月巡回監査率やK(継続MAS)F(FXシリーズ)S(書面添付)実践割合等で管理していけば、事務所体制が整備されてくるという実感があります。また、関与先の黒字化支援についても、BAST優良企業の条件(書面添付の実践、中小会計要領への準拠、限界利益額の2期連続増加、自己資本比率30%以上など)のクリアを目指すことによって、自ずとよい結果につながっています。

松﨑堅太朗会員
税理士の4大業務完遂に向けてオールTKCで全力を傾けていける
原田 そうした中で、TKC全国会が「会計事務所の経営革新」検討プロジェクトを設置した背景について、あらためて確認しておきます。お三方の話にもあったように、今日の税理士業界は、深刻な人材難や社会からのデジタル化推進の要請など大変革期に突入しています。いまこそ「会計事務所の経営革新」が求められているとの問題意識から、10年後のあるべき税理士業務(クラウド時代の巡回監査・経営助言)を見据え、TKC会員事務所が経営革新を実現するための〈近未来の巡回監査〉のあり方を検討するプロジェクトが第220回全国会正副会長会(令和6年3月)において設置されました。
ここで言う「会計事務所の経営革新」とは、TKCシステムの徹底活用と月次巡回監査の徹底断行により、税理士の4大業務を同一企業に対して同時提供できる事務所体制を構築するということです。そこで、〈近未来の巡回監査〉の定義、あるべき姿、標準的手法等を具体的にビジュアル化し、これをTKC全国会としてオーソライズして、TKC会員事務所に分かりやすく提示することによって、巡回監査の現場の実務に落とし込んでもらえるようにすることを目的として取り組んできました。
そこで皆さんへの質問ですが、地域会会長や全国会委員長の立場でプロジェクトに参画することになったときの率直な感想を教えてください。
佐藤 プロジェクトがスタートする半年位前に、坂本会長から新たな全国会運動方針に関するイメージを伺いました。それは私なりの理解では、月次巡回監査を基本にした、かっこいい会計事務所像を会員にしっかり提示して、そこに向かって全員で駆け抜けていく、というものでした。
これまでも全国会では、「KFS作戦」など、TKC理念に根ざした素晴らしい施策を推進してきて、個々の事務所においてもその成果が定着してきていると思います。いよいよTKC会員事務所がこの成果を近未来に向けてしっかりと活かしていかなければならない重要なステージに入ってきたのだなと、坂本会長のお話から強く感じました。さらに、プロジェクトが進行する中で、TKCの飯塚真玄名誉会長が税理士の4大業務完遂を全面的に支援するとの方針のもと、月次決算速報サービス提供の重要性を示してくださいました(本誌令和6年10月号特別寄稿)。このようなオールTKCとしての取り組みに、これから全力を傾けていけることに対して、とてもワクワクした気持ちになりました。
吉野 私はプロジェクト発足の話を聞いて、これは巡回監査・事務所経営委員会としても覚悟を決めて万全に取り組まなければならないなと感じました。というのもクラウド会計を駆使して顧客拡大している会計事務所の中には、巡回監査の必要性などまったく考えていないケースが意外と多いからです。記帳代行のみで顧客を増やそうという思惑が見えて、同じ税理士としてとても危機感を覚えていました。
その点で今回のプロジェクトに参画した一番の思いは、TKC会計人としての哲学を持った上で、DXなど時代対応をしていく──そういうことを会員の皆さんにしっかりお伝えしなければならないということでした。
松﨑 私の場合も、先ほど吉野先生がおっしゃっていたように、企業再生に近いご相談や、事業承継に関して後継者がいないなどの問題が周辺で起こっており、今までと同じようにやっていたら、お客さんは減っていくし、事務所自体も沈んでいってしまうという恐れがありました。その打開策について、全国会の会員先生方からいろいろなヒントを授かっていましたので、それをこのプロジェクトを通じてしっかりと目に見える形にして、全国の会員事務所にお示ししていくというのは、とても意義のあることだと思いました。
中小企業支援委員長の立場としては、昨年末に、継続MAS予算登録件数が飛躍的に伸びて10万件を突破できたこともあり、税理士の4大業務の経営助言に関してまだまだ伸び代があると実感したところです。TKCモニタリング情報サービス(MIS)についても、決算書等提供サービスの利用件数が35万件を超え、さらに高みを目指したいと考えています。このプロジェクトでも、「会計事務所の経営革新」に向けて、全国の会員先生方の心に火を灯したいという気持ちで参加しました。
原田 各々が熱い思いでもってプロジェクトに参画されたことがよく分かりました。
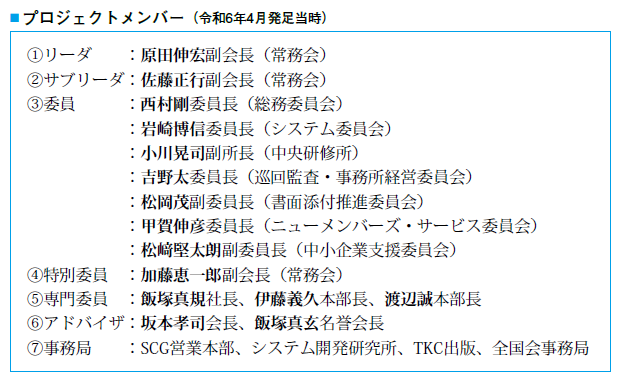
税理士業務は法律業務であり巡回監査は事実認定と法律判断行為
原田 実際にプロジェクトは昨年の4月から活動を開始しました。その後、プロジェクト会議(5回)と制作・検討チーム会議(手引き制作チーム:6回、ビジュアル化検討チーム:5回)を開催し、〈近未来の巡回監査〉のあり方の議論やTKC会員事務所に提示するテキストと動画の検討を重ねました。そして、12月に開催した第5回プロジェクト会議において成果物完成の目途が立ち、〈近未来の巡回監査〉の現場への落とし込みは、新たな全国会運動方針の活動に引き継がれることになりました。その意味では、運動方針への助走的な位置付けとしてわれわれのプロジェクトが役割を果たせたことは、ひとまずよかったと安堵しています。
プロジェクトでは佐藤先生にはサブリーダ、吉野先生には手引き(テキスト)制作チームリーダ、松﨑先生にはビジュアル化(コンセプトムービー)検討チームリーダをお務めいただきました。そこで皆さんにはそれぞれの立場からプロジェクトを振り返っていただきます。まず佐藤先生からは、プロジェクト会議でポイントになった議論についてお聞かせください。
佐藤 個別の委員会等では決定できない巡回監査のある種の革新的な部分に関して、このプロジェクトを通じてオーソライズしていくという側面がありましたので、特に全部監査に関して活発な議論がなされました。メンバーの中でも、本質的な巡回監査というところを踏まえつつも、さまざまな意見が出ていました。例えば、監査の範囲の強弱、専門家としての心証形成、アウトプットアプローチ等々、監査論上の監査に関する発言もありました。
その中で、巡回監査は監査論上の監査ではないこと、税理士業務は法律業務であること、従来の巡回監査の持つ概念を重視して厳格運用すべきこと、巡回監査の場所とは関与先の現場であること(現場主義、証拠主義)、事前確認その他、事務所で行うことはすべて巡回監査の準備であること、証憑突合は巡回監査の目的ではなく手段であること──などが一つ一つ確認されました。
つまり、これらのことを前提にして、FXクラウドシリーズの巡回監査機能によって経理事務の効率化と自動化を図り、われわれ会員もしくは職員は、しっかりと関与先の現場に赴いて事実認定と法律判断業務を行わなければならないということです。
私は議論を通じて、〈近未来の巡回監査〉というのは、まさしくデジタル力と人間力の融合そのものであると感じました。今まで証憑突合にすごく時間が掛かっていて、巡回監査が進まなかったという部分もあったかもしれません。そこが、デジタルで一新して完結できる体制が作られるようになると、巡回監査担当者の人間力が関与先から一層求められてくるでしょう。そのニーズに的確に応えることができれば、巡回監査実施関与先が一気に増えていくのではないかと確信しています。
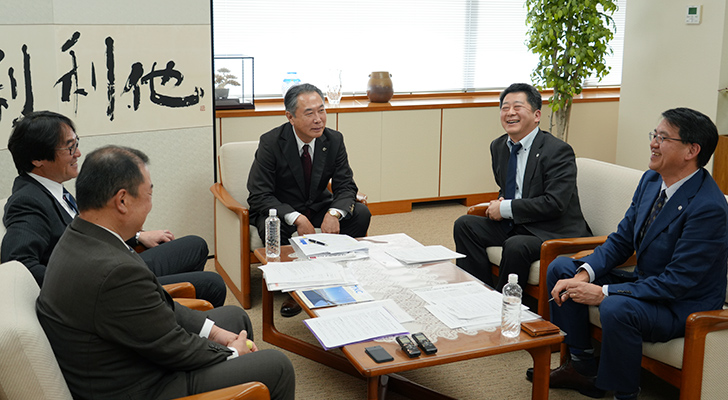
「これから変えるべきもの」は時代に対応した全部監査の手法
次に、吉野先生から、テキスト『TKC会計人 業務の未来設計』の制作にあたってリーダとして特に意識された点などについて、聞かせていただけますか。
吉野 坂本会長はテキストの「はじめに」で、発刊目的を次のように述べられています。
「本書は、税理士、とりわけTKC会計人の過去と現在の状況を踏まえながら、税理士の『近未来のあるべき姿』を具体的に示して、その目標に導く明確な道筋を示すものです。」
つまりこのテキストでお伝えしたいのは、単に、DXを使って仕事を楽にしましょうという話ではありません。当然、楽にできるところは徹底的にそうする一方で、時代に合わせて専門家としての役割をいかに果たしていくべきなのかということが重要なのです。
そもそもTKC全国会は哲学を持っている集団です。会計帳簿の証拠力を強化するという視点と、会計帳簿を使って税務・会計はもとより、保証や経営助言に関する業務にどう活かして展開するのかというところを強く意識しています。TKCシステムもそのことにフォーカスして開発されています。近未来においてもそれをどう推し進めていくべきかという点をかなり意識して、テキストの制作に臨みました。
原田 坂本会長はこのテキストについて、TKC全国会初代会長の飯塚毅博士が1969年に発行された『電算機利用による会計事務所の合理化』(略称『合理化テキスト』)の現代版であるとも表現されています。
吉野 その意味では、今回のテキストがTKCの原点をしっかりと踏まえ、そこを軸にしながら未来に展開していくきっかけになればよいですね。しかし、これが完成版だとは思わずに、これからどのように事務所経営に活かしていくかと考えるための入門書的なものとして位置付けていただけると嬉しく思います。
原田 それでは、コンセプトムービー「税理士の未来」の制作をご担当された松﨑先生から、特に会員に伝えておきたい点をお聞かせください。
松﨑 坂本会長から文字情報だけでは〈近未来の巡回監査〉のイメージが伝わりにくいからビジュアル(動画)化したいという要望をいただきました。リーダの原田先生からも「動画の担当をよろしく」と指名され、二つ返事でお引き受けしました(笑)。
私たちのチームでは、シナリオを作成するにあたって最初にフリーディスカッションを行いました。総務省を始めとする各省庁の未来予測の資料などを持ち寄って、いろいろなアイデア出しから行いました。コンセプトムービーを観ていただければ分かりますが、外国人の女性社長を登場させたり、宙に浮くディスプレイもシーンの中に取り入れてみたりしました。その中で、現在と未来を往き来する重要なアイテムとして使わせていただいたのが『飯塚毅会計事務所管理文書【第三版】』でした。その中から引用した言葉が「手書き時代と変わらないもの」です。
一方、「これから変えるべきもの」は、まさに時代変化に対応した全部監査の手法ということで結論付けています。近未来というと新しいことに目が行きがちなのですが、実はベースには不変のものが流れているということを意識しながら、コンセプトムービーをご覧いただけるとありがたく思います。
原田 ここが決め台詞というところはどこでしょう。
松﨑 終盤で所長が「巡回監査は現場で行わなければならない、という本質は変わらない。AIに財務分析や仕訳の自動生成はできても、経営者を説得したり責任を取ることは決してできない。税理士という仕事は、AIには決して取って代わられることのない仕事なんだ!」と主役の甲本税理士に説くところです。
原田 やはりそうでしたか。私もその場面では涙しました。
※後編に続く。後編では、新たなTKC全国会運動方針への対応を中心に掲載します。
TKC全国会が考えるこれからの税理士事務所の役割をTKC会員に分かりやすく伝えるために制作したコンセプトムービー「税理士の未来」を公開いたします。当動画は、2035年にタイムスリップしてしまった税理士を主人公とし、ドラマ仕立てで10年後の税理士の業務がどう変わるのかを表現しました。

(構成/TKC出版 古市 学)
(会報『TKC』令和7年4月号より転載)