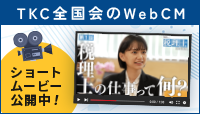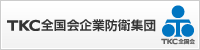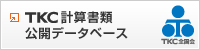寄稿
新しいビジネスモデルを確立しよう(3)
中小企業の継続支援「F=フォロー」は時代の要請
中小企業と会計人の関係は「相即不離」

TKC全国会会長
粟飯原一雄
国税庁が平成23年度分の「会社標本調査」を公表しました。それによると、平成23年の法人数は約257万8千社で前年度より約8千社減少しており、この20年間常に廃業率が開業率を上回ったことになります。
また、欠損法人は約185万9千社で、欠損法人割合は前年度よりやや下がり72.3%でした。欠損法人の比率は、平成11年に70%を超えて以来、途中で60%台に下がった時期があったものの、ここ3年はまたしても70%台となり、ほぼ4社に3社が赤字決算法人という状況が10年以上も続いていることになります。
平成11年に「中小企業基本法」の抜本的な改正が行われ、中小企業を日本経済のダイナミズムの源泉と捉え、「中小企業新事業活動促進法」をはじめ、様々な法環境が整備されたのにもかかわらず、中小企業の低迷状態が永く続いています。
中小企業と会計人とは、決して切り離すことのできない、いわば「相即不離」の関係にあります。中小企業が低迷していて、会計人だけが繁栄するということはあり得ません。
2021年まであと8年、TKC全国会創設50周年という記念すべきこの年を、このような状態の延長線上で迎えてよいのでしょうか。
私たちTKC会員の願う近未来像は、「関与先企業をはじめ中小企業がもっともっと元気になってほしい」、そして「会員事務所はもっともっと成長発展し、国家機関、金融機関、地域社会から信頼される存在でありたい」ということに尽きるのではないでしょうか。
この度「TKC全国会の政策課題と戦略目標」を掲げた本当の理由がここにあります。
困難に挑戦し、乗り越えるために「戦略」が必要
TKC全国会の2021年に向けての戦略目標の数値はかなり高いハードルであり、その達成のためには、様々な困難が待ち受けています。しかし困難を克服してこそ、この疲弊した状況からの脱皮が可能になると考えます。そして困難を乗り越えるためには、戦略が必要です。困難がなければ戦略は不要です。そして優れた戦略は、過去の経験の延長線上からは生まれず、飛躍から生まれると言われています。
戦略論の世界的な権威者と言われるアメリカのリチャード・P・ルメルト博士はその著書『良い戦略、悪い戦略』(村井章子訳・日本経済新聞出版社)で、「戦略とは『こうなったらいいな』という漠然とした願望ではなく、具体的な難局を打開するための行動を指し示すものでなければならない」として、「戦略に安直な近道は存在せず、王道を行くしかない」と述べています。
「F=フォロー」
自計化企業に業績管理体制を定着させる
『中小企業白書2013』(中小企業庁)には、中小企業による財務・会計面でのIT活用つまりパソコン利用についてのアンケート結果が掲載されています。
これを見ると、「財務・会計」のためのIT利用は、中規模企業の85.8%を占め、小規模事業者においては60.1%(下図「規模別・業務領域別のITの導入の状況」参照)にのぼっています。すなわち小規模事業者においても、その6割以上が自計化をしているという結果でした。
IT化が進み、経営者の若返りも進むなかで、この自計化率は確実に増えていくことが予測されます。しかし自計化が進めばよいというものではありません。パソコン会計の導入が帳簿作成や経理事務の合理化だけを目的とするものであってはならないと考えます。「会計で会社を強くする」という視点で、会計数値をいかに経営に役立たせるかが重要です。
そのためには関与先企業の社内に、P=計画・D=実行・C=検証・A=改善行動の「マネジメントサイクル」による業績管理体制を確立することが必要です。「F=フォロー」は、その中の(C=検証)と(A=改善行動)にあたります。計画を立てて、その実行状況の検証と対策行動を行うことです。そのためには実行段階で生じたコト(差異)の事実を正しく認識する視点が必要です。
しかし計画・実行段階で終わってしまい、結果を振り返り、次につなげるステップまで至らないケースが散見されます。企業が自計化する要諦は、マネジメントサイクルに従った業績管理体制を定着させて総合的な経営力を高めることにあると言えます。
「F=フォロー」
経営者がタイムリーな財務情報を縦横無尽に使いこなす
TKCの自計化システムは、別名「業績管理システム」とも言われ、経営者の意思決定に役立つ情報を提供する機能を優先しており、自社の業績管理における計数的な把握を経営者自ら行う体制にすることを目標にしています。
つまり日々の仕訳入力のデータの全てが、経営者が戦略上の意思決定を行うために必要な情報となります。計画(予算)と実績との差異に対してチェック(C)ができ、改善すべき行動(A)の素早い意思決定を助けます。
- 我が社の最新業績は?/売掛金の回収状況は?
- 予算対比・前年対比は?/採算部門あるいは不採算部門は?/予算を上回っている経費科目は?
- このまま行ったら今期の着地点はどうなる?/直近の資金繰り予定は?
このような経営に必要な情報を「社長ボタン」一つで入手でき、これを縦横無尽に使いこなすことで経営の舵取りに大きな武器となります。関与先企業の黒字化のための業績管理体制の構築に最適なTKC自計化システムの導入を積極的に進めていかねばなりません。
「F=フォロー」
経営革新等支援機関によるモニタリングの実施
昨年8月「中小企業経営力強化支援法」が施行され中小企業金融の新たな時代が始まろうとしています。
金融機関と経営革新等支援機関とのコラボレーションにより、中小企業の財務経営力を強化し、中小企業の成長・発展を促す施策が期待されています。TKC会員の多くが支援機関として認定されています。「F=フォロー」の業務でもう一つ大事なことは、経営改善計画の策定支援とともに、経営革新等支援機関に求められている計画策定後の実行フォロー、すなわちモニタリング業務があります。
中小企業・小規模事業者の経営改善や企業再生に向けて、計画策定後の実行フォローアップは、我々TKC会計人の経験と知識が存分に発揮しえる領域と言えます。
本年1月に開催された静岡会生涯研修において、中小企業庁小規模企業政策室・林揚哲室長は「税理士の皆さんは中小企業事業者にとって一番身近なホームドクターであり、経営支援の最も重要な一翼を担っていただくことが支援法の哲学と言えます」との期待を述べておられました。関与先企業のタイムリーな業績管理体制の構築支援と経営革新等支援機関としての、モニタリング業務は、ともに時代から要請されているミッションと受け止めるべきではないでしょうか。
最大の敵は「自己限定」と指摘した初代会長
ところで、このような戦略目標の実行を阻む最大の障害はなんでしょう。
飯塚毅初代全国会会長は、それは会計人の心の中にあると指摘されました。その一つとして、会計人特有の心の癖として、自らの可能性をふさいでしまう自己限定の傾向を挙げておられます。
その点を著書『会計人の原点』(93頁~94頁)の中で、次のように記述されています。
「税理士は納税者の頭脳水準を勝手に限定している。TKC会計人の中には『うちの関与先は規模が小さいし、そんな高度なものはとても理解できないのだから、受け取る帳表はTKC財務三表だけでよい』と勝手に関与先企業の需要と頭脳水準とを、決めてかかっている会員が、かなりおられるように見受けます。それは、会計人が自己中心の発想法に立って、勝手に判断している結果に過ぎません。それは重大な誤りです。(略)一刻も早く自我意識を捨て去って、関与先中心に、祈りをもって、関与先の健全性、発展性に向かって全力投球すべきではないですか」
KFSの「F=フォロー」は、中小企業の自計化──業績管理体制構築を支援することによって中小企業を元気にしていく源と言えます。
TKC全国会創設50周年の年である2021年(平成33年)を迎えて、「失われた30年だった」と嘆くことがないように、平成11年以来KFS運動で培った経験と知識を総動員して、戦略目標を何としてでも達成すべきではないでしょうか。
(会報『TKC』平成25年6月号より転載)