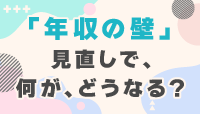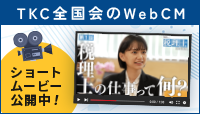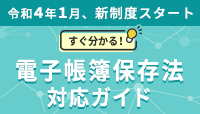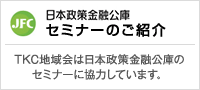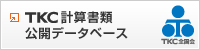消化器系のがんは早期に発見すれば95%が完治可能と言われるが、専門医でも判別は難しいというのが現実。そこで、内視鏡画像診断に人工知能(AI)を活用して、早期がんの「見逃し」をなくす取り組みを行っているのがAIメディカルサービスの多田智裕医師である。
- プロフィール
- ただ・ともひろ●1971年、東京都生まれ。90年、東京大学入学。 96年から東京大学医学部附属病院や辻仲病院などに勤務し、内視鏡医師として経験を積む。 2005年、東京大学大学院卒業。 06年、武蔵浦和メディカルセンター内に「ただともひろ胃腸科肛門科」を開業。 AIとの出会いをきっかけに内視鏡の画像診断支援AIの開発に着手。 17年、株式会社AIメディカルサービスを創業。
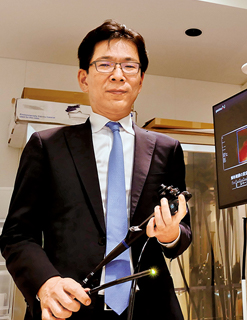
多田智裕氏
昨年の12月、早期胃がんに特化したAI搭載の内視鏡画像診断支援ソフトウエアの製造販売承認を、厚生労働大臣から取得し、今年の3月から販売を開始しました。
この製品、『gastroAI model-G』は、内視鏡システムの内視鏡ビデオ画像プロセッサから汎用コンピューターに入力された病変候補画像をもとに、肉眼的特徴から生検等追加検査を検討すべき病変候補である可能性を推定します。また、プログラムが生検等追加検査を検討すべき病変候補の可能性があると推定した場合、内視鏡表示エリア内に矩形表示により医師に注意喚起と診断補助を行います。
日本における胃がん罹患者数は、年13万人以上で大腸がん・肺がんに続いて第3位、死亡者数は年4万人以上で肺がん・大腸がんに続いて第3位となっています。胃がんは、病期が進行すると死亡率が高まりますが、早期に発見すれば十分に治療可能な疾患です。5年相対生存率は、ステージⅢ以降で発見された場合は5割以下ですが、ステージⅠで発見されれば95%以上となります。
一方で、早期の胃がんは判別が難しく、相当程度見逃されているとも言われています。
現在、国内外における内視鏡医は質量ともに不足しています。また、内視鏡からの画像を人間の目で見ると、どうしても見逃しが起きます。しかし、それを、膨大な画像データを覚えこませたAIによって補完すれば、がんを早期に発見して数多くの人々の命を救うことができます。
当社はこうした背景から胃がん診断支援AIを開発しました。これを用いることで、専門医並みの精度で、早期胃がんを発見することが可能となります。
140超の病院からデータを収集
私は、東京大学で医学博士を取得し、10年くらい修行を積んだ後、2006年に内視鏡専門クリニックを開業しました。AIに着目したのは16年、日本ディープラーニング協会の理事長である松尾豊東大教授の講演を聞いたことがきっかけです。この講演で画像認識能力においてAIが人間を超え、それを可能にしたのがディープラーニングであることを知り、内視鏡検査に応用できるのではないかと考えました。内視鏡検査は画像認識そのものだからです。
この16年を起点にして、胃がんの原因とされるピロリ菌の有無を識別するAI、そして胃がん検出のAIの開発に着手しました。
ディープラーニングで重要なのは、AIに覚えさせるデータの量と質です。まずは、国内トップクラスの病院から画像を入手することから始めました。内視鏡医療は日本発祥であり、現在も世界をリードしているのは日本です。機器のシェアは日系メーカーが98%を占め、専門医の技量はトップクラス。日本の内視鏡医療は70年の歴史があり、日本内視鏡学会には3万5,000名が登録しています。ちなみにアメリカでは1万5,000名。ことほどさように、日本の内視鏡医療のレベルは世界最高水準なのです。こうした環境に後押しされて、世界最高水準のデータを集めることができたことが、最大の成功要因だったと思います。
データ収集に関しては、最初は手探りでしたが、がん診療で国内ナンバーワンのがん研有明病院から承諾いただけたのが大きく、その後は、東京大学病院、大阪国際がんセンター、慶應大学病院など、次々と協力病院を増やすことができました。現在では、国内外で140を超える病院からデータをいただいています。
ワンルームからのスタート
それらデータを地道にAIに学習させて、17年5月にはピロリ菌を識別するAIのプロトタイプを開発、同年7月には胃がん発見の完成にもめどが立ちました。
開発が進むと、このAIをより多くの臨床現場で使ってもらいたいという気持ちが膨らんできました。そのためには個人の研究では限界があり、会社をつくる必要性を痛感。医療ベンチャー立ち上げの道を模索し始めました。大学発ベンチャーのピッチに参加し、国内の投資家と起業家が集うインキュベイトキャンプを経験するうちに、内視鏡AIが世界の医療の発展に貢献できると確信を持つようになりました。
同年9月、AIメディカルサービス(AIM)を設立。オフィスと呼ぶには質素なワンルームからの出発でした。とはいえ、研究・開発は順調に進み、同年10月にはピロリ菌識別の論文、18年1月には胃がん検出の論文を発表。早期胃がんについて6ミリ以上の病変で検出率98%という驚異的な数値をたたき出しました。さらに、胃がん検出AIは、動画リアルタイムでも94%の感度を記録。内視鏡検査中にリアルタイムで検査支援を行うAI開発のめどが立ったのです。
21年8月には胃がん診断支援AIの薬事申請を行い、23年12月に内視鏡検査中に肉眼的特徴から生検等追加検査を検討すべき病変候補を検出し、医師の診断補助を行うAI搭載の内視鏡画像診断支援システムとして製造販売承認されました。
近い将来AIが世界を制する
AIによる内視鏡診断技術の普及によって、世界で年間400万人といわれるがん患者の何割かを救えると考えています。消化器系のがん(胃がん・大腸がん・食道がん)は早期(ステージⅠ)に発見すれば97%完治できます。早期がんの「見逃し」が1人減れば、1人の命を救ったこととイコールになるのです。
『gastroAI model-G』は胃がんに特化したAI診断支援ソフトですが、今後は当然、大腸がんや食道がん向けのものも開発していきます。また、日本のみならず、東南アジアや欧米への展開も予定しており、すでにシンガポールと米国には子会社を設立。シンガポールとブラジルでは薬事承認を取得しています。
共同研究も欧米や香港、東南アジア、ブラジルで進展中。さらに、通信ネットワークが高度化されれば、クラウドサービスとして、全世界に普及させていく構想もあります。
AIは、決して人間が戦う相手ではありません。便利なツールとして使いこなせば良いし、AIを活用すれば、人間の能力を高めることができるのでよりよい結果が出せます。日本では、「AIによって仕事が奪われる」などといったマイナスイメージで語られることが多々ありますが、海外では、そうした議論はすでに飛び越えており「どう利用するか」だけが議論されています。
米国の著名なソフトウエア開発者であり投資家のマーク・アンドリーセン氏は、11年、ウォール・ストリート・ジャーナルに「(過去)10年でインターネットを使う人が500万人から20億人に増えた」➡「今後10年で50億人が携帯端末でインターネットに常時アクセスする」と寄稿し、その通りになりました。ソフトウエアが世界を制する時代になったのです。
同じくアンドリーセン氏は、23年に「過去4,000年において人類は知能を使い生活水準を1万倍以上向上させた」➡「人類の知能を根源的に拡張させてくれるAIは、あらゆる分野で生活水準を向上させる」と述べています。この仮説が正しければ、10年後あるいは20年、30年後には「AIが世界を制する」時代が来ることになります。
おそらく、近い将来、「昔はAIなしで医療診断がなされていたのか! 信じられない」と驚かれる時代が来ると思います。
(取材協力・柳田幸紀税理士/構成・髙根文隆)