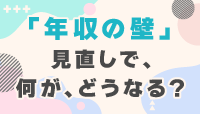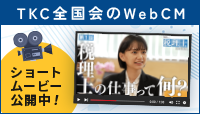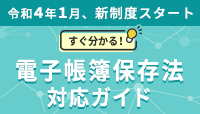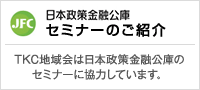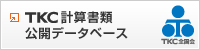工事現場での安全対策について、仕事を依頼した一人親方や配送業者に対しても責任が生じるようになると聞きました。詳細について教えてください。(建設業)
労働安全衛生規則等の改正により、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます(2025年4月1日施行)。改正の背景には最高裁判所で下された「建設アスベスト訴訟」判決(21年5月17日)があります。建設業における安全衛生対策に関する主な改正のポイントは2つあります。
【ポイント①】労働者以外に対する保護する対象範囲の拡大
危険箇所等での作業を行う場合、事業者が労働者に行う措置(危険箇所等への立ち入り禁止、立ち入り箇所等の限定、悪天候時の作業禁止、火気が禁止されている箇所での火気使用禁止、災害発生時における労働者の退避など)が、同じ場所にいる労働者以外の人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員などで契約関係は問わない)まで拡大します。つまりこれらの義務が、今後は自社の従業員だけでなく、同じ作業場で何らかの作業に従事する全ての者にまで拡大されるということです。
【ポイント②】下請け事業者や一人親方への周知の義務化
危険箇所で行う作業の一部を請負人(一人親方、下請け業者)に行わせる場合、立ち入り禁止が必要であるような危険箇所等において、例外的に作業を行わせる場合には、労働者に保護具等を使用させる義務があります。その時には、事業者は請負人に対して保護具等を使用する必要があることを周知しなければなりません。事業者は下請け事業者や一人親方に対して指揮命令を行うことはできないため、「周知」という形になります。
二つ先の下請けには義務なし
このように保護の対象範囲が拡大され、事業者は同じ現場で働くすべての人を対象に、危険箇所等での作業に対する措置を行う義務が生じます。ただし、同じ現場で複数の事業者が作業を行う場合、これらの措置をそれぞれの事業者ごとに行う必要はありません。各事業者が共同で行うことも可能です。
事業者が危険箇所での作業に対する措置を適切に行ったにもかかわらず、同じ現場で働く従業員以外の人がそれを無視した行動を行った場合は、事業者に責任は生じません。具体的には、立ち入り禁止や火気の使用禁止を明確に表示等しているにもかかわらず、同じ現場で働く従業員以外の人が立ち入り、火気を使用することや、事業者が明確に退避を求めているにもかかわらず、同じ現場で働く従業員以外の人が退避しないことなどが挙げられます。
重層請負の場合、個々の事業者は請負相手に対する義務を負いますので、2次下請けに対する義務はありません。この場合、1次下請けが2次下請けに対する義務を負い、2次下請けが3次下請けに対する義務を負うことになります。