目の前にぶら下げられたニンジンにはつい手が伸びるもの…。販促活動には、顧客への何らかのメリット提示が絶対条件だ。とはいえ、常識にとらわれた従来型インセンティブでは、いまの賢明な消費者は見向きもしない。だが、そこにひとひねり加えれば、新しい世界が見えてくる。
間違いだらけの「特典販促」

販売のあるところセールスプロモーションはつきものである。よほどブランド力のある店舗や製品は別にして、値下げや景品など顧客の需要を刺激する何らかのインセンティブ施策は、売上確保の必須条件といえるだろう。しかし、はたしてそのプロモーションが、期待通りのプラスの結果を生みだしているかとなると、いささか心許ないと言わざるを得ない。プラスどころかマイナスを呼び込む起点となるケースも散見される。それほどに、顧客へのインセンティブ提示には、デリケートな心配りが必要だということだ。が、その心配りを実践するのはそう簡単なことではない。少なくとも以下のような基本的な誤解を排除した上で、具体的戦略立案に取りかかるべきである。
誤解1
「値下げ」は最も効果的なインセンティブである
もちろん、価格を下げることは、消費者にとって分かりやすいし、ダイレクトに需要を喚起するインセンティブになり得る。しかし一方で、その効果が過大評価されてきたのもまた事実である。なぜ過大評価されてきたのだろうか…。
通常、スーパーなどが値引きセールを行う場合、大々的にチラシを打ち、店頭プロモーションを行い、商品陳列にも工夫を施す。そんな販促活動の総合力が売上に反映しているにもかかわらず、POSデータから読みとれるのは値引率と売上推移だけ。つまりその時点で、分析する側はその商品の売上増が100%値引きによる効果であると誤解してしまうのだ。
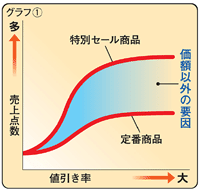
グラフ(1)を見てもらいたい。上の折れ線は値引きとチラシ、陳列の工夫などを組み合わせた特別セール商品のプロモーションのケース。下は定番商品の棚で値引きだけを行ったケースだ。特別セール商品を見ただけだと、値引きによる効果は絶大のように思える。しかし、定番商品では、値引きによる効果ははるかに限定的である。つまり、値引きそのものの効果は定番商品の実績で量るのが妥当で、特別セール商品は値引き以外のプロモーションによって売上点数を上積みしているのだ。
要は、値引きによる効果を限定的なものと認識し、並行してそれ以外のプロモーションをバランスよく組み合わせることが必要なのである。値引きに頼った販促に終始することは、結果的に非効率を呼び、いたずらに粗利を減らす危険性を孕んでいるといえるだろう。
誤解2
値下げ幅が大きければ大きいほど、あるいはセール期間が長ければ長いほど集客が増え、結果として売上が上がる。
短期速効性という面でいえば、その通りである。極端な値下げを実行すればセール期間中は売上がはね上がるだろう。しかし、それはあくまでも短期でのこと。長期的に見れば、この理屈は成り立たない。
ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンらが提唱した「プロスペクト理論」によると、人間はポジティブな情報よりもネガティブな情報の方にはるかに心理的に強く影響されるようだ。
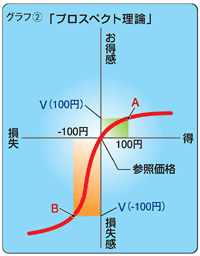
グラフ(2)を見ていただきたい。
たとえばある商品を100円値引きしたとする(A)。すると、消費者はV(100円)分のお得感を感じる。ところが、その値引きした状態から、100円プラスして元の価格に戻した場合(B)、消費者の感じる損失感はV(マイナス100円)となる。グラフの傾斜を見ていただければ分かる通り、お得感と比べて数倍もの損失感を感じることになる。こうなると、元の価格に戻した後のこの商品の売り上げは激減する。結果として価格を元に戻せなくなるのである。
つまり、値下げ幅を大きく、あるいは期間を長くしてインパクトを強めることは、長期的に見ると、マイナスの影響を蒙ってしまう可能性が高いのだ。
では、この理論に絡め取られないためにはどうしたらいいのか。様々な方法論があるが、要は値下げ価格が、消費者の心理のなかでグラフの中心部の「参照価格」に変異しないようにすることである。
具体的には、まず期間を明示すること。これは最低条件である。「○○周年セールで1ヵ月限定」など、特別セールであることを消費者が認識すれば、「参照価格」行きをある程度免れることができる。
が、それだけでは不十分である。商品を値下げすれば、どうしてもその値下げイメージがついてしまうからだ。そこで、単品をダイレクトに値下げするのではない別の方法が必要になってくる。
たとえば、2つ以上の商品をバンドリング(抱き合わせ)してトータルで値下げする方法は有力である。こうすれば個別商品の値下げイメージ定着は避けられる。また、既出のプロスペクト理論の「シルバーライニングの原理」も、バンドリング販売の有効性を後押しする。この原理は「ほぼ同等のゲインとロスがあった場合、ゲインとロスは統合した方が価値は高まる」というもの。つまり、1個買うと1個無料ですというより、2個買うと1個分の値段ですという方が価値が高まるということだ。この原理に近づける形でバンドリング販売を行えば、より効果が得られるかもしれない。
また、同じ値引きでも属性などで縛る条件つき値引き。あるいは増量やおまけ、クーポンや懸賞などを付加することで間接的に値引きしたりという工夫も重要になってくる。つまり、その商品のブランドイメージを損なうような値引きではなく、そこにひとつ緩衝剤を入れ込み、消費者の目を逸らす工夫だ。これら工夫の巧拙が、顧客インセンティブ戦略の成否を分けるのである。
誤解3
くじ引きなどの懸賞の景品には少数でも高価なものを用意した方が影響力がある
懸賞にはあらゆる人が対象のオープン懸賞と、商品購入者だけを対象とするクローズド懸賞がある。「1000万円が当たる」などというとてつもなく高額な懸賞は、たいていがオープンであり、中小企業の販促はクローズドが一般的。
そのクローズド懸賞でも、最近までは、比較的高額な景品を少数用意するのが一般的だった。海外旅行やプラズマテレビなどの高額景品を提示して消費者へのインセンティブにするわけだ。しかしこのやり方だと、せっかく商品を買って応募したのに外れてしまったという人が大量に発生する。あるいは「どうせ当たらないだろう」という諦めを消費者に喚起する可能性も高い。結局はそれら不満だけが残ってしまい、後々のイメージを悪くしてしまう危険性がある。そこで最近では、たとえば「100万円を1名様に」よりも「10万円を10名様」、「10万円を10名様」よりも「1万円を100名様」の方がトータルな効果を見込めるとの考え方で懸賞を実施する企業が増えてきた。少なくとも、大手メーカーの商品プロモーションの流れは、その方向性に向かいつつある。
このようにできるだけ広く、多くの人に特典を与えるやり方の究極の形は「もれなく」型である。「商品ご購入の方にもれなく進呈」というやつだ。よく見かける「シール○○枚でもれなくグラスを進呈」などという飲料メーカーのプロモーションがそれである。が、これも、あまりにも集めるシールの枚数(販売証明)が多かったり、景品が粗末なものであったりするとそれほどの効果は期待できない。
そこで、最近流行の兆しを見せているのが「セルフリキデーション」(自己清算方式)というもの。これは、ある程度の購入証明にプラスして消費者がいくらかお金を負担すれば、かなり高価なものが「もれなく」貰えるというものだ。たとえば、ネスレなどは『上質を知る人』キャンペーンでこのセルフリキデーション方式を採用している。この方式であれば、購入金額をそれほど高く設定することなく、なおかつ良い景品も提供することができるため、前述した「もれなく」型の弱点はとりあえず補完される。一考の余地はあるだろう。
誤解4
景品には、なるべく消費者の欲しがりそうな汎用的なものを選択するべきである。
短期的に考えればその通りである。使えそうもないものを景品にしても仕方がない。しかし、その物差しだけで景品を選択すると、即時性は期待できても継続性は見込めない。長期的な視点に立つなら、もっと戦略的な景品の選び(つくり)方をすべきであろう。
たとえば、サントリーが数年前、ウィスキーにアルプスの天然水である「仕込み水」のおまけを付加した。このおまけには「こんなおいしい水でウィスキーを仕込んでいる」というメッセージ(情報)が含まれている。また、カゴメはトマトジュースにトマトの苗がもらえる懸賞をつけた。これも「きちんと品質管理したおいしいトマトでジュースをつくっていますよ」との情報を伴ったインセンティブである。
上記は大手メーカーの例でかなりしゃれた施策だが、中小企業でも豊かな発想さえ持って望めば、いくらでもこのような施策を仕掛けることはできるだろう。商品に由来するものはもちろん、会社の歴史やイメージに由来するもの、所在地に由来するもの…。たとえば、スマイルリンクルという会社の事例は、広島お好み焼店が広島カープをテーマにしたインセンティブで大成功をおさめたケースである。つまり、自社商品とまったく関係のないものを選ぶよりも、その企業の何らかの情報を伴ったインセンティブの方が、長期的に消費者の印象に残る分、高い効果が期待できるのである。
誤解5
ポイントカードによるインセンティブの提供は、いまや小売業・飲食業の必須アイテムである。
ポイントサービス普及の大本となったのは、航空業界の「マイレージ」である。航空業界は変動費が低く固定費が高い。飛行機1機はどれだけお客が乗ろうとコストはほとんど変わらない。そのため、マイレージで1人分余計に乗せてもコスト負担は同じなのである。ホテルも同様で、基本的にはポイントサービスはこのような業界に向いている。
一方、流通業はどうか。変動費が大きいためお客が商品を買えば買うほどコストが増加する。ポイントサービスによって、実質的な値引きを行えば、それがそのまま利益に跳ね返ってくるのである。本来、このような業界にはポイントサービスは向かない。ちなみに最近でもマクドナルドやユニクロといった錚々たる企業がポイントサービスを全廃している。このような現実を直視し、無条件にポイントサービスを信奉することは止めるべきであろう。
が、だからといって、ポイントサービスを全面否定する必要もない。うまく活用し売上を伸ばしている小売業も少なからず存在する。要はやり方である。
成功例としては、山梨県のスーパー・オギノはあまりにも有名である。が、そのオギノのポイントカードの還元率が0.2~3%というのをご存知だろうか。ちなみにユニクロは8.75%だった。にもかかわらず、ユニクロが失敗しオギノが大成功を収めているのには理由がある。オギノは顧客データを活用しながら極めて臨機応変にインセンティブを提示しているのだ。つまり、一律還元ではなく、ロイヤルユーザーを見極め、個客にピンポイントに還元していく手法である。また、オギノはメーカーとタイアップし、メーカー側のコストで消費者に還元していくセールも多用するなど、ポイントサービス全体のコストをできるだけ押し下げる努力を行っている。
要は、小売業や飲食業の場合、自らの財務構造を見極めながら慎重に戦略を練ることが、ポイントサービス成功の条件だということ。ポイントサービスは本来優良顧客を獲得するためのもの。できれば「一律」は避けた方がいい。
(本誌・高根文隆)
掲載:『戦略経営者』2004年12月号













