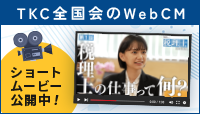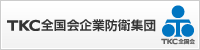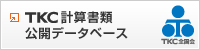対談・講演
職業会計人の独立性 税理士、巡回監査士の「指導機能」発揮を期待する!
千代田邦夫 元金融庁公認会計士・監査審査会会長 立命館アジア太平洋大学客員教授、
坂本孝司 TKC全国会会長
元金融庁公認会計士・監査審査会会長の千代田邦夫立命館アジア太平洋大学客員教授と坂本孝司TKC全国会会長が対談し、職業会計人の独立性における「指導機能」発揮の重要性や、巡回監査が「三現主義(現地・現物・現人)」の実施に基づく事実認定作業であることなどが話し合われた。司会は加藤恵一郎本誌編集長が務めた。
司会 本誌編集長 加藤恵一郎
とき:令和7年6月10日(火) ところ:TKC東京本社

アメリカの監査制度の歴史を研究して成果を活字に残したかった
──今月号は、千代田邦夫先生と坂本会長との対談を企画させていただきました。お二人の出会いは、坂本会長が2022年に『職業会計人の独立性──アメリカにおける独立性概念の生成と展開』(TKC出版)を上梓し、その重要な文献として千代田先生のご本『闘う公認会計士──アメリカにおける150年の軌跡』(中央経済社、2014年)を引用されたところから始まります。最近、千代田先生はTKC地域会の研修会等でご講演され、我々の業界についてもますます理解を示してくださっています。

坂本孝司会長
坂本 千代田先生には今年1月に静岡会にお越しいただきました。私も会場で直に拝聴しましたが、税理士の独立性や自己研鑽の大切さについて熱く語っていただいた感動的な講演でした。本日こうしてじっくりお話しできる機会をいただき、うれしく思います。
千代田 静岡では、300名を超えるTKC会員の税理士の先生、また巡回監査士など事務所スタッフの方々にお話しでき、とても光栄でした。私も今日の対談を楽しみに参りました。
──まず、千代田先生が研究者を志したきっかけからお話しいただけますか。
千代田 高校時代に公認会計士という職業を知りました。駅から高校までの途中に、「公認会計士」という小さな看板を掲げていた家があって、何をしているのだろうと通るたびに思いました。英語の先生は東京帝国大学法学部卒の難波渉先生という方で、先生の朴訥で誠実な姿勢に惹かれた私は、大学に入学してから夏休みにはご自宅を訪問して、大学生活を報告していたのです。商社マンになろうとしていた私に公認会計士という仕事があることを教えてくださったのがこの難波先生でした。大学4年時に公認会計士試験の受験勉強を始めました。
大学院の師は青木茂男先生です。公認会計土第2次試験に合格し、2年間の大学院を修了した時、時代は明治から数えて100年でした。幕末から新時代にかけて多くのリーダーを輩出した「薩摩」に魅せられていた私は、鹿児島で教鞭を執りたいと申し出ると青木先生は喜ばれ、鹿児島経済大学(現・鹿児島国際大学)を紹介してくださいました。
私が大学教員として心に決めていたのは、1つのテーマを4年間は徹底的に追いかけ、成果を活字に残すことでした。テーマは日本の公認会計士監査制度の範となったアメリカの監査制度の歴史で、特に法定監査以前の1880年代から1930年代までの職業会計人の「闘い」を勉強して、アメリカの監査制度の発展を政治的・経済的・社会的展開の中で捉えてみようと考えました。
32歳の時に8年間過ごした鹿児島を離れて立命館大学に移り、それから定年まで33年間務めました。赴任した当時の立命館はマルクス・レーニン主義の全盛で、教授会で右と左が、また左と左が激しくぶつかり合うような時代でした。ただその中で多くを学び、理事・学部長・研究科長・就職部長等の大学の行政にも係わり、学生目線で透明性の高い大学・職場でなければならないことを実感しました。
坂本 加藤先生は大学は立命館に進み、千代田先生のゼミで学ばれたそうですね。
──ちょうど千代田先生が立命館に赴任された年と同じ1976年に私も入学しました。大学3年の時に千代田先生のゼミに入り、直接ご指導いただきました。
千代田 そういう意味では、あれから約45年後に坂本会長との対談の機会をいただき、こうして加藤君とも再会できたわけですから感激しております。
「通説」をうのみにせずに好奇心を持って研究に取り組む
──千代田先生が研究者として大切にされていることは何ですか。

千代田邦夫教授
千代田 実は、「研究者」と言われることに素直になれないところがあります。それは、24歳の時に大学教員になりましたが、将来は公認会計士あるいは税理士として事務所を持ちたいという気持ちがあったせいかもしれません。研究者を目指そうというよりも、アメリカの公認会計士制度の歴史を自分なりにまとめてみたいという好奇心が先行して、その積み重ねの結果として今の私があるように思います。
ただ、1994年に出版した『アメリカ監査論』(中央経済社)が一般社団法人日本内部監査協会の青木賞、日本会計研究学会の太田賞、そして日経・経済図書文化賞をいただいたことをきっかけに、多少研究者として自信が出てきました。振り返ると、これまでに本を15、16冊出版したので、ほぼ4年に1冊ずつ活字に残してきたことになります。アメリカの監査制度の歴史を継続して勉強してきたのは私にとって財産であり、中身はともかく、所期の目的は達成できたと思っています。
坂本 千代田先生が明らかにされたアメリカ公認会計士制度の歴史的解明の研究成果がなければ、私は先のアメリカにおける独立性概念の生成と展開についての研究を進めることはできませんでした。先生のご研究はそれまでの学界における「通説」に対して、しっかりとエビデンスを付けて、論理的に反論されている点が印象的でした。
千代田 私はいわば研究者としての「親分」がいなかったから、「一次資料」に基づいて得られた事実を信じてそのまま書けたとも言えます。
──千代田先生は金融庁公認会計士・監査審査会会長の要職を2013年から3年間つとめられましたが、当時を振り返っていかがですか。
千代田 審査会には70名ほどのメンバーがいて、その約半数が4大監査法人出身の公認会計士でした。任期を終えると出身事務所に帰り、プロパーの人はいません。私は、「審査会の会長はお飾り」であってはならないと考えていたので、問題があればしっかり議論することを徹底し、会議をリードしてきたつもりです。
在籍3年目の時に遭遇したいわゆる「東芝事件」のときは、さらに気持ちを引き締めました(詳しくは、千代田邦夫著『経営者はどこに行ってしまったのか──東芝 今に続く混迷』(中央経済社、2022年))。第三者委員会の調査報告書では会計監査については必ずしも十分に取り上げていないことが判明したため、我々の使命である監査法人監査が適正に行われていたのかを検査するため、スタッフと打ち合わせをしつつ取り組みました。根本的原因を探るべく調査報告書を改めて読み返しながら、私の若干の監査経験も生かしながら、検査報告をまとめました。印象に残っているのは、金融庁による処分は私が予想していた以上に重いもので、業務改善命令だけではなく、公認会計士法に基づく課徴金約21億円が初めて科されたことです。
公認会計士の皆さんには厳しいことを言う会長と思われたかもしれませんが、私自身は業界全体を応援する立場でした。この事件への対応も含めて、貴重な経験をした3年間でした。
坂本 千代田先生が職業会計人を愛しているのがよくわかります。それゆえ不正を看過できずに「会計正義」を追求される。反骨精神といいますか、矜持といいますか。
千代田 私自身はそれほど反骨精神がある人間とは思っていないんです(笑)。ただ、職業会計人としてここはというところは決して譲ってはいけないし、使命感は失いたくありません。
税理士、公認会計士は同じ職業会計人として互いを認め合う時代

『公認会計士の力──わが国
70有余年の監査制度の分析と展望』
(中央経済社、2025年)
──千代田先生のその信条は、最近上梓された『公認会計士の力──わが国70有余年の監査制度の分析と展望』(中央経済社、2025年)にもよく表れていますね。
千代田 この本はタイトルだけを見ると「公認会計士万歳」といった印象を持たれるかもしれませんが、そうではなく、問題点は指摘しつつも、現場で誠実に業務に取り組んでいる、職業会計人として譲れない局面で闘っている公認会計士の方々を勇気づけたいという想いで書きました。
──本の帯には「公認会計士は『会計正義』を追求する“プロフェッショナル”である」とあります。
千代田 正義という意味は立場によって異なりますが、公認会計士にとっての正義とは、発生している経済事象が適切に仕訳されているか、そして、経営者に起因する財務諸表の虚偽表示を発見することだと考えます。
坂本 会計正義という言葉にはしびれました。公認会計士のみならず、職業会計人の一翼を担う税理士も高いプライドが醸成されることと思います。
千代田 税理士、公認会計士は同じ職業会計人としてお互いを認め合う時代です。そのためにもそれぞれの領域の中で独立性を持って仕事をし、実力を付けていく以外に手段はありません。坂本先生からは拙著への感想を丁重にお手紙でいただき、その真意をしっかり読みとっていただきました。特に、職業会計人の独立性という意味では、会計士も税理士も一緒ではないかと先生はおっしゃってくださいました。
税理士の独立性は、顧客である納税者と税務当局との間で常に揺れ動いているのです。顧問先の社長との関係で、「こちらが報酬を支払っているのだから言うことを聞いてくれますよね」といった場面がきっとあると思います。そういうとき、また、仕訳が経済実態を表していないときなどに、ダメなものをダメと毅然と言えるかどうか。ここが決定的に重要です。
坂本 まさに我々はそのことに日々さらされています。私は自分の事務所で、顧問先を説得してどうしてもダメなら契約を解除して構わないと職員に伝えています。日々その闘い、繰り返しですね。
千代田 正しいことをしていれば会社は伸びるという信念を持つことが重要です。会計事務所からの指導に対して、社長は瞬間的には抵抗するかもしれませんが、後から「先生にあの時言ってもらって良かった」と思うものです。伸びていく会社の経営者ほどそうでしょう。
坂本 そうした姿勢で、月次巡回監査とTKCシステムを活用し指導しているTKC会員事務所は顧問先が発展し、事務所も発展している傾向にあります。
千代田 そうだと思います。また、スタッフはリーダーである所長の背中をよく見ています。所長が職業会計人としての姿勢を貫けば、「自分たちが言えないことを所長が顧問先に言って闘ってくれている。私たちをリードしてくれている」とか、「この業務は誰にも負けないように努力して、責任を果たしていこう」などと前向きな風土が事務所の中に醸成され、チーム力がアップしていきます。逆に、所長が顧問先に決断をおもねる「迷い」のようなものが出てくると、事務所で働くスタッフがやる気をなくします。
税理士の独立性が日々揺れ動く中で、TKC全国会の皆さんが「租税正義の実現」に向けて運動を展開し、独立性を支えるべく奮闘されている──、皆さんに今回伝えたいのはこのことへの敬意です。
巡回監査は「三現主義(現地・現物・現人)」の実施に基づく事実認定作業

加藤恵一郎本誌編集長
──今のお話に通ずると思いますが、千代田先生は最近の講演の中で、我々に対して「指導機能を発揮する基本的な視点となる『仕訳の裏に存在する取引の実態(経済実態)を把握すること』」の重要性を指摘されています。
千代田 仕訳が取引の実態を、経済実態をきちんと反映しているかどうかが極めて重要です。いうなれば、税理士にしても公認会計士にしても、仕訳の「後」ではなく「前」に、どれだけエネルギーを注げるかがポイントです。
坂本 TKC全国会初代会長の飯塚毅博士も、出来上がった仕訳から整合性をとるのではなく、その前をよく見なさいとおっしゃいました。巡回監査で毎月現場に行き、実際の経済事象を確かめるということです。会計の入り口論です。
製造業では、問題発見と改善の基本姿勢として「三現主義」──すなわち「現場」「現物」「現実」を重視する考え方が徹底されています。これは、現実に即した判断と改善を行うために不可欠な行動原則です。私たちが実施する巡回監査においても、まさにこの「三現主義」に通じる実践が求められると考えています。
企業の経済取引の実態を把握し、税務・会計の観点から正しい処理を促すためには、形式的な書類確認だけでなく、現実に即した検証と対話が重要です。私見ですが、巡回監査における「三現」は次のように整理できると考えています。
●現地(現場)
少なくとも毎月関与先を訪問し、その事業活動の現場に身を置いて事業の実態を把握する。臨場感ある現地でこそ、気づける事実があります。
●現物(証拠)
事実認定を行うために、領収書、請求書、契約書などの証憑類を確認するとともに、必要に応じて実際の「モノ」を確認する。すべての仕訳が取引の経済実態、すなわち「真正の事実」を正確に反映しているかを確かめる姿勢です。
●現人(顔の見える関係)
経営者、経理担当者、各取引の責任者と直接対話し、意図や背景を把握する。必要に応じて、会計・税務の視点から指導も行います。
飯塚毅博士は「税理士はどのようにして自己の法的責任である『真正の事実』に準拠する業務ができるでしょうか。第一は、企業経営者の心に常にベルトを引っ掛けて、彼らを不正経理に走らせない工夫をこらすこと(現人=坂本)、第二は、関与先企業の現場に出かけて行って(現地=坂本)、会計処理の網羅性、真実性、実在性を確証してくること(現物=坂本)」とされ、「そのためには、少なくともひと月に一回以上は、関与先を訪問して、経営者の心に果たして正しくベルトが掛かっているかどうか、会計処理に網羅性、真実性があるかどうかを確かめ、ときには毅然として警告を発すること、が絶対の条件となります」と言われています。
巡回監査は、これら「三現主義」の実施に基づく事実認定作業であるわけです。
千代田 現地・現物・現人の「三現主義」という言葉は、とても分かりやすくて良いですね。公認会計士が行う財務諸表監査と税理士が行う巡回監査は異なることから線引きが難しいと感じていました。この「三現主義」であればまさしく仕訳の裏に存在する取引の実態(経済実態)を把握し、税理士の皆さんが指導機能を発揮されます。まさに、“キーワード”です。
──全国会ではいま、「税理士の近未来のあるべき姿」を具体的に示し、TKC会計人の原点である巡回監査の時代対応について議論を整理しています。
坂本 デジタル化の進展は著しいですから、現地に行かなくても帳簿らしきものが出来上がってしまう面があります。しかし「三現主義」の徹底に基づく事実認定作業を行い、最後は経営者の顔を見て確認しなければならないですね。
千代田 それが、坂本会長が提唱されている「顔の見える関係」の構築ということでしょう。デジタル化の時代だからこそ現地での確認は非常に重要です。
坂本 大切なのは使い分けですね。現地・現物・現人の「三現主義」が巡回監査の本質であり変えてはならず、その他の部分は大いにデジタルを活用すればよいのです。
「租税正義の実現」を組織の運動として続けてきたことに惹かれる
──千代田先生はご講演で「TKCの理念、すなわち飯塚毅博士の理念の実現のためには、税理士の『指導機能』の発揮が不可欠である」と熱く訴えられていますが、飯塚博士の理念などをどのようにご覧になっていますか。
千代田 飯塚先生の理念や理論は坂本会長のご本や『TKC会報』の講演記録から知りました。飯塚先生は「租税正義」の実現に向けて税理士は実務でどうすべきであるかとして、納税者の立場にも税務当局の立場にもおもねらず、坂本会長の言葉をお借りすれば裁判官の補佐人的な役割に位置付けられました。
飯塚先生は『正規の簿記の諸原則』(森山書店、1983年)で、日本の商法はドイツ商法に依拠していましたからそこに焦点をあてて研究され、また、アメリカの監査制度も概観され、同時にその成果を個人としてではなく「運動論」に結びつけられました。映画『不撓不屈』のモデルとしても登場し、税務当局とも7年間にわたって闘い、飯塚事務所員4名の無罪を勝ち取りました。闘う研究者として、私は、飯塚先生に感銘を受けるのです。TKC全国会はすでに創設から54年という重い歴史がある中、現在も坂本会長はじめ会員の皆さんが飯塚先生の理論を継承し、実務において実践されている。ものすごいエネルギーです。
飯塚先生が税理士個人としての成功を追い求めるのではなく、国家や税理士業界全体をみて大きなグランドデザインを描き、「税理士の独立性」を追求し、「租税正義の守護者」としての役割を果たしていくことによって、税理士全体の社会的地位向上に向け、先駆的に取り組まれてきたという事実がすごいのです。
坂本 権威ある千代田先生の言葉を厳粛に受け止め、税理士が国民一般、また社会から納得を得られるように、我々は引き続き襟を正して取り組んでいく所存です。

向上心を持って活動している巡回監査士の存在
千代田 このようなTKC全国会の歴史の重さや取り組みを、会員の皆さんはよくご存知でしょうが、事務所のスタッフにいかに広げていくかが大切です。その意味で、静岡会で講演させていただいた際、巡回監査士の方たちも多くおみえでしたが、この巡回監査士制度は画期的だと感じます。事務所のスタッフの方たちにとって、たとえ税理士を目指さなくとも「誇りを持って働く」ことにつながり、「どう生きるか」という問いへの答えにもなっていると感じるからです。この業界でやっていこうと決意し、実力を付けるために向上心を持って学ばれている方たちの存在は心強いですし、心から「頑張れ」と伝えたいです。
坂本 若き職業会計人へのエールに感謝いたします。おかげさまで現在、巡回監査士と巡回監査士補は合わせて約1万7,000名おります(令和7年1月1日現在)。受験者のうち、200名近い方が一般受験されています。
千代田 合格率も21%くらいと厳しいようですし、TKC巡回監査士制度が税理士業界全体のレベルアップにつながっているのではないでしょうか。
巡回監査士の大切な仕事が経営助言です。さきほど申した経済実態を表す事実の数字だからこそ、皆さんが取り組まれている税務・会計・保証・経営助言の4大業務が意味を成します。
経営助言というと、巡回監査士の方たちにとっては少し負担に感じるかもしれませんが、気負う必要はありません。「基本的には誠実だろうけれども、最近の社長の言葉の節々でちょっと気になる」とか「金額的にも動きが大きい」とか、そういうときは時間を作ってしっかり対話をすればよいのです。論理づけをしながら、自信を持って伝えていくことが大切です。
坂本 顧問先一社一社を見て、それに応じて支援していけるのが、この職業の魅力です。
千代田 顧問先の中には「うちの税理士先生、巡回監査士は厳しいけど、これだけ頑張ってくれているから報酬アップで応えたい」といった社長が出てきます。全てのクライアントがそう考えるとは限りませんが、これからTKC事務所と一緒に会社を伸ばしていきたいという経営者は必ずや皆さんに応えてくれますよ。
顧問先の規模等によって、「一般に公正妥当と認められる企業会計基準」と「中小会計指針」、それに「中小会計要領」を使い分けていくこと。そして助言業務として、月次決算、月次巡回監査、「月次決算速報サービス」の3点セットを使いこなすことが時代から求められているのです。同時に、それを駆使できるのは税理士の先生や巡回監査士の知識、経験という「力」であると思います。
全国会は「勉強する会」。さらに「実力」を付けて業界全体の発展に貢献してほしい
──最後に、TKC会員へのメッセージをお願いします。
千代田 皆さんの活動を知れば知るほど、「TKC全国会は勉強する会」と感じます。「揺れ動く独立性の中で、仲間同士で胸襟を開いてコミュニケーションをとったり、ときに恥をかき失敗したりしながら、仲間同士で『力』を付けていく会」だと確信します。今後ますます業界全体の発展に向けてリードしていっていただきたいと思います。
坂本 飯塚毅博士は、TKC全国会の会員は血縁的同志であると言われました。お互い専門家で独立しているからこそ、支え合う仲間であるべきと。事務所経営などで孤独を抱えて悩むのではなく、オープンに何でも相談できる仲間になれよと。千代田先生が今おっしゃった通りです。
千代田 TKC会員の皆さんが団結して「税理士の独立性」を重視し「租税正義の実現」に向けた運動を50年以上も実践されておられるのは、会員の税理士先生が、それは正しいからだと信じておられるからでしょう。「組織の運動論」として結び付けている点が、私のような外にいる者も思わず応援したいという気持ちにさせられるのです。中小企業の成長のために引き続き切磋琢磨し、「指導機能」を強化していただくことを強く期待します。
坂本 ありがとうございます。今回、巡回監査の本質は「三現主義(現地・現物・現人)」であることを確認できました。皆でしっかり全体の運動として実践していきたいと思います。
千代田先生には来月札幌市で開催されるTKC全国役員大会で基調講演をしていただけます。TKC会員一同、楽しみにしております。
(構成/TKC出版 清水公一朗)
千代田邦夫(ちよだ・くにお)氏
1944年生まれ。66年早稲田大学第一商学部卒業、68年同大学院商学研究科修士課程修了。鹿児島経済大学助教授、立命館大学経営学部長、熊本学園大学大学院会計専門職研究科教授、早稲田大学大学院会計研究科教授、2013~16年金融庁公認会計士・監査審査会会長等を経て、現在立命館アジア太平洋大学客員教授他。
(会報『TKC』令和7年7月号より転載)