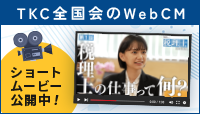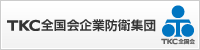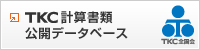寄稿
TKC全国会 これからの10年に向けて

TKC全国会会長
粟飯原一雄
平成25年の新年を迎え、TKC会員の皆様に謹んでお慶びを申しあげます。
日本経済は、失われた20年を過ぎ、今や混迷と「不確実性」の時代と言われています。特に、決められない政治が続く中で、1千兆円を超える国の借金とGDPの1.8倍の財政赤字、人口減少と超高齢化社会それに伴う毎年1兆円ずつ増える社会保障費、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)や原発を巡るエネルギー問題等々、解決すべき多くの深刻な課題を残しています。
2000年からの12年間で国政選挙が9回(衆議院選挙5回、参議院選挙4回)もあり、この間、内閣総理大臣は小渕内閣から数えて9人も誕生しています。平均在任期間が1年半という状況で、しかもその大半は民意を反映しているとは思えず、むしろ政局によるものであったと思わざるをえません。一国のリーダーが目まぐるしく替わる日本を世界はどう見ているのでしょうか。尖閣諸島等を巡る領土問題も、政治の混迷の隙を衝かれたように思えてなりません。木を見て森を見ずとよくいいますが、今の政治を「現在の日本は木も見ずして、葉の虫食い現象を見る議論が花盛りだ」と神野直彦東京大学名誉教授は指摘しています。
今回の衆議院選挙の結果、3年4か月ぶりに政権の座についた安倍晋三総理には、過去の自民党時代の反省と民主党時代の決められない政治から決められる政治に、そして一流国家としての強い経済、財政、外交を目指すビジョン、日本のあるべき姿を示して、日本経済の再生を図っていただきたいものです。
「会計の力」で中小企業再生と国力増大を
さて、このような厳しい経済環境下にあって、わが国は「会計で経営を強くする時代」を迎えています。明治6年(1873年)に福沢諭吉は『帳合之法』を著し、その中で簿記会計の普及を通して「天下の経済の面目を一新し、国力を増大する。」と述べています。すなわち、日本が近代国家となるためには、国家による殖産興業策だけではなく、民間の経済を活発化する必要があり、そのためには西洋の工業技術だけでなく、西洋の企業経営を発展させる礎となった簿記会計の「実学」を学び、活かすことが不可欠であると諭しました。
このような先覚者によって簿記会計が明治初年にいち早く採り入れられたことによって、その後日本の近代化を支える企業が数多く育成され、経済発展によって国力増大の礎が作られました。
それから約140年が経過し、ソ連の崩壊以後、世界は市場経済によって一元化され、グローバル化が急速に進展する中で、会計の重要性が再び高まってきました。平成11年から、アメリカ版グローバル・スタンダードといわれる国際会計基準が会計の一元化として順次波及し、いわゆる「会計ビックバン」と呼ばれる状勢が生まれました。これを故武田隆二先生(第三代全国会会長)は、「第2の会計ルネッサンスの時代」と表現しておられました。
しかし、国際会計基準の導入は、主に上場企業、大企業を対象とする動きであり、中小企業会計については、これと切り離して、確定決算主義を前提とする会計のあり方が検討され、平成17年8月に「中小企業の会計に関する指針」(中小指針)が公表され、続いて平成24年2月には中小企業の属性に見合った会計として「中小企業の会計に関する基本要領」(中小会計要領)が公表され、更に同年8月に「中小企業経営力強化支援法」が施行されるに至りました。この法律では、「中小指針」及び「中小会計要領」の普及とその活用を通じて中小企業の経営力の向上を図ることに加え、企業が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力を向上させ、財務経営力の強化を図ることが中小企業の経営革新促進のために重要であるとされています。
このような考え方は、まさに明治初期に我が国に採り入れられた簿記会計の原点である、会計を経営に活かし、「天下の経済の面目を一新し、国力を増大すること」そのものであり、会計のあるべき姿を体現したものと言えます。「会計」で中小企業経営者の財務経営力を強化していくことこそ、まさに現在の中小企業の「再生」、そして「国力増大」に繋がる喫緊の課題と言えます。
「TKCの強み」を活かす絶好のチャンス到来
振り返ればTKC全国会は、昭和46年(1971年)8月に結成され、既に40年を経過し、会員数1万名を超える大集団となり、今や国家、社会からも大きな期待を受けるまでになりました。
何故、TKC全国会は今日まで存続・発展し得たのか。まずそれは、創設者である飯塚毅初代会長の掲げた「職業会計人の職域防衛と運命打開」の基本方針に賛同した多くのTKC会員が、巡回監査を実行し、法令に準拠した最新のTKCシステムを駆使して関与先企業を支援し、会計事務所の経営基盤を構築してきたことにあると言えます。このような中で個々の会計事務所の評価の高まりと相まって、TKC全国会によって、職業関連法規の欠陥を是正する昭和55年及び平成13年の税理士法改正への貢献、税務行政円滑化を促進する電子申告の取り組み、K・F・S活動を通しての中小企業の黒字決算支援等が行われ、全国会活動の公共性が広く理解され、社会的評価が非常に高まってきました。
政治の混迷が続き、中小企業の経営環境はますます厳しさを増してきている中で、われわれTKC会計人の役割は、今後ともますます重要な局面にあると言えます。
TKC全国会は、平成11年に始まった「第一次成功の鍵作戦」以来、中小企業の経営を支援するさまざまな活動を展開してきました。それはまさに会計を経営に活かす活動でもありました。経営者に発想の転換、姿勢の転換、そして行動の転換を促し、継続MASシステムで経営者と将来を語り経営計画の策定を支援し、TKCの自計化システムの活用により、タイムリーな業績管理体制の構築を支援してきました。同時に巡回監査の徹底断行と書面添付の実践によって、決算書・税務申告書の信頼性を高めてきました。これらの巡回監査を基盤としたK・F・Sへの取り組みは、われわれTKC全国会が築いてきた新たな「ビジネスモデル」であると言えます。
この強みをさらに活かす絶好の機会が、今日めぐってきたと言えます。
このような状況を踏まえて、次月号で「これからの10年に向けたTKC全国会の政策課題」を纏め、骨太の方針としての「戦略目標」を提起させていただきます。
年頭に際しまして、会員の皆様には、まずもって現在取り組んでいる全国会重点活動テーマの最終年度として、その達成に全力を注いでいただき、最大の成果を挙げられることをご期待いたします。
(会報『TKC』平成25年1月号より転載)