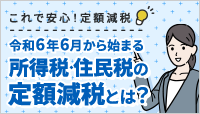「ネガティブ・ケイパビリティ」とは、どうにも答えの出ない、どうにも対処できない事態に耐える力を言う。2017年に『ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力』を上梓した帚木蓬生氏は「変化が激しい現代社会だからこそ、モヤモヤを抱えたままじっと耐える力が必要になる」と語る。
- プロフィール
- ははきぎ・ほうせい●1947年生まれ。作家、精神科医。東京大学文学部、九州大学医学部卒業。79~80年マルセイユ・聖マルグリット病院神経精神科、80~81年サンタンヌ病院精神科で研修。『閉鎖病棟』(山本周五郎賞受賞)、『逃亡』(柴田錬三郎賞受賞)、『蠅の帝国』『蛍の航跡』(2作品で日本医療小説大賞受賞)など著書多数。

──「ネガティブ・ケイパビリティ」とはどのような考え方ですか。
帚木 性急に解答や理解を求めずに、不確実さや不思議さの中にとどまることができる能力で、詩人であるジョン・キーツが発見し、精神科医であるウィルフレッド・ビオンによって精神分析における重要性が説かれた概念です。現代社会は変化が激しく不確実性に満ちていることから、目の前の問題を的確に、なおかつ迅速に対処する能力(ポジティブ・ケイパビリティ)の養成に夢中になりがちですが、現代社会において答えをすぐに出せるような事柄は、ほんのひと握りしかありません。すぐに結論を出せないような複雑な問題であふれているのです。
こうした問題に直面したときに力を発揮するのがネガティブ・ケイパビリティです。「より良い答えを導くためにモヤモヤを抱えたままじっと耐える」という考え方を頭の片隅に置いておくことで、仕事や生活が少し楽になります。
──近年、ネガティブ・ケイパビリティをテーマとした書籍が多く出版されたり、テレビ番組の特集が組まれたりと、「モヤモヤを抱えたまま耐える」という考え方が広がりつつあります。こうした社会の流れについて、帚木さんの考えを聞かせてください。
帚木 問題解決が叫ばれる世の中の風潮に疑問を持つ人が増えてきたのではないでしょうか。そもそも、人間の脳の仕組みとして、物事を理解しようとする性質があります。さらに、これまでの日本の教育は、正しい答えを早く導き出すことに重点が置かれていました。問題解決が社会で強調されているのは、この二つが要因として考えられます。
問題解決を強調することで陥りがちなのが問いの平易化です。これは問題を素早く解決するために、問いが持つ複雑さをそぎ落としてしまうことです。その結果、設定した問いが現実からかけ離れたものとなり、答えとして導かれたはずの解決策も机上の空論と化してしまう。今の世の中、誰もがこうした八方ふさがりの状態を少なくとも一度は経験しているのではないでしょうか。だからこそ、「解決を急ぐのではなく、モヤモヤを抱えたまま過ごしてよい」という姿勢が、多くの現代人の心をつかんでいるのだと思います。
手探りで作品を紡ぐ
──ネガティブ・ケイパビリティという言葉に初めて触れたのはいつですか?
帚木 精神科医になって5~6年が過ぎたころでしょうか。当時の私は精神科医として大きな壁に直面していました。当時は患者の具体的な症状や言動、振る舞いを精神分析の理論やマニュアルにあてはめて最適な療法を検討する「問題解決型」の診察が主流でしたが、病気を克服したにもかかわらず再入院してきた患者、症状が一切回復しない患者を多く目の当たりにし、次第に「このやり方で本当に病気を治せるのか」と疑問を感じるようになったのです。
こうした疑問を抱くなかで、たまたま読み進めていた「共感について」という医学論文で紹介されていたのが、ネガティブ・ケイパビリティです。「事実や理由をせっかちに求めず、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいられる能力」という記述を読んだときに、「問題を解決しないことも一つの能力なのか」と目から鱗が落ちるような思いをしました。それ以来、ネガティブ・ケイパビリティは私自身の人生を支えるキーワードとして、常に頭の片隅に置いています。
──ネガティブ・ケイパビリティは、作家や精神科医の仕事にどんな影響を及ぼしていますか。
帚木 作家としては普段の執筆スタイルに大きく影響しています。具体的には、作品やキャラクターの設定、台詞、結末などを細かく構想せず、手探りの状態で作品を紡いでいます。例えば『閉鎖病棟』(新潮社)という作品の終盤、ある登場人物が裁判にかけられるのですが、この展開も最初からこと細かに考えていたわけではなく、執筆を進めるなかで人物の言葉や裁判官とのやり取りが生まれました。とりわけ長編小説は先が長いですから、ディテールを細かく考えず、行き当たりばったりで書くことで面白い作品が出来上がるのです。
一方で、精神科医としては問題解決にとらわれない独自の治療手法の確立につながりました。私の診察は「身の上相談」そのものです。患者の話に耳を傾け、共感し、励ましの言葉をかける。解決方法が明確ではない患者に対しては、傾聴・共感・激励をひたすら繰り返しながら治療してきました。
──ネガティブ・ケイパビリティを意識しながら患者と接することも治療の一つなのですね。
帚木 興味深い事例を紹介しましょう。私はギャンブル依存症患者とのミーティングを30年以上、1~2週間に1回の頻度で開催しています。このミーティングは最近の出来事を1人ずつ話していくという形で進行します。「パチンコ屋に行きそうになったが我慢した」「ギャンブルしそうになって家族に叱られた」など、各自が話したいことを話し、他の参加者はひたすら耳を傾けるのです。このミーティングにはルールがいくつかあって、例えば「自分の体験だけを話すこと」「他人の話にコメントや補足、アドバイスをしないこと」などです。
こうしたルールを設けることで、参加者は他人の反応を気にせずに話ができますし、自分自身の行動を顧みたり、他人の話を参考にしたりしながら依存症の克服を目指すことができます。実際にミーティング後の参加者を見ているとほぼ全員が朗らかな表情をしており、このミーティングを通じて多くの患者がギャンブル依存症を克服していきました。
この手法はビジネスシーンにも応用できます。名前をつけるならば、「内省する会議」がふさわしいでしょうか。例えば、社員がこの1週間に直面した課題や収穫、失敗事を話すだけのミーティングを行うことで、社内の風通しの改善や社員のモチベーションアップが期待できます。発言へのツッコミはもちろん、指示やフィードバックも厳禁なので参加者は臆せず発言できますし、全員の話を参考にしながら自分自身の活動を振り返る良い機会になります。
頭の片隅に留めておく
──ネガティブ・ケイパビリティを身につけるにはどうすればいいのでしょうか。
帚木 ネガティブ・ケイパビリティは訓練して身につくものではありません。頭の片隅に置いておくだけで良いのです。ただ、ネガティブ・ケイパビリティを意識するためのヒントとして、音楽や美術、文学など芸術作品に触れることをお勧めします。例えば、クラシックのコンサートに足を運ぶ、絵画を鑑賞するなど、答えのない世界に積極的に触れることでネガティブ・ケイパビリティを自然と意識できるようになり、問題解決に雁字搦めになった生活から距離を取ることができると思います。
(インタビュー・構成/本誌・中井修平)