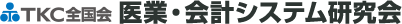実現へ進む「人工冬眠」の研究 ―冬眠で健康長寿になれる!?―
人工冬眠で数百年眠り続け、目を開けると未来にタイムトラベルしている――。SFの世界ではお馴染みの人工冬眠だが、これを現実のものにしようとする研究が進んでいる。しかも人工冬眠が実現すれば、救急搬送時のリスクを減少させ、やがて発病や老化を防止できるようになるなど、医療のかたちを変える可能性もあるという。理化学研究所の砂川玄志郎氏に、人工冬眠に関する研究の現在と今後の展望についてうかがった。
砂川 玄志郎
理化学研究所 生命機能科学研究センター
冬眠生物学研究チーム チームリーダー
Sunagawa Genshiro
小児科医。大阪赤十字病院、国立成育医療研究センターで勤務後、京都大学大学院医学研究科博士課程修了。博士(医学)。理研生命システム研究センター研究員、生命機能科学研究センター基礎科学特別研究員などを経て、2020年より現職。
聞き手/TKC全国会医業・会計システム研究会 代表幹事 丸山定夫
取材協力/本誌編集委員 加藤田敏孝
マウスを冬眠させることに成功
2040年に人工冬眠が実現?
──まずは、砂川先生が冬眠研究を開始されるまでの経緯からお聞かせいただけますか。
砂川 もともと、私は医学部を卒業後、国立成育医療センター(当時)などで、研修医としてICUに入るような重症のお子さんを診ていました。同センターには全国から重症の小児患者が集まってきます。しかし、なかには重症すぎて搬送できず、「なんとかならないのか」と悔しい思いをすることがありました。
救急搬送の難しさについて考えていたちょうどそのころ、マダガスカルで冬眠するキツネザルが見つかったという論文を目にしました。そのとき、人類と同じ霊長類が冬眠できるのであればヒトも冬眠できるのではないか、そうすれば、たとえば患者さんが危険な状態の時に冬眠に誘導できれば治療までの時間を稼げるのではないか、と思い、冬眠の研究をしようと決意したのです。
臨床の合間に勉強して大学院に入学し、同時に理化学研究所の研究チームに研究員として在籍。まずはおよそ10年、睡眠の研究に専念しました。その後は本格的に冬眠に関する研究を始め、今に至ります。
悔しい思いをした研究の原点を忘れないようにするためにも、現在も週に1回ほど、神戸市内の病院で小児救急を担当しています。
──そもそも、学術的に冬眠はどのように定義されているのでしょうか。
砂川 「定義」というものはその時点で得られる知見で精いっぱいきっちりしたことを言っているともいえます。
そういう意味では、冬眠の定義については、原理がわかっていないためあいまいです。しかし、哺乳類の代謝が落ちて、体の動きが鈍くなった状態であるということは共通して認識されています。体温の維持は哺乳類にとって重要な機能であり、自ら体温を低下させているのに死んでいない状態というのは他にないわけです。ただし、その状態がどのくらいの期間続くかなどは動物によってバラバラですから、定義が難しいというところです。
実を言うと、睡眠と冬眠の違いについても、まだ明確な答えはないのです。睡眠中も基礎代謝が少し落ちるものの、冬眠では普段の数パーセントにまで落ちて、異常なほど体温が下がります。しかし脳のメカニズムが解明されると、睡眠と冬眠はほとんど同じという可能性もありうるわけです。
──これまで先生が冬眠について研究されてきたなかで、大きな進展につながったものはありますか。
砂川 2020年に、筑波大学の櫻井武教授らのグループと発表した研究成果があります。これはマウスの脳の一部に存在する神経細胞群(Q神経)を興奮させることで、体温と代謝が数日間にわたって著しく低下し、本来は冬眠しないマウスを冬眠のような状態(QIH※)にできることを発見したものです。
これにより、まずは冬眠研究そのものがやりやすくなりました。というのもそれまでは、自然界では年に1回しか生じない冬眠を、実験室で研究対象とすることは困難でした。しかしマウスをいつでも冬眠のような状態に誘導できるので、冬眠と病気の関係や、冬眠と寿命の関係などについての仮説を実験的に検証できるようになったのです。
また、冬眠しないはずのマウスで成功したということは、同様にヒトも冬眠のような状態に誘導できる可能性が出てきたということを意味します。明確な根拠があるわけではないのですが、2040年頃にはヒトを含めた大型動物においても、数時間程度の人工冬眠であれば可能になると思っています。
──あと15年ほどで人工冬眠が実現する可能性があるとは驚きです。
砂川 現時点で、本来冬眠しない動物であっても冬眠に近い状態にすることができていて、あとはヒトの脳でどこまでできるかというところが課題ですが、人の脳のどの部分を操作すれば代謝が落ちるか、という目処はある程度ついています。
しかし、脳はなかなか直接触れられない場所ですから、どうリーチするかが課題です。ただ、これも今から10~20年以内にある程度解決できるだろうと見込んでいます。
もちろん、自分に発破をかける意味でも言っています。2040年というのは、自分自身が研究者としてしっかり取り組めるのがそれぐらいまでだと思いますので、それまでに数時間レベルの人工冬眠を実現させたいと思っています。
──まずは数時間の人工冬眠を可能にすることが重要なのですね。
砂川 たとえ数時間であっても、人工冬眠によって、安定した状態での救急搬送が可能になれば死亡率を下げられますし、さまざまな後遺症も防げるようになります。
それより長い期間冬眠させることについては、冬眠自体は動物たちが普通に行っていることですから、少なくとも数か月単位であれば、ヒトでも可能だろうと考えています。一方で、冬眠の時間が長くなればなるほどもちろん実現は難しくなるでしょうし、自然界では冬眠が1年を超えることはありませんから、おそらく1年というところに大きな壁があるのではないかと思っています。
ゆくゆくは私よりもっと若い世代の研究者たちによって、冬眠の期間を伸ばす研究が進んでいくことを期待しています。
動物での研究が進んでもヒトへの適用が課題
──現在はどのような研究に取り組んでいるのでしょうか。
前者についてですが、現在、小型哺乳類を冬眠に近い状態に誘導するときには、動物の脳にある特定の神経だけを操作するという極めて細かいことを行っている上、遺伝子の改変などを多用していますから、実験動物でしかできません。そこで遺伝子改変などをせずとも実現可能にするよう研究しており、今のところ2つのアプローチがあります。
1つはこれまで取り組んできたような、脳を刺激して冬眠を誘導する方法。睡眠もそうですが、やはりさまざまな現象が脳を中心にして起こっている以上、「脳のこの部分を操作すれば全身がこう変わります」となれば非常に分かりやすいですし、生理的にも自然なことなので、これが理想です。
もう1つは、末梢組織をいきなり冬眠状態にするという、自然界の冬眠とは全く異なる方法です。自然な冬眠はあくまで脳から始まりますが、変化自体は現場、つまり末梢組織で起こります。脳からみれば、心臓や肝臓などの臓器から指先の組織まで末梢組織にあたりますが、それらの組織がすべて代謝が落ちた結果が冬眠です。
脳へのアプローチはとても大変ですが、末梢臓器はリーチしやすい。たとえば薬を注射すれば血液を通じて臓器に届きます。自然界と異なっていても、「人工」冬眠ですから冬眠できてしまえばいいわけです。
これはどうやって研究するかというと、冬眠している動物としていない動物を用意し、臓器、たとえば肝臓なら肝臓を徹底的に比較します。どこに違いがあるのかを把握して、その違いを引き起こす薬を作り出せれば肝臓を「冬眠」させることができます。
──人工冬眠を実現させるためのアプローチはさまざまなのですね。もう1つの「効果の研究」とはどういうことでしょうか。
砂川 人工冬眠による効果のエビデンスを示す、ということです。もしヒトが冬眠できるようになったとしても、たとえば老化が進んでしまうとか、新たな病気にかかるとか、そうしたネガティブな要素がないとは言い切れません。また、冬眠で本当に患者搬送の時間稼ぎができるかどうかも、まだ確認されていない以上、私たちがそうしたエビデンスを示していく必要があるわけです。
具体的には、病気にかかった動物を冬眠させて病気が進行していくかどうか観察したり、同様に動物が冬眠中に老化が止まるかを確認したりしています。
──人工冬眠の実現までに、先生が障壁と感じていることはあるのでしょうか。
砂川 今技術をヒトに適用しようとしたときが問題になると思います。ヒトで試すというのは相当後になりますが、技術がどの段階に達したら試していいのかは不明確です。
また、人工冬眠は今のところ病気の進行を遅らせることが目的で、今ある治療のかたちとは大きく異なりますから、治験の扱いをどうするかなども課題となってくるでしょう。
ただ、冬眠しても安全であることさえ示せれば、効果などの知見は動物による実験などで蓄えられますから、ヒトへの適用もスムーズになるのではないでしょうか。
積極的に治す「攻めの冬眠」で健康長寿にもなれるか
──この先の研究の展望についてお聞かせください。
砂川 ここまで基本的に、病気の進行を遅らせるという目標を前提にお話をしてきましたが、最近はもう一歩先に進んだことを考えています。それは冬眠で進行を遅らせている間に治療する、ということです。
今の医学では発症のメカニズムがわからずに治せない病気がある一方、発症理由がある程度わかっていても病勢が強すぎて治療できない病気もあります。その最たるものが、がんです。さまざまな人たちが治療しようと研究していますが、細胞が異常に増える勢いが強すぎて治せないわけです。
そうした病気にかかった患者さんを冬眠に誘導すれば、代謝がゆっくりになりますから病気の勢いもゆっくりになると考えられます。しかし進行が遅れただけでは目が覚めればまた勢いが強まってしまい、冬眠した意味がないかもしれません。
そこで、いわば敵の動きを止めている間に治療するというアイデアです。残念なことに、ヒトの持っている防御力、つまり免疫も冬眠中は低下しますから、人工的に冬眠しても低下しない免疫力を入れてあげればよいと思うのです。いわば「攻めの冬眠」です。
まだできていないから自由にものが言えるという面もあるのですが、「冬眠したから治せる病気」も出てくるのではないかと思います。冬眠で病気の進行を遅らせることはできると確信していますが、攻めの冬眠のステップまで実現できれば人類に相当大きな貢献ができると思っています。いまはそうした青写真を描きながら準備している段階です。
──冬眠で病気を治せるとは夢が広がりますね。
金間 「攻めの冬眠」は老化対策にも使えるのではないかと思います。老化は産まれた瞬間から始まっていますが、若いうちは老化のスピードがそこまで速くないということと、老化への抵抗力があるので、一見老化していないように見えます。それが歳を取るにつれ、老化に対して修復が追いつかなくなるから老化していくのです。
そこで冬眠している間に老化の修復を少しずつでもできれば、たとえば1か月に1回、人工冬眠でメンテナンスし、リフレッシュするような世界があるかもしれません。定期的なメンテナンスならばコストも計算でき、事業にすることも可能です。無限の生命は難しいとしても、今よりも長く健康に生きられる時代が来るのではないかと思います。
また、冬眠というのは脂肪を消費しますからダイエットにもなります。もちろん走ったり運動するほうが速く消費できるのですが、病的肥満のように、服薬していても太ってしまう人には効果的ですし、走る気力がないような人には魅力的でしょう。
人工冬眠の実現は世界平和にまでつながる
──冬眠が実現すると社会の常識や法制度まで変わってきそうです。私たち税理士からすると、冬眠で相続の扱いがどうなるのかなども気になるところです。
──医療との関係でいえば、今の医療では治せない病気でも、冬眠でタイムトラベルして、未来で治療を受けることもできそうですね。
砂川 確かにそれもわかりやすいシナリオですが、ある意味では神頼み的なところがあるようにも思われます。病気の治療法が見つかるまで冬眠するのは、いつまで冬眠すればわからないですからコストの計算ができないわけで、実現するとしても一番最後か、あるいはとてつもないお金持ちしかできないと思います。
これは私の予想ですが、おそらくヒトのトータルの寿命は大きくは変えられないと思います。再生医療や若返り研究など何か全く異なる技術が登場すれば別ですが、1000年生きられるようになるのは難しい。しかし人工冬眠が実現すれば、1000年先にタイムトラベルして未来の景色を見られるかもしれない。そういう意味ではロマンがありますよね。
──1000年後の世界がどうなっているのか、想像がつきません。
砂川 まさにその通りです。ここまで冬眠が生物にとって安全かどうかという話をしてきましたが、人工冬眠におけるリスクはそれだけではありません。冬眠中は、外の世界で災害や戦争が起こるリスクもあります。それらを含めて安全をすべて担保できていなければ、冬眠でタイムトラベルするかどうか判断できないわけです。
そう思うと、実は数十年単位の冬眠というのは、私たちのような研究者が一生懸命に研究開発して安全な技術を確立したとしても、社会や公共インフラの整備、もっといえば世界平和が実現していなければ誰も希望しないと思うのです。ということは、たとえば冬眠を希望するお金持ちがいれば世界平和に向けた投資をするかもしれません。私たちが技術をつくっておけば、やがて世界の平和につながるのではないか――。そんなことも考えています。そのためにも、数時間単位での人工冬眠を実現させ、医療に活かせるよう、研究を続けたいと思っています。
(2024年11月18日/構成・本誌編集部 川村岳也)