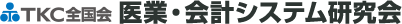「最近の若者」の思考の特徴とは? ~若者が働きやすさを感じる職場のつくり方~
現代の若者たちといえば、社会問題への関心が高く物怖じしない「Z世代」のイメージがある一方、主体性や積極性に欠けるという批判もある。今の若者たちはどのような思考で行動しているのか。そして人材難のなかで辞める若者を少なくするためには、どのような職場づくりが求められるのか。マーケティングやモチベーション論などを専門とし、『静かに退職する若者たち』(PHP研究所)を上梓した金間大介教授に話をうかがった。
金間 大介
金沢大学融合研究域融合科学系 教授
東京大学未来ビジョン研究センター 客員教授
Kanama Daisuke
横浜国立大学大学院工学研究科物理情報工学専攻(博士(工学))、バージニア工科大学大学院、文部科学省科学技術・学術政策研究所、北海道情報大学准教授、東京農業大学准教授、金沢大学人間社会研究域経済学経営学系准教授等を経て、2021年より現職。
若者の半数は「いい子症候群」
自分だけ目立つのを回避する
──金間先生は「現代の若者」の特徴をどのようにとらえておられますか。
金間 私自身はもともと経営学が専門ですから、各企業の皆さんから若手社員についての話をうかがう機会が多いのですが、よく聞くのは「素直で真面目でいい子で優秀」というキーワード。次いで「コミュ力(コミュニケーション能力)が高く、協調性がある」という評価です。
こうしたポジティブな性質は、新入社員への研修や、配属後の対話などの場面で感じていらっしゃるのだと思います。特にいまの新入社員については、学生時代にコロナ禍があったにもかかわらず、対話ができて協調性があると評価されます。
一方で、同時に「主体性がない」「自分の意見を言うところを聞いたことがない」「質問に手を挙げない」という声も聞きます。
これらは産業界の皆さんが今の20代をどう見ているか、あるいはどう見えるか、ということを示していますが、私はこうした性質を持っている若者を「いい子症候群」と呼んでいます。
つまり、目立つのが怖くて、自分がどう見られているかをいつも気にしながら行動を選択している。横並びがよくて100人のうちの1人としていつも埋もれていたい、と思いながら生活している若者が多くなっているのです。
いまの若者の気質としては、およそ5割くらいが「いい子症候群」ではないかと思っています。
──いい子症候群の若者というのは、人前で褒められるのを嫌がるそうですね。
金間 まさにいい子症候群の一番わかりやすい特徴です。たとえよいことであったとしても、いい子症候群の若者は人前でほめられることを「上に目立つ」ととらえるので、嫌がってしまうのです。
──今の若者世代である「Z世代」※といえば、各種メディアで取り上げられているように、社会問題への意識が高く、物怖じせずに発信するという印象があります。
金間 そうした、いわゆる元気なZ世代というのは「自己実現系」あるいは「変人」と言っていますが、これは全体の1割くらいです(図表参照)。
しかし実態としてはそうした若者の割合はかつてないほどに少ない。各時代の若者を対象とした調査研究によると、自ら事業を起こしてみたいと思う若者は過去最少という状況です。
──過去最少というのは驚きです。そうした傾向は世界でも共通なのでしょうか。
金間 この状況は日本のみの話だと思ってください。私もさまざまな国の若者を対象に調査しましたが、若者がこうした状況になっているのは日本だけです。
──それでは、なぜ日本でのみ、そのような状況になっているのでしょうか。
金間 複雑で多様な要因が関係していると思います。私としては、大きく分けると、社会経済、教育、家庭環境の3つが要因になっていると思っています。
一番わかりやすいのは社会経済の状況かと思いますが、少子高齢化、特に少子化です。人口動態として圧倒的に若年層が少なくなっている。私は人口減少自体はまだ大きくは影響していないと思っていますが、生産年齢人口の大幅な減少が一番の課題です。そのなかで高齢化も進み、もはや「若いというだけで勝ち」という状況になっているのです。
──「若いだけで勝ち」とは、どういう意味でしょうか。
金間 生産年齢人口が減少しているにもかかわらず、社会・経済の構造として、今なお昔と同様に、若い人を下から入れて組織を支えてもらう、というシステムが続いてきています。
逆に言えば、若い人が来なければ組織が保てず、ひいては経済や社会を動かせません。ですから若い人は絶対に入れなければならない。しかし数が少ない。その結果、若者の奪い合いになり、初任給などの上昇を招いている。これが「勝ち」ということです。
本来であれば、若年層人口の減少に合わせて組織構造も変革すべきでした。簡単にいえば、若い人が入ってこなくても成り立つビジネスのあり方を考えるべきだったのです。しかしそうした変革はほとんど手つかずのまま今に至っている状況です。
──2つ目の要因である「教育」についてはいかがでしょうか。
金間 今の若者は小学校でゆとり教育を受けてきた世代ですが、一般的なゆとり教育の批判にみられるような「競争で順番をつけない」ということ自体は、いい子症候群の増加とはそこまで関係していません。
重要なのは、ゆとり教育が「個性を尊重しながら、みんなで協調性を発揮する」という教育だったことです。
どういうことかといえば、個性の尊重ということで、若者たちは「人にはそれぞれの個性があって、それを発揮することが自分の幸福にとっても社会にとっても大事」と教えられます。
その一方で、若者たちは「みんなで協調してこの国を盛り上げていこう、絆を大切に」とも教わることにもなります。
この内容を実際の教室に導入することが困難だったと思われます。たとえば小学校の教室では、個性の尊重のために、先生が順番に発言させて、「それぞれ意見があるから皆さんの意見を聞きましょう」と教える。
一方で順番を飛ばしたり、人の意見を否定したりする子どももいます。そうすると先生は「順番を大事に」「ひとり1分を守ろうね」と注意します。
「個性の発揮とはとがったものである」とされながら、実際にとがったことをすると怒られてしまうわけです。
そうしたなかで、子どもたちは「個性を尊重するよりも、まずはルール」「個性の発揮には『マニュアル』がある」と学習していきます。こうして「決められた個性の発揮の仕方」を小学校から大学まで学んで社会人になると、「いい子症候群」の若者になるのではないか、と私は思っています。
──3つ目の「家庭環境」というのは、いい子症候群の若者の増加とどう関係するのでしょうか。
金間 いまの20代の親世代はざっくり考えると子どもの年齢プラス30年程度、つまり50代が多いかと思いますが、たとえばその真ん中にあたる55歳について考えてみると、大卒であれば社会人として33年働いてきている。この「33年」は、1991年のバブル崩壊から現在までがちょうど33年で、いわゆる失われた30年と合致します。
失われた時代の間にずっと社会人だったのが20代の親世代です。日本経済が停滞を続けたなかで、ずっと子育てをしてきた。そのため、少しでもリスクが減るようにと、守りの子育てになったのではないでしょうか。たとえば「目立つと大変なことになる」「地元に帰ってきて、安定した公務員になってほしい」と伝える親が多くなるのは、ある意味当然のことではないかと思います。
上との対話はコストが高い
本音を聞きだすのは「不可能」か
──近年は、本音を言わずに退職代行サービスを使って突然退職する若者が増えているといいます。
金間 そうした行動をする若者がまさにいい子症候群の若者です。どういう思考でそうした行動につながるかというと、いい子症候群の若者は上の立場の人とのコミュニケーションを怖がり、ストレスに感じる。ですから、退職の申し出時に質問されるのを嫌がり、代行サービスを使うのです。
上の立場の人からすれば、「辞めたいです」の一言で済むじゃないか、と思われるかもしれません。しかし、いい子症候群の彼らは、辞めたいと言ったらどうなるかを頭の中で緻密にシミュレーションします。当然のリアクションとして、「どうして?」と聞かれ、「もうちょっと考えてみてくれないか」と言われる。この2つの反応が必ず返ってくるとわかっているわけですが、何と答えていいのかがわからないので、この返答が大嫌いなのです。だから退職代行サービスという手段で「逃げる」ことになります。
──たとえ一言でも、上の立場の人とのコミュニケーションを怖がったり、避けたりするわけですね。
金間 特に、「自分に矢印が向く」ような会話を嫌がります。「辞める」というのがまさに典型例ですが、どうして辞めたいかを聞かれたとき、多くの若者は上司や先輩から納得してわかってもらえるような返答を用意しなければなりません。当然、本音は言いません。かといって、どうやってウソをつけばいいのかも、きっと素直には出てこない。
彼らは「この上司はこういえばこう返してくるだろうな……」と考えるうちに、コミュニケーションに対するコストがとても高く感じます。それで、「だったら退職代行サービスに数万円払ってしまおう」という発想になるわけです。
──コミュニケーションのコストよりも、サービスを利用するコストのほうが安く感じてしまうのですね。そうした若者から本音を聞きだすのは難しいのでしょうか。
金間 以前は「きわめて難しい」と言っていたのですが、もはや「不可能」に近いでしょう。理由は明確で、本音を引き出そうするほど、本音を隠されるからです。
そもそも、若者にとって本音を話していいことがあるのでしょうか。若者の立場からすれば、本音を話すことは「何かを握られる」ことだと思うのです。友達の間ですら、本音を話すことはほとんどないのではないでしょうか。話すとしても、ほんの一握りで、本当に仲のいい5~10人か母親の2択だと思います。若者からすると、本音を話せば何かを握られて、それがずっとつきまとってしまうかもしれないと考えるのではないでしょうか。
実際、上の立場の人からすれば、「本音を知りたい」というのは、組織のため、部署のため、知りたい自分自身のため、つまり自分の利益のために思うわけです。相手の利益のために本音をさらけ出すという状況を、若者はよく知っているのだと思います。
若者を探ろうとせず「武装解除」して反応を待つ
──本音を聞き出すのが「不可能」だとして、それでも仕事上、若者と円滑なコミュニケーションをとっていかなければならないとしたら、どういったことに気をつけるとよいのでしょうか。
金間 先ほど言いました通り、まずは本音を引き出そうとしないことです。本音を引き出そうと考えた瞬間に、いい子症候群の若者はそれに対抗する「スイッチ」を入れるだけです。
今の若者は、「この人に対しては、どうしたらこの場を円滑に終わらせることができるか」というコミュニケーション能力に非常に長けている存在だと思ってください。こうした若者に対しては勝ち目はない。どうやったら本音を引き出せるか、どうしたら若者は思うように行動してくれるか、という思考を働かせた瞬間、彼らは守り一辺倒になっていきます。
ですから、やるべきことはこの逆です。つまり若者を探らない。むしろ、若者に話しかける側がオープンになってください。
ポイントは「矢印」です。自分の話をするときは、自分に矢印が向いていますよね。このときに気を付けていただきたいのは、自分について語ることで相手にこうなってほしい、と考えないようにすることです。たとえば武勇伝とか失敗談を披露し、「自分は若い時にこんなことをやらかしたから大丈夫。だから君もがんばれ!」と伝えるようなケースです。しかし、これは止めたほうがよいでしょう。若者は「この話は最終的にこちらに矢印が向いてくる」と警戒します。
ですからぜひ、本当に最近気にしていることや、興味を持っていることについて話してください。特におすすめしているのが、前向きに思っている内容について話すことです。たとえば、「いまうちの診療所はこういう状況だけど、将来的にはこうしていきたいと思っている」といった話です。ぜひ、展望や夢を聞かせてあげてください。「だから頼むよ」とは言わずに、あくまで「自分はこうしていきたいと思って頑張っている」という話をしてください。
もっとも、こう話したとしても、若者からはおそらく反応はありません。しかし、「この人は素で自分の話をしたな」という印象は残ります。これを繰り返していくと、いつかリアクションが来るでしょう。1年後か、あるいはいつになるのかはわかりませんが、「自分に手伝えることがあったら何でも言ってください」という言葉が出てくると思います。
──上司や先輩が何か特別なスキルを身につけるというよりも、オープンにさらけ出すことが必要になるのですね。
金間 今の上司や先輩は「対若者」の理論武装、あるいはスキル武装をしすぎていて、若者にそれを見透かされているのではないでしょうか。確かに素で話す機会がこれまでなかったかもしれませんが、「武装解除」して、素で話してみることをおすすめします。実際、結構難しいと思いますが、それこそ挑戦ですね。
価値観を明確にすることで若者は働きやすさを感じる
──クリニックをはじめとする組織で若者を含めて円滑に運営していくために、意識するべきことはあるのでしょうか。
金間 やっていただきたいことが1つあります。それは組織の運営ルールを明確にして、それを知らしめることです。
先ほども少し触れましたが、「将来はこうしたい」という価値観を、まずは自分のなかで明確にして、他人に語れるようにしていただく。そしてそれをルールに落とし込んでください。
経営者、あるいは管理職の方のなかには価値観やルールがあいまいになっている方もおられます。しかし将来の方向性をあいまいにしておきながら、若者に主体性を発揮してほしいと期待していないでしょうか。この場合、むしろ上に立つ人の価値観やルールがブレているからこそ、若者が指示待ちになってしまい、主体性を発揮できないのです。
たとえば「このクリニックでは、この目標を実現させたい。だから今日から毎日〇〇に取り組みます。守らなければ注意します」とはっきり伝えてください。そして守らない人には「あの時こう話したよね、わかってくれたと思うのだけど、何か質問はありますか。なければ、改めてお願いします」と伝えます。そしてこの姿勢を、全従業員に対し一貫してください。もしその〇〇がうまくいかなければ、潔く認め、謝罪し、修正案を提示してください。この点が一番大事です。
こうすることで、若者は「働きやすい」と感じるようになります。若者は理不尽を嫌うので、若者にとって嫌な職場とは価値観が曖昧で、不公平な職場のことなのです。「院長は厳しいけれど、フェアでわかりやすい」というほうが働きやすい職場になると思います。
特に、いい子症候群の若者は「資格さえあればあとは安心だ」と考える傾向にあるので、看護師をはじめとする資格制の職種には多くなりがちです。価値観とルールを明確にして、それにもとづいた運営をしていただきたいと思います。
(2024年10月25日/本誌編集部 川村岳也)