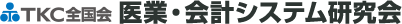どうなる第8次医療計画 ~2040年へ向けた最初の一歩~
2025年には団塊の世代がすべて後期高齢者に、2040年には団塊ジュニア世代がすべて高齢者となり、人口動態が大きく変化する。2024年度から開始される「第8次医療計画」は、こうした超高齢社会における医療提供体制の構築に向けた第一歩となる。個々の医療機関ではどのような取り組みが必要となるのか。「第8次医療計画等に関する検討会」構成員であり、社会医療法人祐愛会織田病院で「次世代型退院支援」など一線を画す取り組みを行う織田正道理事長に話をうかがう。
織田 正道
公益社団法人全日本病院協会 副会長
第8次両計画等に関する検討会 構成員
社会福祉法人祐愛会 理事長
聞き手/ TKC全国会医業・会計システム研究会 広報委員会委員 加藤田敏孝
Oda Masamichi
日本大学医学部卒業後、久留米大学、佐賀大学医学部の勤務を経て、1990年より医療法人祐愛会織田病院院長に就任、1998年に同理事長に就任。
人口減少を見据えた効率的な医療提供体制の構築を
──2024年度から第8次医療計画がスタートしますが、まずは策定にあたっての背景をお聞かせいただけますか。
織田 第8次医療計画の期間内には、2025年に団塊の世代がすべて後期高齢者となります。さらに、2040年には団塊ジュニア世代がすべて65歳以上となり、高齢者人口がピークをむかえ、生産年齢人口が現在と比べて1,400万人ほど減少します。今後マンパワーが不足するため、効率的な医療提供体制の構築は不可避であることは、誰が考えても明らかです。
──第8次医療計画の特徴としては、現時点でどのような点が挙げられるのでしょうか。
織田 第8次医療計画では、これまで5疾病5事業であったところ、「新興感染症対策」を新たな事業として盛り込み、5疾病6事業となりました。また、在宅医療にも重点が置かれるでしょう。
これまで、地域医療構想及び医師確保計画、外来機能報告等、在宅医療及び医療・介護連携、救急・災害医療提供体制等、に関するワーキンググループが設けられ、重点的に議論されてきました。
──地域医療構想については、2025年で目標年次を迎えますが、現状をどう捉えていますか。
織田 地域医療構想は2014年からスタートしました。将来推計人口をもとに、2025年時点で必要となる病床数を、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つの医療機能ごとに算出し、超高齢社会にも耐え得る医療提供体制の構築を目的としています。
構想計画時は、機能分化しないまま高齢化を織り込んだ場合、病床数は152万床程度必要となるとの試算でしたが、それを機能分化することで、115~119万床程度にしようとしていました。では、現在の病床数がどれぐらいかというと、119万床です。つまり数字の上では、目標としていた値になっています。
──他方、病床機能ごとに見ると、急性期病床・回復期病床には目標とは乖離があります。
織田 これは確かに数字の上ではその通りで、急性期病床は予定していたより、13万床過剰で、回復期は17万床不足していることになっています。一方で実態は数字ほどの乖離はないと考えています。回復期病床が少なくて困っている医療圏はありません。
というのも、実際には高度急性期、急性期から軽快するまでの自然経過の過程で、医療資源投入量でいくと回復期に属する期間があります。そうした現実を無視して、現在の急性期病床を回復期病床にしてしまうとおかしなことになってしまいます。
──今後、地域医療構想はどのような形になるのでしょうか。
織田 地域医療構想は基本的に2次医療圏を1つの構想区域として定めていますが、「第8次医療計画に関する意見のとりまとめ」においてはこの医療圏の見直しについて検討が求められています。
とはいえ、2次医療圏の見直しは実際には難しいと思います。
今問題になっているのは主に都市部です。高機能病院が隣接しているため、外部からの流入が激しく、地域医療構想が成り立たなくなっているのです。地方については、これまで少しずつダウンサイジングを図りながら、何とかやり繰りしてきたわけで、これを見直すとなると、医療圏を統合したがために、目の前にあった病院がなくなってしまうということになりかねません。
──医療圏は、都道府県を跨いでの設定も可能ですが、そのような医療圏は1つもありません。
織田 その通りです。しかし、これは仕方がないことだと思います。地図上で隣接しているといっても、その地域固有の実情があり、日常生活の動きや交通の事情があった上で、2次医療圏が設定されているわけで、そこには地べたの人間関係があります。そういったものを無視して、地図の上だけで考えるのは無理がありますし、見直しにしても、時間をかけた協議が必要でしょう。
かかりつけ医機能報告制度でこれまで以上に役割が明確に
──「外来機能報告」については、2022年4月に、医療計画に先んじて開始されました。
織田 外来機能報告は、「医療資源を重点的に活用する外来」等の実施状況について都道府県への報告を義務付ける制度で、かかりつけ医機能を担う医療機関、紹介受診重点医療機関を地域内で明確化させ、連携を促進させる意図があります。基準を満たした医療機関は、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向があるか確認を行い、協議するとされています。医療機関にこの意向がなければ、自治体は、「紹介受診重点医療機関になれ」ということは言えません。地方では診療科の偏在が激しく、公的病院しか特定の診療科がないということがあります。「紹介受診重点医療機関」になると、患者さんの自己負担が高くなってしまうので、地方の病院は手を上げにくい現実があります。
──かかりつけ医機能が明確になることで、これまで以上にその役割が重要になってきますね。
織田 先般、「かかりつけ医機能報告制度」の創設や後期高齢者医療制度の見直し等を柱とする全世代型社会保障法案が国会で成立しました。これはかかりつけ医機能を「身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能」と定義し、医療機関にその有するかかりつけ医機能を都道府県に報告させる制度です。これまで以上に、かかりつけ医療機関を明確にしようとしていることが読み取れます。
在宅医療については、今後の需要の増加に向けて、地域の実情に応じた体制整備が求められます。なかでも、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を医療計画に位置付け、在宅医療圏域に少なくとも1つは設定することになります。
在宅医療の提供体制で必要となるのは、①退院支援、②日常の療養支援、③急変時の対応、④看取り、の4機能となります。①~④の機能確保にあたり、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」として念頭にあるのは、在支病・在支診です。そして、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」は市町村、保健所、医師会等です。中小病院の生き残りのためには、在支病になることも選択肢の1つではないかと思います。
──在宅医療圏域については、「適切な」圏域が求められます。
織田 「適切な在宅医療圏」とは、できる限り急変時の対応がとれる体制が構築できる圏域ということです。地域にもよりますが、2次医療圏では広すぎると思います。市町村単位、さらに小さい単位が適切なのではないでしょうか。しかし現在の在宅医療圏の7割近くが、2次医療圏をそのまま在宅医療圏として設定していますので、引き続き検討が必要です。
そして、今後重要になる医療と介護の連携ですが、これが非常に難しい。医療と介護というのは基本的に法律も違い、その建付けも違いますし、組織のあり方も違います。その上、人手不足やこれまでの連携の実績不足もあって、まだまだ連携が上手くとれていませんが、いずれにしてもこれは必須です。地域ごとに問題点を洗い出して、それを1つひとつ解決して行くことが次へつながります。
──連携という点でいくと、6事業目の「新興感染症対策」も平時からの連携が求められますね。
織田 平時の連携なくして、有事に急に連携がとれることは絶対にありえません。平時から連携が行われて、信頼関係があるからこそ、有事に連携が取れるのです。ですからコロナ禍で地域医療構想が進んでいた地方は、連携という点ではあまり問題にはなりませんでした。問題が起こったのは都市部が多かったように感じています。
85歳以上人口の急激な増加に 次世代型退院支援で立ち向かう
──第8次医療計画でも、在宅医療等の「治し支える医療」が重要となりますが、織田病院では、以前から在宅医療に力を入れていますね。
織田 当院は、佐賀県南部医療圏にありますが、後期高齢者のうち、年齢階級でみると「85歳以上」の割合が急激に上昇し、「75~79歳」「80~84歳」の割合を2013年時点で逆転したのです。都市部では、2030年頃に逆転するとされていますが、我々の医療圏では既にそれが起きているわけです。
その逆転で何が起きるのかというと、救急車の搬送件数・新規入院患者の急激な増加、病床回転率の低下、救急の受入困難です。70代後半、80代前半であれば、退院支援を必要とする患者さんはそう多くありません。しかし85歳を超えると途端に話が違ってきます。退院までに期間を要するので、病床が瞬く間に不足します。
この85歳以上人口の増加は、全国的に2030年ごろに必ず起こるわけです。早急な対応が必要だと感じています。実際当院でも、2004年から2020年にかけて、85歳以上の救急搬送が2.6倍、新規入院患者数は3倍に増加しています。ですが、当院の病床数は117床のみです。そのうち新型コロナ即応病床が20床です。つまり、単純に退院後の受け皿が足りないのです。だからこそ患者さんをご自宅に帰し、在宅医療で対応する必要がでてきます。そういう意味では、地域医療構想と地域包括ケアシステムが円滑に連携し、2本柱でうまくいくことが重要です。
──だからこそ、「次世代型退院支援」が必要なのですね。具体的な取り組みを教えてください。
織田 入退院支援を行う「リエゾンナース」の配置、多職種協働で退院後もケアの継続を行う「メディカルベースキャンプ(以下、MBC)」の設置、ICT機器を活用した「在宅見守りシステム」の構築、「オンライン診療」の活用が大きなところでしょうか。
──リエゾンナースの具体的な役割について教えてください。
織田 当院では退院支援が専門のナースをリエゾンナースと呼んでいます。地域の診療所や介護施設、院内のスタッフと連携し、入院直後から退院支援の対象を選定しています。10年ほど前にこの仕組みを開始してから、退院支援が効率的になりました。85歳以上人口が増加した一時期、リエゾンナースだけでは上手く機能しなくなりましたが、薬剤師、管理栄養士、MSW等の専門職を病棟に専属配置することで対応しました。それまで、各職種が各部署に配置されていましたが、病棟専属配置後は互いの顔が見え、円滑に連携がとれるようになりました。
──では、MBCにはどのような役割があるのでしょうか。
織田 MBCでは、医師・訪問看護師・リハビリスタッフ・ケアマネ等が連携して、ターミナルや特別訪問看護指示書が出た患者さんに対して、退院直後の2週間を対象に、在宅ケアを行います。この期間が非常に重要で、放置すると途端に、ADLが低下し、栄養状態も悪化し、酷い場合は再入院となってしまいます。逆に、この2週間を乗り切れば、入院前の生活に戻っていける可能制が高い。加えて、かかりつけ医の先生にお戻しする際の負担が減ります。
在宅医療に効率化は欠かせない AI・ICT機器の積極的な導入を
──そして、MBCで「在宅見守りシステム」を運用しているのですね。
織田 「在宅見守りシステム」では複数の機器を組み合わせて、在宅患者の健康を見守っています。MBC内の大型のモニターにマップが表示されており、患者さんの自宅や、スタッフの位置と状況がリアルタイムで把握できます。
たとえば、温度センサーを患者さんのご自宅に設置し、29度を超えた時点で、MBCのモニターにアラートを出し、患者さんの熱中症を防ぎます。
また、患者さんのご自宅のテレビを利用した「ビデオ通話」により、患者さんと会話をすることができます。これがうまくいったのは、テレビを用いたからです。普段使い慣れているリモコンであれば、操作も簡単でタブレット端末等と違い心理的な抵抗も少ないのだと思います。物理的なボタンがあるということも大きいのでしょう。当然、クリアしなければならないセキュリティの問題等はありましたが、訪問看護の効率化にも寄与しました。
他にも、転倒検知装置や患者さんの睡眠時の状態を確認できるベッドスキャン等、さまざまな機器を活用しています。
──その上でオンライン診療にも取り組まれているわけですね。
織田 オンライン診療は、今後の地域医療を支えていくためには不可欠です。コロナ禍でオンライン診療が進み、高齢の患者さんお1人での受診は難しくても、ご家族のフォローがあれば、かなりの部分の対応が可能です。患者さんにはスマートデバイスを身につけてもらい、脈拍や血圧等の情報がスマホを通じて送られてきます。
オンライン診療は現在、高齢の患者さんに積極的に受け入れられています。というのも、高齢の患者さんは、通院自体が非常に困難で、いざ病院に行こうとすると、丸1日がかりです。ご家族の方からしても、負担は同様です。
──織田病院では、ICTの導入に積極的ですが、AIの導入については、どのようなお考えですか。
織田 AIの導入については、現在もチャレンジの真っ只中です。現在は、AIによる退院支援の分析に取り組んでいます。MBCが持っている情報を、文字情報も含めてすべて数値化し、ディープラーニングを行って分析をしました。そこでわかったのは、退院支援対象者の選定の判断は「ほぼ正しい」ということです。
MBCで退院支援の対象外としていた患者さんは、AIも対象外でしたし、MBCが退院支援の対象としていた患者さんは、AIも同様でした。一方で、MBCが退院支援の対象外としていた患者さんの中に一定数、AIが対象とした患者さんがいたのです。医師や専門スタッフの見落としを防いだわけです。
今後はAIが作ったたたき台を元にMBC内で議論するようになるでしょう。1から退院支援者を選定するより効率化できます。
医療や介護は労働集約型の仕事ですが、今後はその労働力がどんどん減少していくわけですから、業務の効率化は避けては通れません。そのためにも、活用できるAI・ICT機器は積極的に導入するべきだと思います。
(2023年5月22日/構成・本誌編集部 伊藤之陽)