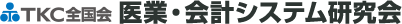クリニックの「税」のあれこれ 第7回 確定申告で注意すべき点は?
TKC全国会 医業・会計システム研究会 湯浅 浩一
いよいよ、年に1回の所得税確定申告の時期がやってきます。令和6年分については定額減税への対応と財産債務調書の提出期限の変更(令和6年分申告分から翌年6月30日に変更)が改正点として留意すべき事項になります。今回は基本となる所得金額とその経費を中心に解説します。
Q 開業後初めて確定申告をするのですが、どのようなことに気をつけるとよいのでしょうか。
A 所得税額は1年間のすべての所得金額から所得控除額を差し引き、税率を適用して計算します。すべての所得金額とその経費等に漏れがないことが大事になります。
1.所得金額
所得税法においては、所得は10種類に区分されますが、そのうち開業医に関わる主な収入は「事業所得」「給与所得」「一時所得」「雑所得」の4つです。
(1) 事業所得
事業所得は、「①事業収入」から「②事業経費」を控除した金額が事業所得金額になります。 ①事業収入:保険診療収入、自由診療収入、文書料、窓口等における物販収入などの雑収入が該当します。知人や職員などを無償で診療した場合も自由診療収入などに計上が必要です。保険診療収入は社会保険診療報酬支払基金が発行する源泉徴収票などで再度確認をします。
②事業経費:薬剤、医療材料の仕入高などの販売原価、看護師などの人件費、医療機器やレセコンのリース料、家賃、中小企業倒産防止共済、専従者給与など事業を運営、維持するためにかかった支出が事業経費(以下「実額経費」)として認められます。
(2) 給与所得
その年、開業前に勤務していたときの給与だけでなく、開業後でも他の医療機関、福祉施設や製薬会社から給与所得として収受した場合は、給与所得となります。(3) 一時所得
生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などがある場合は一時所得となります。一時所得の金額は、次のように計算します。 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
ふるさと納税の返戻品についても一時所得として課税対象となりますので忘れずに計上しましょう。返戻品の収入金額の計算方法は次のいずれかによります。
①寄附先の自治体へ相談・確認し計算する方法
②寄附金額×30%(総務省の通達によりお礼の品の原価は寄附額の3割以内から推計)
(4) 雑所得
公的年金の受給や製薬会社などから得る講演料、執筆料などが該当します。それぞれ公的年金等控除額や必要経費が控除できます。2.事業経費の注意点
(1) 人件費 給与、雇用保険や厚生年金などの法定福利費、職員の飲食代や忘年会費用なども含む福利厚生費が該当します。人件費を必要経費として計上するにあたっては、給与明細書の控えなどを保存しておくことが大切です。 また、所得拡大促進税制の適用を受けると、その増加額の一部を税額控除できる場合がありますのでご検討ください。
(2) 青色事業専従者給与
原則として、生計を一にする配偶者などに支払う給与は必要経費として認められませんが、次の3つの条件に該当している場合は必要経費として認められます。
①青色申告者と生計を一にする配偶者そのほかの親族であること
②その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
③その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事できる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の事業にもっぱら従事していること
前記③の条件に関しては税務当局のチェックが厳しく、「業務量が極端に少ない」「資格を保有しているが勤務実態がない」などの理由から否認される場合があるので、タイムカードや業務日誌等の記録を残しておきましょう。
(3) 家賃・設備費
家賃、駐車場代、水道光熱費、通信費、医療機器の購入費またはリース料などが該当します。医療機器や消耗品の購入費のうち、金額が10万円以上、かつ、使用可能期間が1年以上のものは減価償却資産として耐用年数に応じた経費となります。
(4) 接待交際費
事業に直接関係する支出であれば、金額の大小に関わらず全額経費として計上できますが、税務調査で指摘を受けやすい項目です。
所得税では接待交際費の金額に上限はありませんが、口頭だけの説明で税務当局が納得することはありません。領収書には人数や相手方の氏名、会社名、住所、会った理由・目的等、事業に直接関係のある旨を細かくメモに残しておくようにしましょう。
(5) 家事按分
車を購入した際、その車を事業とプライベートの両方で使うことがあります。このような場合は、「家事関連費」として、支出額などを事業用と自家使用とに分けることで、事業用部分は経費にできます。
同様に、診療所兼自宅の建物などの減価償却費、水道光熱費(メーターを区分していない場合に限る)、固定資産税なども事業用部分は経費にできます。
按分の方法に明確なルールはなく、床面積や業務時間、日数、使用時間などの割合を基準とするのが一般的です。合理的な説明ができることが重要になります。
3.社会保険診療報酬の所得計算の特例へ
個人開業医の場合、実額経費との有利判定で租税特別措置法第26条「社会保険診療報酬の所得計算の特例」を利用することで、概算経費で税額計算できます。特例を利用する要件は、社会保険診療報酬が5,000万円以下であり、かつ、自由診療等を含めた医業活動から生ずる総収入金額が7,000万円以下である場合に限られています。特例を適用するかどうかは、毎年選択することが可能です。
ただし、特例を利用した場合は、青色事業専従者給与を適用できませんので注意してください。
有利判定は、次のように比較検討するとよいでしょう。
①実額経費(青色事業専従者給与計上前)>概算経費
⇒実額経費が必ず有利に
②実額経費(青色事業専従者給与計上前)+青色事業専従者給与>概算経費
⇒実際に双方を計算し検討
③実額経費(青色事業専従者給与計上前)+青色事業専従者給与<概算経費
⇒概算経費が必ず有利に
また、特例を適用する場合でも、自由診療など社会保険診療報酬以外にかかる経費は実額経費を算出しなければなりません。
普段はほとんど税理士にお任せしているという方も、所得金額に漏れがないか、改めてしっかり把握しておきましょう。
次回は医療法人化(法人成り)の利点や注意点などについて解説します。
(TKC医業経営情報2025年2月号より)