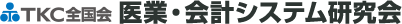クリニックの「税」のあれこれ 第5回 「三共済制度」をご存じですか?
TKC全国会 医業・会計システム研究会 櫻井 裕子
「小規模企業共済」「中小企業倒産防止共済」「中小企業退職金共済」の三共済制度について、言葉は聞いたことがある院長先生もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、効果的に活用すると節税や税制優遇、資金調達が可能となる三共済制度について解説します。。
Q 三共済制度では節税になることもあると聞いたのですが、医療機関は加入できるのでしょうか。
A 医療法人の場合、「中小企業退職金共済」に加入できます。個人開業医の場合は、「小規模企業共済」「中小企業倒産防止共済」にも加入可能です。
1.中小企業退職金共済とは
従業員の退職金制度はあくまでも「任意制度」です。特に医療機関では人材の流動性が比較的高いため、退職金制度がなじまないとされることもあります。しかし、医療機関は経営者だけでなく従業員の資質も経営に大きな影響を及ぼすため、良い人材を確保することが経営課題となります。
医療機関に退職金規程があり、将来の退職金が保証される仕組みは、優れた従業員の確保と定着率向上に寄与します。退職金準備の手段として、投資金額が比較的少額から始められる「中小企業退職金共済」を活用することは有効な経営手段の1つです。
この制度は、単独で従業員の退職金制度を設けることが困難な中小企業の実情を考慮し、国等の援助を得ながら退職金制度を確立するものです。掛金は月額5千円から1万円までは千円刻み、月額1万円から3万円は2千円刻みと幅広く選択することが可能です。ただし、従業員が1年未満で退職した場合には共済金は不支給であり、掛金納付月数が12か月以上24か月未満は元本割れ、24か月以上42か月以下は掛金相当額、43か月経過すると、掛金を上回る退職金が受け取れます。
特徴としては次の通りです。
①掛金は全額損金・必要経費として計上可能
②国の掛金助成制度がある
③掛金月額はいつでも増減可能(減額は従業員の同意が必要)
注意すべき点として、加入する際には従業員全員を加入させることが原則であり、退職金規程などの整備も検討が必要です。また、退職金の受け取りは、掛金を支出したクリニック等ではなく、従業員本人に直接支給されます。退職後の手続きは不要ですが、注意が必要です。
2.小規模企業共済制度とは
小規模企業共済とは、小規模企業(事業者)の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などを積み立てられる制度のことです。クリニック経営者にとっても、リタイア後の生活資金を準備するための退職金は重要です。
個人でクリニックを経営している場合、院長先生の将来の退職金の準備をしつつ、掛金が全額所得控除されるため、現在の所得税を節税でき、退職金等受け取り時にも税制上の優遇を受けられます。また、事業資金の借入れも可能です。小規模企業共済への加入は有益な方法といえます。
ただし、医療法人設立後の加入はできないので注意が必要です。そのほかに次の特徴があります。
①掛金増減が可能、全額所得控除に
掛金は、月額千円から7万円まで設定可能で、加入後は500円単位でいつでも変更できます。個人所得税の1年間の節税効果は図表を参照ください。
②退職時の共済金受け取り時も税制上の優遇あり
第一線をリタイアされたときに、それまで積み立ててきた掛金に応じて利息相当額が上乗せされて共済金を受け取れます。共済金の受け取り方法は、「一括」、「分割」、「一括と分割の併用」の3つの方法があり、受け取る共済金の種類や額に応じて選択可能です。一括受け取りの場合は「退職所得扱い」、分割受け取りの場合は「公的年金扱い」となり税制上優遇を受けられます。
③加入資格
個人開業医の場合、加入資格は従業員の数が5人以下であることです。開業後、クリニックが拡大する前に加入する必要があります。また、加入対象者は、個人開業医の配偶者や後継者などの「共同経営者」 までです。
④留意点
早期解約の場合に受け取り額が減少する点が挙げられます。掛金納付月数が240か月未満で任意解約すると、共済金は掛金合計額を下回ります。また、共済金A・B※は掛金納付月数が6か月未満の場合、準共済金・解約手当金は掛金納付月数が12か月未満の場合は、共済金を受け取れません。
法人成りを予定している場合は加入資格を喪失するため、加入を慎重に検討する必要がありますのでご注意ください。なお、MS法人の役員(医療法人の役員と兼任は禁止)であれば、一定の要件を満たせば加入可能です。
※共済金A:個人事業廃業または死亡。共済金B:65歳以上で老齢給付を受ける場合。準共済金:法人成りで加入資格を喪失した場合。解約手当金:任意解約時に支給される金額。
3.中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは
中小企業倒産防止共済は、節税とリスク対策を同時に実現できる制度です。これは中小企業の連鎖倒産を防ぐための制度で、取引先の倒産などにより売掛債権が回収困難となった場合に、無担保・無保証で掛金の最大10倍(上限8,000万円)まで借入れ可能です。掛金が全額経費となり、40か月以上納付していれば掛金の全額が戻ります。
なお、こちらも医療法人は加入できません。開業医にとっては検討の価値がある共済ですが、解約して受け取った共済金は全額収入になるため、解約のタイミングを見定める必要があります。そのほかの留意点は次の通りです。
①加入資格
クリニックの場合、加入資格は常時使用する従業員の数が100人以下の個人事業主です。
②掛金は全額経費計上が可能
掛金月額は5千円から20万円で、いつでも増減可能です。積立上限額は800万円までとなっており、たとえば大きな利益が出ている年は期末に240万円を事業所得の必要経費・損金計上して、節税対策が可能です。
③緊急時の確実な資金調達が可能
取引先の倒産により売掛金が回収困難となった場合、詳細な金融審査を行わず、倒産取引先の概況等の事実確認のみで、積立金掛金の10倍の金額(最高8,000万円)まで低金利で借入できます。
しかし、この制度の本来の目的である共済金の貸付は一般消費者に対する貸付が対象ではないため、クリニックなどの医療機関は貸付を受けることが難しい業種とされています。
④解約時も40か月以上の納付で100%返戻
定期的な修繕や設備入れ替えの資金を目標に、40か月以上掛金を積立て、解約時にその資金に充てたり、業績の悪い年に解約して損失の補塡に利用できたりします。ただし、一部解約はできません。再加入も可能ですが、令和6年10月1日以降に解約・再加入した場合は、解約日以降2年間、掛金を損金または必要経費に計上できなくなるためご注意ください。
⑤医療機関は個人から法人成りした場合に通算できない
医療法人は、共済契約者の地位を引き継ぐことができません。そのため、医療法人成りした際は解約手当金を全額個人事業の収益に計上することになります。
三共済制度を活用することで、節税しつつリスク対策を行うことが可能です。ただし、加入後にデメリットが生じる可能性もあるため、加入に際しては顧問税理士と十分に相談することをお勧めします。
次回は税務行政におけるDXと医業経営の関係について解説します。
(TKC医業経営情報2024年12月号より)