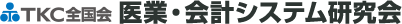クリニックの「税」のあれこれ 第2回 クリニックが法人成りしたときに土地や建物はどうする?
TKC全国会 医業・会計システム研究会 加藤田 敏孝
クリニックが法人成りした後、クリニックの土地建物などの院長所有資産を誰が所有するかによって、所得税額などは変わります。また、理事長の自宅を医療法人の社宅扱いにすることで、減価償却費や維持費を医療法人側の経費として算入するという選択肢もあります。
Q クリニックを医療法人に移行させたのですが、これまで院長(理事長)個人で所有していたクリニックの土地や建物はそのまま所有していてもよいのでしょうか。
A 個人で所有し続けるほかに、設立した医療法人への移行や、MS法人を設立しそちらに移行させる方法も考えられます。メリットとデメリットを比べて判断しましょう。
法人成り後の土地建物は誰が所有すればよいか
クリニックが法人成りした後、理事長先生が所有していた、クリニック・自宅の土地建物の所有者をどうするかについてはいくつかの方法があります。ここでは、クリニックの土地建物(駐車場敷地を含む)について説明します。
⑴ 個人で所有し続ける
まず考えられる方法は、クリニックの土地建物を個人で所有し続けるという方法です。
個人所有の物件を医療法人に賃貸することとなりますので、医療法人は理事長先生個人に地代と家賃を支払い、個人には不動産所得が入ります。親族承継や第三者承継で、初代理事長が引退しても、そのまま土地建物を所有し賃貸すると、初代理事長は安定した収入を受け続けられます。
一方で、個人開業後すみやかに法人成りした場合には、役員報酬と不動産所得の両方を個人で受けることとなり、所得税の税率が高くなってしまいます。また年間の家賃収入が1,000万円を超える場合には、消費税の課税事業者となることにも留意が必要です。
⑵ 医療法人に移行する
医療法人の設立時に土地建物を現物出資する方法もあります。
それに合わせて個人の借入を医療法人に移すこともできますが、移行できる借入は設備投資部分に限られ、運転資金部分の移行はできません。個人の借入金を大幅に減らすことができるのはメリットですが、すべての移行はできないこと、また不動産の移行により、不動産取得税、登録免許税のほか、理事長先生に譲渡所得税が発生することがデメリットとなります。なお、法人設立時でなくとも、医院建物や医療機器と、借入金を『負担付贈与』という方法で両者をバランスさせ、医療法人に移行することもできます。
⑶ 別法人に移行する
一般法人(メディカル・サービス(MS)法人)を設立し、そちらに不動産と借入金を移行するという方法もあります。
この方法のメリットとしては、医療法人は毎月MS法人に家賃を支払い、安定したコストを計上することができます。また初代理事長は不動産をMS法人に移行することにより、売買代金の収受以降は、家賃収入がMS法人に入るため理事長先生自身のキャッシュ増加を防ぐことが期待できます。
デメリットとしては、法人の設立コストが発生すること、また法人を維持するためのコスト(均等割などの税金や税理士報酬など)が発生するということが考えられます。さらに⑵と同様に不動産の移行時に不動産取得税、登録免許税、譲渡所得税が発生します。
このように、どの方法も一長一短あり、これがベストというものはありません。ご自身のクリニックの状況に合わせて、どの方法がよいのかご検討ください。。
医療法人化で自宅を社宅扱いにする方法とは
医療法人化によるメリットの1つとして、理事長先生や職員の住居を社宅として扱うことで、今まで経費とならなかった自宅建物が、医療法人側で減価償却費や維持費の経費算入が可能になります。
医療法人化による所有者の移行ではさまざまな税の取扱いが生じます。また、社宅とする方法では貸与するのが使用人(職員)の場合と、役員(理事長先生)の場合で注意点が異なります。今回は役員に対する社宅のケースで、家賃設定時の取り扱いについて、留意すべき点を解説します。
医療法人で社宅の導入を検討する場合、税法だけでなく、医療法にも配慮する必要があります。厚生労働省の『医療法人の業務範囲〈令和4年2月22日現在〉』「Ⅱ.附帯業務」の留意事項には、以下のように記されています。
1.役職員への金銭等の貸付は、附帯業務ではなく福利厚生として行うこと。この場合、全役職員を対象とした貸付に関する内部規定を設けること。
また同じく「Ⅳ.付随業務」には以下のように記されています。
また同じく「Ⅳ.付随業務」には以下のように記されています。
①病院等の施設内で当該病院等に入院若しくは通院する患者及びその家族を対象として行われる業務又は病院等の職員の福利厚生のために行われる業務であって、医療提供又は療養の向上の一環として行われるもの。
つまり理事長先生の社宅が、医療提供・療養の向上の一環として運営されるのであれば、それらは認められます。ただし、理事長先生1人のためではなく、全職員を対象とした社宅運用規程を作成し、その一環として理事長の社宅が運営されていることが必要といえます。
また当然ではありますが、適正な家賃を支払うことも必要です。
税法上の「適正な家賃」はどのように算出する?
医役員に対して社宅を貸与する場合、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下、「賃料相当額」)を受け取っていれば、給与として課税されることはありません。
賃料相当額は、貸与する社宅の床面積により「小規模な社宅」と「それ以外の社宅」に分け、図表のように計算します。ただしこの社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められない、いわゆる「豪華社宅」である場合はこの適用はなく、通常支払うべき使用料相当額が賃貸料相当額となります。
社宅の要件を満たすための体制を整え、適正な賃料を徴収することで、税務署からの指摘を受けないように対応することが必須となります。
次回は医療機関の交際費の判断基準や、交際費と厚生費との違いなどについて解説します。
(TKC医業経営情報2024年9月号より)