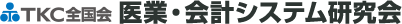クリニックの「税」のあれこれ 第1回 家事関連費はどこまで認められる?
TKC全国会 医業・会計システム研究会 石川 誠
今回より、診療所を運営する上で知りたい・知っておくべき、クリニックに関する「税」について、院長先生からの相談が多い内容を中心にピックアップし、誌面上で解説します。第1回は家事関連費について説明します。
Q 当院はクリニックと自宅が一体になった建物なのですが、水道代や電気代の請求は一緒になって届きます。どこまでが必要経費として認められるのでしょうか。
A 診療所併用住宅の水道光熱費のように、事業のための支出と、生活のための支出が混在した支出のことを「家事関連費」といいます。こうした支出は、使用割合や時間などの合理的な基準で区分計算をして、必要経費に算入します。
「家事費」とは?
「家事関連費」とは?
「どのようなモノが必要経費として認められるのか?」という質問は、いつの時代も関心が高い問題です。何故ならば、必要経費として認められるかどうかで、納める税金の金額に影響するからに他なりません。
今回は個人事業者の所得税に関する規定を中心に解説します(法人については別の機会に述べることにします)。
個人事業者は、経営者であると同時に生活者であるという2つの側面を持っているために、現金や通帳などからの支出には、事業のための支出(必要経費)と、生活のために消費した支出(家事費)の2つがあります。
そして、その必要経費と家事費が混在した支出のことを「家事関連費」といい、判断が必要になります。
所得税法45条には家事上の経費は必要経費に算入しないとし、そのほかの事例として、所得税、道府県民税、市町村民税、それらの延滞税、過少申告加算税、罰金、科料などが挙げられていますが、これらに関しては明確であるため議論の余地はありません。
所得税法施行令96条1項には、「家事関連費の主たる部分」が診療所経営に必要であり、明確に区分できる場合は必要経費にできるとされています。
ここでいう「主たる部分」とは、業務に必要な部分の金額が50%を超えるかどうかで判定しますが、50%以下でも金額が明瞭に区分できる場合は必要経費にしても差し支えない(所得税基本通達45-2)とされています。
青色申告の場合は上記に該当するもののほか、取引の記録等に基づいて業務の遂行上直接必要であることが明らかであれば必要経費に算入できるとしています。
税法の文章は難解ですが、要するに「事業に直接必要である」「明確に区分できる」ということがポイントとなります。。
税法の文章は難解ですが、要するに「事業に直接必要である」「明確に区分できる」ということがポイントとなります。。
何が家事関連費になるのか
どこまで必要経費に算入できるか
では、具体的にどのような支出が家事関連費として検討すべきなのでしょうか。主なものを挙げてみましょう。
まず、診療所併用住宅については、家屋の減価償却、家賃、修繕費、固定資産税、火災保険、支払利息などが挙げられ、これら建物の減価償却や家賃等は事業用部分の床面積割合などで合理的に案分計算できます。
また、建物に取り付けられている電気、水道、ガスの水道光熱費や電話等の通信費は、使用割合や使用時間等の合理的な基準で区分計算をして必要経費に算入します。
これらの区分計算は、併用住宅でなく診療所と自宅が離れていたとしても「事業に直接必要である」「明確に区分できる」部分は必要経費に算入できることになります。
次に自動車関係です。車両の減価償却、ガソリン、自賠責保険、任意保険、車検、点検、自動車税、重量税、駐車場代、割賦利息などが対象となります。
このほかの事例は下図「必要経費に関する判断の事例」を参照してください。
ここまで、主に診療所の事業経営に関する家事関連費について述べましたが、アパート経営による不動産所得、山林所得又は原稿料などの雑所得についても同様の考え方で判断することになります。
ここまで、主に診療所の事業経営に関する家事関連費について述べましたが、アパート経営による不動産所得、山林所得又は原稿料などの雑所得についても同様の考え方で判断することになります。
研修医の子どもへの給与は原則として必要経費にならない
それでは、親族に対する給与はどうなるか見ていきます。所得税法56条には事業に従事する親族に対する対価の支払い(給与)は必要経費に算入しないとされています。
したがって、たとえば一緒に暮らす研修医の息子さんがときどき診療所を手伝ってくれるので、その対価として給与を支払ったとしても、原則として必要経費になりません。
しかし、青色申告の届けを出して、税務署長から承認を受けていれば、親族に対する支払いであっても一定の条件の下に必要経費に算入することが認められています。
また、白色申告であっても事業専従者は一定の条件の下に事業専従者としての控除額が認められています。
したがって、たとえば一緒に暮らす研修医の息子さんがときどき診療所を手伝ってくれるので、その対価として給与を支払ったとしても、原則として必要経費になりません。
しかし、青色申告の届けを出して、税務署長から承認を受けていれば、親族に対する支払いであっても一定の条件の下に必要経費に算入することが認められています。
また、白色申告であっても事業専従者は一定の条件の下に事業専従者としての控除額が認められています。
家事部分の消費税の扱いはどうなるのか
消費税法基本通達11-1-4には、個人事業者が資産を事業と家事の用途に共通して消費し、又は使用するものとして取得した場合、その家事消費又は家事使用に係る部分は課税仕入れに該当せず、合理的な基準により区分計算するとしています。
したがって、会計処理としては税込みと税抜きに分かれますが、いずれにしても、家事関連の部分については課税仕入れにはなりません。
税務調査では何を調べられる?
必要な準備は?
税務調査は税務署が必要と判断した場合や、外部からの情報がある場合などに行われることもありますが、基本的には収入の漏れや必要経費の内容について調査が行われます。
税務調査では、家事費が経費に含まれていないか、元帳や領収書を基に質問されることがありますので、事業との関連性や必要性について答えられるようにしておくことが必要です。
このうち、家事関連費については、明確に区分できることや区分計算に客観的な合理性があるのかがポイントです。毎年の確定申告のときにはあらかじめ顧問税理士と打ち合わせをしておくことが大切です。
区分されていなかったり、区分計算に恣意があるとみなされると必要経費として認められず、自ら修正申告をするか、税務署により更生決定をされることになり、税金を納めなければなりませんので注意が必要となります。
このうち、家事関連費については、明確に区分できることや区分計算に客観的な合理性があるのかがポイントです。毎年の確定申告のときにはあらかじめ顧問税理士と打ち合わせをしておくことが大切です。
区分されていなかったり、区分計算に恣意があるとみなされると必要経費として認められず、自ら修正申告をするか、税務署により更生決定をされることになり、税金を納めなければなりませんので注意が必要となります。
次回は会計上の社宅の処理や、法人成りの際の賃貸借の扱いなど、不動産関係について解説します。
(TKC医業経営情報2024年8月号より)